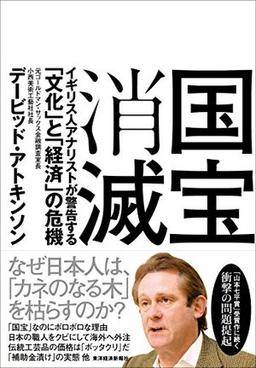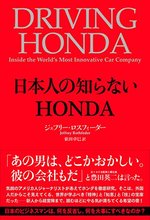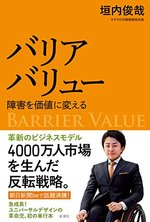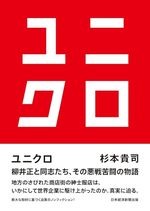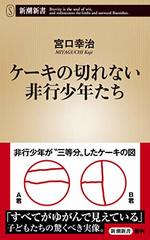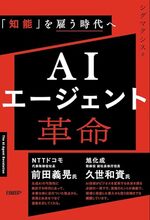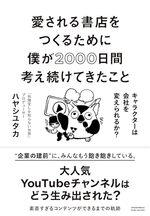なぜ今、「文化財の大転換」が必要なのか
観光立国をめざすための秘策
人口減少が著しく、GDPの大きな伸びを期待できない日本において、社会保障費をどう捻出するかは喫緊の課題である。日本経済を立て直すために、著者は観光立国をめざすべきだと提言している。現在、日本のGDPに観光業が占める割合は約3%にすぎない。そこで、世界的には第4の基幹産業となっている観光業に力を入れ、外国人観光客という「短期移民」を募ることにより、日本の観光業は50兆円以上の産業へと成長することができると目されている。
その観光業を構成する重要な柱が「文化財」だ。人口減少により、寺社仏閣の維持に欠かせない「氏子」や「檀家」、そして国内観光客の数が急激に減少する今、日本各地の文化財は「一生に一度行けばよい」という観光地から、リピーターを生み出す魅力的な観光資源へと転換することを余儀なくされている。
これまで、文化財関係者の大多数には、「稼ぐ」「売る」「PRする」という発想が根づいてこなかった。また、行政の根幹には、「優れたものを選定し、補助金(税金)を投入して手厚く守る」という考えがあり、これが芸術や文化の発展をむしろ阻害してきたのだ。
文化財を観光資源化することで得られる4つの効果

こうした行政の方針を見直し、文化財の業界を産業化することで、次の4つの効果が期待できる。1つ目の効果は、文化財を観光資源として整備することで、観光立国の実現を果たし、社会保障制度を支える屋台骨を築けるという点だ。2つ目の効果は、手厚すぎる保護行政を調整することで、観光客の満足度を上げ、観光客から文化財維持費を得られるという点である。3つ目の効果は、日本文化の伝承を担う教育施設へと文化財を進化させることで、人々が日本古来の歴史や習慣、美意識を身近に学ぶことを可能にするという点だ。最後に4つ目の効果は、文化財の修理の現場を増やすことで、伝統技術の継承に寄与するという点である。
日本には北から南まで、多種多様な建造物や地域の特色が息づいた伝統が残っており、これらは観光資源としてのポテンシャルを大いに秘めている。文化・文化財を「収入源」とみなす意識を日本人が持つようになれば、文化的な衰退を食い止め、日本の街並みを守ることにもつながるだろう。
上記のことからも、日本の文化財行政に「国際観光戦略」という視点を盛り込むという大転換が急務だといえる。
【必読ポイント!】 「日本文化離れ」を食い止める方法
家庭や日常生活から消えゆく日本文化

文化財は、観光資源としてはもちろん、