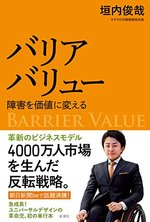日本人の知らないHONDA
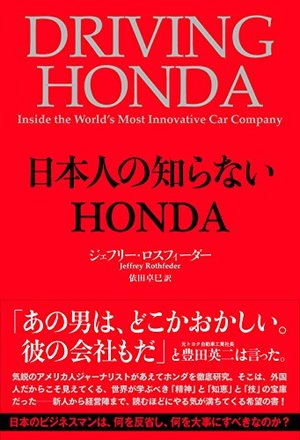
日本人の知らないHONDA
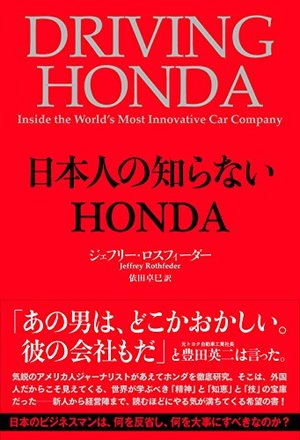
著者
ジェフリー・ロスフィーダー
ジャーナリズム分野で数々の賞に輝いてきたベテラン・ジャーナリスト。これまでにオンライン・ニュース・メディア「インターナショナル・ビジネス・タイム」やPCマガジンの編集長を務めたほか、タイム誌やビジネスウィーク誌の編集、あるいはワシントンポスト紙の特派員など、広範な場で活躍。また、その守備範囲は、リーダーシップからマネジメント、企業文化、グローバリゼーションなどじつに多岐にわたる。ウォールストリート・ジャーナルベストセラーのMake or Breakほか、話題を呼ぶ著書も多数。
ジャーナリズム分野で数々の賞に輝いてきたベテラン・ジャーナリスト。これまでにオンライン・ニュース・メディア「インターナショナル・ビジネス・タイム」やPCマガジンの編集長を務めたほか、タイム誌やビジネスウィーク誌の編集、あるいはワシントンポスト紙の特派員など、広範な場で活躍。また、その守備範囲は、リーダーシップからマネジメント、企業文化、グローバリゼーションなどじつに多岐にわたる。ウォールストリート・ジャーナルベストセラーのMake or Breakほか、話題を呼ぶ著書も多数。
本書の要点
- 要点1「ワイガヤ」は、ホンダを象徴する企業文化である。発言者全員が立場を超え、主観的意見や客観的意見を忌憚なくぶつけあうことで、ホンダの独創性は生み出されている。
- 要点2ホンダは「現場」を最優先にして物事を考える。そのため、中央集権的な指揮系統を持たず、各国の開発者の判断に多くを委ねている。
- 要点3ホンダが求めているのは、常識からはみ出すような個性の強い人材である。しかも自動車業界に離れた人物ほど歓迎される。なぜならそれまでの前例にとらわれないからだ。
要約
【必読ポイント!】 パラドックスを受け入れる
「ワイガヤ」がホンダを躍進させた

moodboard/moodboard/Thinkstock
ホンダの社員は、つねに互いを支えあって日々の職務を果たしている。一人ひとりの意見や提案は平等に扱われ、役職や地位を判断基準にすることは許されない。全員が作業服を着ているのは、全員が平等な立場にいるというメッセージだ。
そのホンダを象徴するような企業文化が「ワイガヤ」と呼ばれる話し合いである。これは、多くの人が同時にワイワイガヤガヤと話し合うことに由来する造語で、議論が白熱してアイデアが自由に出てくる様子や、意見がぶつかり合うなかで意思決定がなされる様子をあらわしている。
ホンダの創業者である本田宗一郎は常々、ものまねより独自性を重んじろと主張しており、ワイガヤもその考えから生まれた。ワイガヤには4つの基本的なルールが定められている。(1)ワイガヤでは全員が平等であり、悪いアイデアは存在しない。(2)すべてのアイデアについて、有効性が証明されるか完全に無効とわかるまで徹底的に議論する。(3)共有されたアイデアは発言者のものではなくホンダのモノになり、グループはそのアイデアを好きなときに使えるようになる。(4)ワイガヤの最後には意思決定がなされ、責任が生まれる。
営業、マーケティング、製造、保守部門にいたるまで、あらゆるところでこのワイガヤは行われている。1分程度で終わる時もあれば、1時間以上議論が続く時もあるという。このような習慣は、その他の企業や評論家たちにとって、奇妙に映るに違いない。生産性を無視しているように思えるし、成果につなげるために必要な強力なリーダーシップが欠けているように見えるからだ。
しかしこのワイガヤこそが、ホンダの創造性を大きく支えている。なぜなら、毎日何気なくワイガヤを行うことで、遠慮や見栄のない意見が自然と出てくるようになり、結果として画期的なアイデアが生まれてくるからである。
パラドックスを歓迎する
「労働者への権限委譲」か「生産性重視」、「多国間管理」か「現地の自治」、「ロボット」か「人手」――組織というものは常にこのようなパラドックスに悩まされているものだ。それにもかかわらず、ほとんどの企業はこういったパラドックスに対して、きちんと向き合うことを嫌う。矛盾する可能性を検討しはじめると、きりがないからである。
一方、ホンダにとって、このようなパラドックスに向き合うことは、恐怖であると同時にチャンスでもあるとされている。現状をつねに見直し、新たな方法で課題に対処する機会を提供してくれるものとしてパラドックスをとらえているからだ。そのような姿勢からは、あらゆる失敗は役に立ち、旧来の知恵はかならず疑ってみるべきだというホンダの哲学が垣間見える。
最高の戦略とは常に流動的であり、口に出した途端に古びてしまうからこそ、根気強く再評価を続けていかなければ、価値を維持することはできない。だからこそ、ホンダはあらゆるパラドックスを歓迎するのである。
イノベーションは管理できない
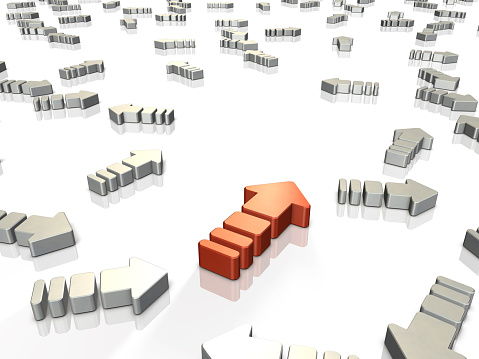
CYCLONEPROJECT/iStock/Thinkstock
ホンダはイノベーションに対する方針を明文化していない。

この続きを見るには...
残り3081/4353文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2016.07.20
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約