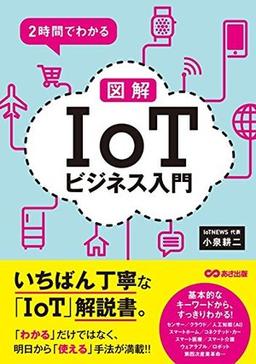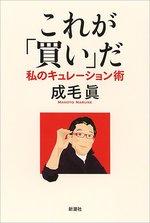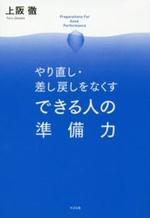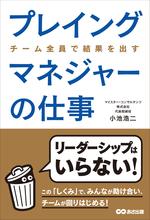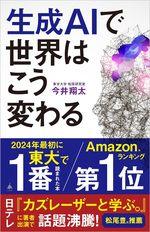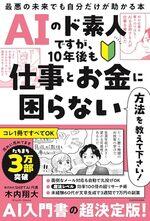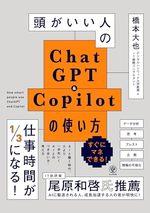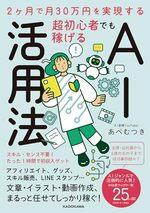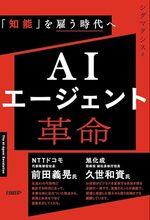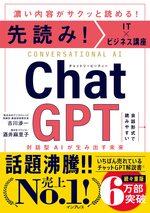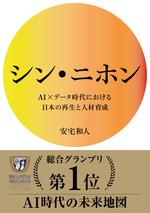IoTとは何か
IoTを読み解くキーワード
「モノのインターネット」の「モノ」とはいったい何か。身近なところでは、冷蔵庫やクルマなどを思い浮かべるだろう。しかし、椅子や机のような、一見インターネットに接続させることに意味がなさそうなモノをIoTの対象外としてしまうと、視野を狭め、チャンスを逃しかねない。IoTが扱うモノとは、「ありとあらゆるモノ」であり、IoTとは「ありとあらゆるモノがインターネットに接続する世界」を指す。
IoTには「センサー」で取得したデータを「クラウド」にアップロードし、「人工知能」がデータから学習し、その判断に従ってモノが「アクチュエート」するという流れがある。それぞれの用語について紹介していく。
まず、センサーの種類は多岐にわたり、温度、湿度、加速度、照度などの情報を取得する。そしてセンサーがデータを得ることをセンシングという。
クラウドとは、インターネット上に存在し、情報を処理するサーバ全体を指す概念だ。さらに、人工知能(AI)については、人が教えた情報をもとに判断する「機械学習」と、サンプルとなるデータをもとに機械自らがそれを応用して学習する「ディープラーニング」とがある。
次に、モノがアクチュエートするというのは、クラウドでおこなわれた判断に基づいてモノが動き、ヒトへフィードバックするということだ。
IoTでは、フィードバックの内容が、そのサービスの価値を左右する。もし自社でIoTサービスを考えているならば、そのフィードバックが社会のどんな問題を解決するのかを考えるべきだ。
モノがつながるメリットと課題

モノがインターネットにつながるイメージがわかないという人は「スマートロック」を思い浮かべてほしい。スマートロックは、スマートフォンのアプリを起動し、ボタンを押すことで自宅のカギが開くというものだ。カギを家族と共有するのも断然簡単になる。同じアプリをダウンロードしてもらい、自宅のカギを開ける権限を渡せばよいからだ。たとえ家族の誰かがスマートフォンを紛失しても、アプリを再度ダウンロードしてもらい、権限を与えさえすればよい。
ここで、あなたが不動産会社の営業パーソンだと仮定しよう。空室の内見の依頼があると、通常なら、あなたは管理会社や大家に連絡し、カギを受け取りに行かなければならない。軒数が増えれば、移動や調整による機会損失が生じてしまう。しかし、スマートロックを導入していれば、アプリへの権限譲渡・剥奪だけで手軽にカギを開けられる。するとお客さんは待ち時間が減って満足度が上がるうえに、乗り気なうちに気になる物件を回れるので、管理会社や大家にとっては成約率の向上につながる。そしてあなたの営業成績がアップするという「三方よし」の結果となる。
もちろんスマートロックの導入は簡単ではないだろう。不動産業界は古い体質で、今までの仕組みを変えたがらない管理会社や大家も多いからだ。まずは1件でも導入事例を作り、利便性を訴求し、徐々に社会インフラへ育てていくという粘り強さが必要だ。
このように、IoT製品を開発しただけではなかなか普及しないという障壁がある。本格的な普及をめざすなら、自動改札機にかざすだけで通過できるカード「Suica」をJR東日本が導入したときのように、突出した利便性や圧倒的な価格の低さによって生活者の支持を得られるモノであることが重要となる。
【必読ポイント!】 IoTが社会にもたらす変化とは
家電とIoT

IoTが家の中にどのような変化をもたらすのかをイメージしてみよう。まず、帰宅して「暑い」「寒い」と感じることがなくなる。なぜなら家が、あなたの帰宅を感知し、快適な室温に設定してくれるからだ。