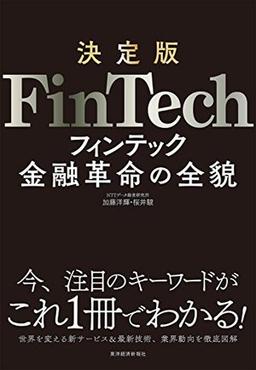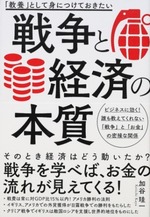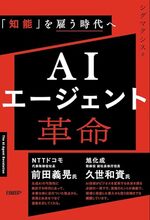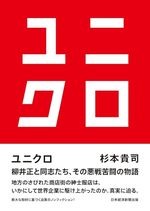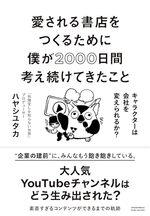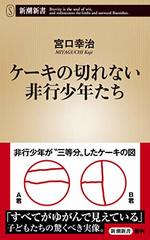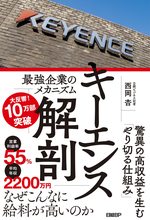フィンテックとは
PayPalがあたえた影響は大きい

フィンテックは、金融(ファイナンス)と技術(テクノロジー)という言葉を掛けあわせた造語であり、使われ方や文脈によって様々な意味を持つが、本書では「金融とITの融合によって生まれた、新しい金融サービス」と定義し、これを提供する企業を「フィンテック企業」と呼ぶ。
フィンテックの起源には諸説あるが、なかでも1998年のPayPalの創業は、非常に重要な出来事として位置づけられている。当時、様々なインターネットサービスが誕生しており、それに伴うオンライン上の決済の必要性が生まれたことで、新しいかたちの決済サービスが誕生したのだ。
PayPalの出身者たちがその後、テスラモーターズ、YouTube、LinkedInなどを創業していることからもわかるように、PayPalの成功はフィンテックだけでなく、シリコンバレー全体にとっても大きな影響をあたえた。
多様なフィンテックサービスの登場
現在、日本でフィンテックサービスの代表例としてあげられているのが、家計簿アプリや、お金の貸し手と借り手をマッチングするソーシャルレンディングサービスである。
家計簿アプリは、日本でも定着しつつある情報管理サービスであり、Money ForwardやZaimといったものが有名だ。一方、ソーシャルレンディングは、既存の金融機関からは融資が受けられないような層にも融資を提供するというサービスで、日本ではmaneoという企業がサービスを提供していることで知られている。
その他の分野だと、「送金」「投資」「業務支援」の領域は注目すべきである。フィンテック企業はこれらの領域において、既存の金融サービスに替わる新しいサービスを提供している。
日本はもともとフィンテック先進国だった
「金融とITの融合によって生まれた、新しい金融サービス」という意味では、実は日本はフィンテック先進国である。たとえば、マネックス証券など、低コストのオンライン証券サービスが誕生したのは1999年のことであり、ソニーやセブンイレブンなど、他業種がインターネット専業銀行に参入したのも2001年と早い時期であった。
しかし、日本人は商品やサービスを選択する際、ブランドで選ぶ傾向が強い。そのため、こういった新たなサービスを提供していたのは、スタートアップ企業ではなく、既存の大企業がほとんどだった。また、そもそも日本では、融資や決済といった規制分野の場合、スタートアップ企業は入ることができない。さらに、日本では既存の金融サービスの質が高かったため、ユーザーはもともとあまり強い不満を抱いていなかった。以上のような理由から、アメリカのように、スタートアップ企業がこれまで出てこなかったと考えられる。
【必読ポイント!】 ビットコインとブロックチェーン
ビットコインという革新

フィンテックの多くは、ITを利用することで、既存の金融サービスを新たな形で提供するというかたちをとっている。これに対し、ビットコインは全く新しいかたちの金融商品だ。「1975年のパーソナルコンピューター、1993年のインターネット、それに続くイノベーションが2014年のビットコインだ」と言われるくらい、ビットコインはフィンテックのなかでも画期的なのである。