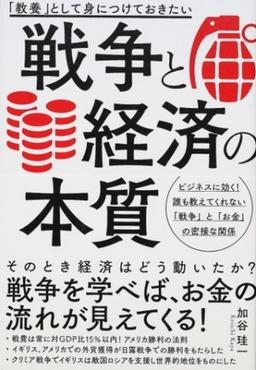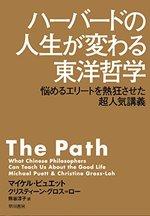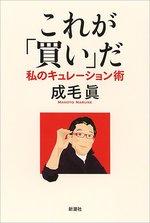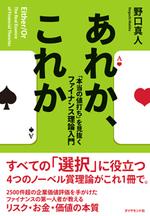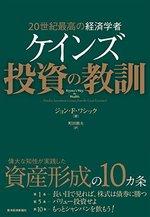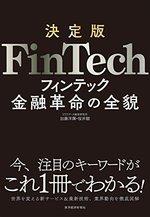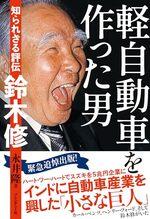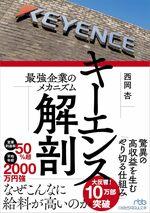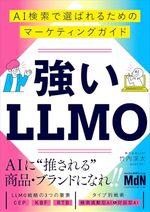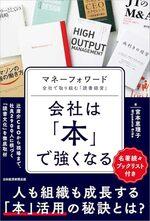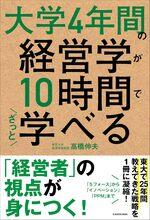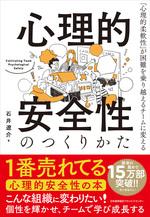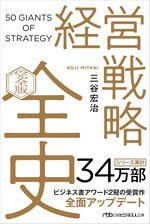戦争とお金の関係
GDPに占める軍事費の割合
戦争には多額のコストがかかると言われているが、実際にどのくらいのお金がかかるのだろうか。
戦争の現実はお金そのものであり、平時における軍事コストはGDPとの比較によって把握できる。各国のGDPに占める軍事費の割合は、米国は3.5%、中国は2.1%、日本やドイツは1.0%程度である。一般的にGDPの1%から3%程度の範囲が適正水準といえる。
中国をはじめとするアジア各国が軍事支出を年々増大させる一方、日本の軍事費(防衛費)は過去20年間ほとんど変わっていない。その理由は2つある。1つは日本政府が防衛費に上限を設定する政策を長く続けてきたこと、もう1つは日本がまったく経済成長していないことである。
有事の際の軍事費

大規模な戦争となるとその費用は平時と比べてケタはずれになる。日清戦争の際の日本の軍事費は当時のGDP比の0.17倍、日露戦争では0.6倍であったが、太平洋戦争では8.8倍にもなっていた。太平洋戦争は日本の経済力を無視した戦争であり、当然通常の手段では戦費の調達は不可能だった。この戦費のほとんどは日銀の直接引き受けによる国債発行で賄われた。
一方、米国の第二次世界大戦の戦費総額は、GDP比の3.2倍であり、日本と比べると相対的な負担はかなり軽かった。米国はその後、朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、イラク戦争という大きな戦争を実施しているが、各戦争の戦費負担はすべてGDP比の15%以内に収まっている。冷静に数字を見ると、少なくとも経済的にはそれほど大きな影響はなかった。
具体的な戦費の使途
2014年の米国の軍事費の内訳を例に挙げると、燃料や資材など軍事的なオペレーションの実施に必要となる経費が34%と最も多い。その後に、人件費23%、装備品の調達費16%、研究開発費11%と続く。兵器のハイテク化が進み、人件費の割合は低下している反面、装備や関連技術に対する支出が増加している。
戦争とマクロ経済の関係
GDPの中身は、消費・投資・政府支出
GDPの支出面は大きく分けて、個人消費、設備投資、政府支出に分かれる。普段あまり意識されないが、経済に占める個人消費の割合は絶大であり、個人消費が活発にならない国は強い経済を運営することができない。少し逆説的だが、戦争に勝つためには、豊かで活発な消費経済の存在が不可欠である。
また、投資は今年のGDPの数字に貢献するだけでなく、将来のGDPを生み出す原資でもある。消費と投資のよいバランスが作り出されると、経済は順調に回り始める。
戦争がGDPや金融市場に与える影響

戦争が発生するとGDP項目における政府支出が増えるが、多くの場合この資金は借り入れによって調達されるため、経済全体に様々な影響を及ぼす。例えば、国債の大量発行は金利を上昇させ、国内の設備投資を抑制するので、経済成長にとってマイナスの要因となり得る。また、大量の国債を中央銀行が直接引き受けるとなると、市中に大量のマネーを供給することになる。すると通貨の価値は減少し、ほぼ確実にインフレを誘発する。
株価は経済の先行指標
株価が上がるということは、多くの人がその企業の将来の売上や利益が増えると予想しているということである。これが一国の経済全体ということになると、その国が将来生み出す収益の期待値が株価となって現れるということになる。