ハーバードの人生が変わる東洋哲学
悩めるエリートを熱狂させた超人気講義
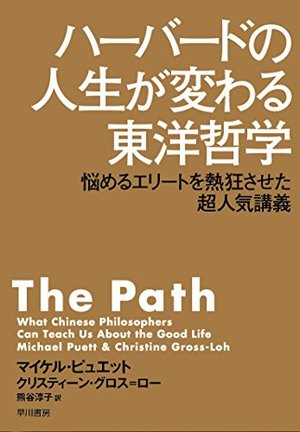
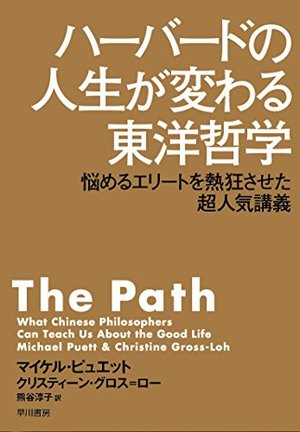
出版社
早川書房
出版日
2016年04月25日
評点
総合
4.2
明瞭性
4.0
革新性
4.5
応用性
4.0
著者
マイケル・ピュエット
Michael Puett
ハーバード大学東アジア言語文明学科の中国史教授。2006年より受け持つ学部授業の「古代中国の倫理学と政治理論」は、「経済学入門」「コンピュータ科学入門」に次いで学内3位の履修者数を誇る。卓越した学部教育により、ハーバード・カレッジ・プロフェッサーシップを受賞。
クリスティーン・グロス=ロー
Christine Gross-Loh
ジャーナリスト。ウォール・ストリート・ジャーナルやハフィントンポストなどに多数寄稿。ハーバード大学で東アジア史の博士号を取得している。
Michael Puett
ハーバード大学東アジア言語文明学科の中国史教授。2006年より受け持つ学部授業の「古代中国の倫理学と政治理論」は、「経済学入門」「コンピュータ科学入門」に次いで学内3位の履修者数を誇る。卓越した学部教育により、ハーバード・カレッジ・プロフェッサーシップを受賞。
クリスティーン・グロス=ロー
Christine Gross-Loh
ジャーナリスト。ウォール・ストリート・ジャーナルやハフィントンポストなどに多数寄稿。ハーバード大学で東アジア史の博士号を取得している。
本書の要点
- 要点1古代中国の思想家たちは、社会を問い直すにあたり、抽象的で壮大なテーマではなく、現実的かつ具体的な問いを探究し続けてきた。
- 要点2孔子は日常的な行為やしきたりを「礼」ととらえ、「礼」をくり返す中で、まわりの人を思いやる能力、すなわち「仁」が磨かれると説いた。
- 要点3老子によると、人間は柔らかさとしなやかさを活かすことで、真の影響力を発揮できる。最も影響力のある人は、無行為(無為)を実践して、相手の考え方を自然と変化させ、周囲に「世界」を生み出す人である。
要約
中国哲学が現代の私たちに教えてくれること
現実的で具体的な問いと向き合ってきた思想家たち
今日、自分の本当の姿を見つけ、内なる真にしたがって自己の人生を「忠実に」生きることが目標とされている。しかし、ありのままの自分にこだわりすぎて、特定の場面で生じる感情を自分の特徴だと思い込むと、自分の可能性を限定してしまうおそれがある。
中国の思想家たちは、どの人も絶えず変化する存在だと説く。例えば、自分のことを怒りっぽいと思っている人間を見たら、それは行動がパターン化したにすぎず、本来なら温和になる可能性を大いに秘めている、と考えるのだ。
人の感情は、内ではなく外に目を向けることで引き出され、日常生活での他者との交流の中で形成される。もちろん自分の意識を改革するには努力を要するが、自分の置かれた人間関係や就いている仕事などの様々な要因を把握し、それらとの関わりを変えていくことが自己成長につながるのだ。また、本書の原題(The Path)にある「道」とは、調和のとれた「理想」ではなく、自分の選択や行動、関係性によって絶え間なく生み出していく行路なのである。
このように、孔子をはじめ、変遷期の古代中国を生き抜いた思想家たちは、社会を問い直すにあたり、抽象的で壮大なテーマではなく、現実的かつ具体的な問いを探究し続けてきた。彼らの思想は、貧富の差が拡大し、社会的流動性が低下しつつある現代社会に対しても、確かな処方箋となってくれる。
【必読ポイント!】 孔子の教え「毎日少しずつ自分を変える」
日常的な振る舞いが、私たちを根底から変える

AntonioGuillem/iStock/Thinkstock
儀礼といえば、作法に則って行うものという印象を抱く人は多い。しかし、孔子は礼の持つ力について新しい解釈をもたらした。
人間には、「他者に対し感情的に反応する」という性向がある。もし受け身の反応しかできないのなら、人は絶えず、断片的な出来事や感情の揺さぶりに翻弄されるだろう。しかし、感情の修養に努め、反応の仕方を磨くことで、よりふさわしい反応ができ、人間性を高められると孔子は考えた。よりふさわしい反応の仕方を身につけるには、食事のときの所作のような、「日常的な振る舞い」が重要だという。
人は無意識のうちに、話す相手によって態度や言葉選び、声のトーンを調整する。この行為やしきたりを、孔子は「礼」だととらえ、私たちが社会生活に適応するための哲学の出発点だとした。例えば、落ち込んだときに、誰かに「やぁ」と声をかけることで、負の感情を断ち切ることができるというように、些細な行動でも、私たちを根底から変えうる力を持ち、何らかの良い影響を及ぼすのだ。
私たちを代替現実へといざなう「礼」
ここでは礼の代表として「儀礼行為」を取り上げてみる。古代の人々は人間世界に渦巻く負のエネルギーに対抗するために、儀礼行為を発展させた。
中でも、危険な霊を慈悲深い祖霊に変えるための祖先祭祀が重視された。祖先祭祀では、死者の霊が存在するかどうかは問われない。あくまで、残された家族が祭祀に本格的に参加することが大事なのだ。立派に儀礼を行っている最中には、彼らは祖先のまっとうな子孫であるかのように振る舞う。そのため、死者が生きている間に家族と結んでいた未解決なままの緊張関係や、生き残った者同士の不和が解消され、理想的な関係へと移行できる。
もちろん、ひとたび儀礼空間を後にすると、家族は実社会の関係に戻り、日頃の不和が再燃するかもしれない。しかし、儀礼をくり返し、その最中に家族が普段担っている役割とは異なる役割を演じ、現実から「離脱」することで、日常生活でもじわじわと家族関係が修繕されていくのだ。
このようにして、礼は束の間の代替現実をつくり出し、わずかに改善した日常生活に私たちをいざなってくれる。こうした礼は、「お願い」や「ありがとう」のやりとりや、カップルが互いに「愛してる」と口にする習慣、そして夕食どきの作法など、私たちの生活の至るところに浸透している。
本当の自分を探してはいけない

evgenyatamanenko/iStock/Thinkstock
とはいえ、私たちは礼の価値を理解せず、機械的にこれまでの習慣をくり返しがちだ。しかし、この状態から抜け出そうという動きも生まれている。例えば、アメリカの一部の大学では、学生たちが物議を醸しそうなテーマを建設的に討論できるような雰囲気のつくり方や意見の述べ方を学ぶ取り組みが行われている。これまでと違う態度を身につけることで、私たちは変容を果たし、他人とのより良い関わり方を学べるようになる。
礼による変容を果たすには、「本当の自分」という考え方を手放さなければならない。「自分に正直であれ」というメッセージは、有害な感情の習癖を固定化することにつながってしまう。かわりに、自己を「様々な感情や性向、願望、特徴がいりまじり、いつも違う方向へと引っ張られる存在」ととらえれば、鍛錬によって、より良い人間へと成長する可能性が開かれるのだ。
「礼」をくり返すことで身につく「仁」
同時に、礼をくり返す中で、まわりの人を思いやる能力も磨かれていく。この能力こそが「仁」、つまり人間の善性なのだ。
孔子はあえて仁を定義しなかった。なぜなら、仁の実践を理解するには、次々に変化する状況の複雑さと格闘し、仁を感じなければならないからである。

この続きを見るには...
残り2186/4340文字
4,000冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2016.08.30
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











