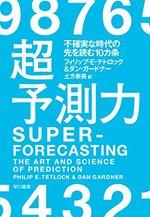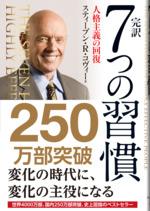採用を科学的に考える
採用に「普遍解」はない
2015年卒の新卒採用から求職者に受験料を徴収する方式を始めた、ニコニコ動画でおなじみのドワンゴ。通年採用で選考する学年を問わない「大学1年生採用」を導入したファーストリテイリング傘下のユニクロ。ユニークな新しい採用手法を導入する企業が出ると、その賛否を問う議論が巻き起こる。しかし、その多くは、バッシングや表面的な「称賛」に終始している。独自の事例を自社の課題と結びつけ、参考にする企業が少ないことに、著者は警鐘を鳴らしている。
求職者と企業両者の期待と、能力評価基準の曖昧化、そして採用活動の過熱化。こうした課題に対し、「面接ではこれを聞け!」といった安易なノウハウは役に立たないし、どの企業にも通用する普遍解はない。しかし、各企業にとって最適な解を導き出すための「ロジック(論理)」と「エビデンス(データ分析から導かれた証拠・根拠)」は、世界の研究者の知見から得ることができる。これらを体系化することが、経営学や著者の構想している「採用学」の使命である。そして、こうした知見を参考に、自社独自の「優秀な人材」を定義していくことで、無名の中小ベンチャーであっても、潤沢な資金を持つ有名な大企業を凌駕できる可能性は大いにある。
「良い採用」とは何か?

採用とは、企業の目標および経営戦略実現に向けて、組織や職場を活性化させるために、外部から新しい労働力を調達する活動である。では良い採用の基準とは何か。それは、求職者をランダムに採用したときに比べて、「①将来の時点でより高い仕事成果を収められる人材を獲得できたかどうか」、「②採用した人材が企業へとより強くコミットし、高い満足度を得て、中長期的に企業にとどまるかどうか」、そして「③採用活動を行わなかった場合と比べて、組織を構成するメンバーに多様性が生じ、結果として組織全体が活性化しているかどうか」の3つである。
フィーリングのマッチング優先にご注意!
募集、選抜、定着という流れで採用活動をとらえたとき、産業組織心理学者ジョン・ワナウスによると、個人と組織の間において、次の2つのマッチングが必要だという。1つ目は、個人が組織に求めるものと、仕事特性や雇用条件といった会社が提供するものとの、「期待のマッチング」である。期待のミスマッチが起こると、入社後の幻滅、離職可能性の増大をもたらしかねない。そして2つ目は、能力のマッチングであり、これが入社後の個人の業績と直結する。
ただし日本では、求職者と採用担当者が互いの主観的な相性を感じ取っていく、いわば「フィーリングのマッチング」が幅を利かせている。さらには、期待や能力のマッチングよりも優先しがちである。
フィーリングのマッチングは、採用担当者や面接官とのやりとりといった、限られた情報に基づくものだ。そのため、これに頼り過ぎることは、入社後に、職務満足やコミットメントの低下、ひいては離職へとつながるリスクをはらんでいるといえる。
【必読ポイント!】 なぜ、あの会社には良い人が集まるのか
入社後のリアリティ・ショック

それでは、募集・選抜のフェーズで、どのように人材を集め、自社の求める人材を引きとめればいいのだろうか。日本企業はこれまで、大規模な候補者群を形成することが大事だと考え、求職者にとって「魅力的」に見える情報を提示してきた。
しかし、これでは選抜のコストを押し上げるばかりか、入社する新人の期待を引き上げるために、期待のミスマッチを引き起こしてしまう。