中東・エネルギー・地政学
全体知への体験的接近
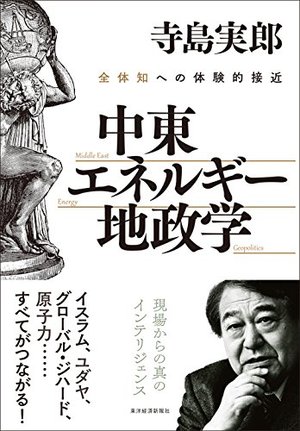
著者
寺島実郎(てらしま・じつろう)
(一財)日本総合研究所会長、多摩大学学長。日本を代表する論客の一人として、各メディアに頻繁に登場している。1970年代、三井物産の調査マンとしてイランのIJPCプロジェクトに関わり、以来、中東やアメリカで情報収集・分析活動を続けてきた。10年にわたるアメリカ勤務を経て日本に帰国後、企業内シンクタンクとして「三井物産戦略研究所」を立ち上げ、世界の最前線でビジネスを展開するための知の基盤の構築に力を注ぐ。「文献とフィールドワーク」をはじめとした、体験に根ざした独自の視線から国内外の経済、政治、エネルギー政策、宗教と、幅広い分野での提言を続けている。著書多数。
(一財)日本総合研究所会長、多摩大学学長。日本を代表する論客の一人として、各メディアに頻繁に登場している。1970年代、三井物産の調査マンとしてイランのIJPCプロジェクトに関わり、以来、中東やアメリカで情報収集・分析活動を続けてきた。10年にわたるアメリカ勤務を経て日本に帰国後、企業内シンクタンクとして「三井物産戦略研究所」を立ち上げ、世界の最前線でビジネスを展開するための知の基盤の構築に力を注ぐ。「文献とフィールドワーク」をはじめとした、体験に根ざした独自の視線から国内外の経済、政治、エネルギー政策、宗教と、幅広い分野での提言を続けている。著書多数。
本書の要点
- 要点1ユダヤ人は国家を喪失し、世界を流浪してきた民族である。そのためユダヤ人は国家という枠組みよりも国境を越えた価値を重視する視点をもっている。
- 要点2情報とは教養を高めるための手段ではなく、問題の解決に向けて多面的に収集するものである。また物事は単純ではなく、いろいろな要素の中で、多面的、重層的に考えなければ本質に迫ることはできない。
- 要点3エネルギーを他国に依存している日本にはバランスの取れた賢さが求められている。中東だけでなくロシアなど特定の国や地域に偏らない政策を考えなければならない。
要約
中東との出会い
戦後日本最大の海外プロジェクト

arhendrix/iStock/Thinkstock
1970年代初頭、パーレビ王朝の統治下にあったイランは、当時中東でもっとも安定し、発展の可能性のある国とされていた。そのような中、イラン・ジャパン石油化学(以下、IJPC)プロジェクトは開始された。ぺルシャ湾岸のイラク国境線に近い砂漠の中にある石油輸出の港町に、近隣の油田から発生する石油随伴ガスを原料とした、イラン初の大型石油化学コンプレックス(複合工場)の建設をめざしたイランと日本の共同事業である。ピーク時には3500人もの日本人スタッフが現地に赴き、投資総額6000億円の巨大国際プロジェクトであった。著者が勤務していた三井物産、および三井グループは中核推進役としてこのプロジェクトに社運を賭けて取り組んでいた。
しかし、IJPCプロジェクトは、何度も歴史の荒波に晒されることとなる。1973年には石油危機をきっかけとする世界的なインフレに見舞われ、計画の見直しを余儀なくされる。1979年にはイラン革命に伴う混乱により、建設工事が中止された。その後、成立した革命新政権の要望もあり、プロジェクトは継続されたが、民間企業が負うことができるリスクを超えているとの判断のもと、日本政府も出資するナショナルプロジェクトへと移行することになる。
そして建設工事再開に合意し、ようやく日本人スタッフが続々と現場に戻り始めた、その直後に、イラクによるイラン空爆が始まった。イラン革命の伝播を恐れたイラクの空爆は次第にエスカレートし、その後全面戦争に突入。IJPCプロジェクトの建設現場も空爆に晒された。
こうしてIJPCプロジェクトは完全に破綻した。その後の清算交渉には約10年もの歳月が費やされ、三井物産には約7600億円の損失が残された。
情報収集のためにイスラエルへ

kirill4mula/iStock/Thinkstock
IJPCプロジェクトがナショナルプロジェクトに移行した直後から、三井物産ではそれまでの国際情報活動の見直しと改善を進めていた。イラン革命を予想できなかった衝撃と反省から、特に中東に対する情報分析のどこに欠点があったのか洗い出しが行われたのだ。その一環で著者はイランについての情報収集を任され、アメリカのイラン専門家5人に会うことになった。
著者は5人の専門家を訪ねる過程で、三井物産の中東に関する国際情報活動がいかに偏ったものであったかを思い知らされた。5人専門家の内3人がイラン革命の可能性を事前に認識していて、その全員がユダヤ人であった。三井物産のこれまでの中東での情報収集活動は、いわゆる「アラブ筋」に限られていた。しかし「アラブ筋」からの情報は「アラブの利害というフィルターを通した情報」であり、生きた情報とは言えないものだった。
一方、1970年代の日本はアラブ寄りの通商政策をとり、イスラエルとは非常に冷たい関係になっていた。そのためイスラエル=ユダヤの情報はまったく閉ざされた状況にあった。帰国後、著者はイスラエルからの情報を入手すべき、という報告書を提出すると、その内容を上層部から認められ、イスラエル行きを命じられることになる。
ユダヤとは何か
テルアビブ大学シロア研究所
徒手空拳でイスラエルに乗り込んだ著者は、ユダヤ筋の情報ソースにたどり着くためにさまざまなルートを当たっていくうちに、テルアビブ大学の中東問題を専門とするシンクタンク、シロア研究所を紹介される。
この研究所との出会いが著者の情報活動に対する認識を一変させた。この研究所では重要人物ごとにタスクフォースが設置されていたが、政治、軍事、宗教の専門家に加えて言語学者、医師、精神分析医も議論に参加し学際的に運営されていた。また情報収集は徹底していて、対象となる重要人物が先週何を食べたか、という情報まで分析の俎上に載せ、多面的、多角的に分析していた。
イスラエルは周囲を敵対国に囲まれ、常に存亡の危機の緊張感と向き合っている国家である。情報は生きるために不可欠であり、情報の分析は生き抜くための必須条件なのである。そして物事は単純ではなく、いろいろな要素の中で、多面的、重層的に考えなければ本質に迫ることはできない。
この研究所での体験で著者は、情報とは教養を高めるための手段ではなく、問題の解決向けて多面的に収集するものであることを強く認識した。
ユダヤ国際主義
ユダヤ人は国家を喪失し、世界を流浪してきた民族だ。そのためユダヤ人は国家という枠組みよりも国境を越えた価値を重視する視点をもっている。この視点は現在の国際主義やグローバリズムが起源とする概念と言える。

この続きを見るには...
残り2399/4267文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2017.02.14
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











