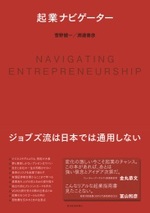獺祭
この国を動かした酒

著者
勝谷 誠彦(かつや まさひこ)
1960年、兵庫県尼崎市生まれ。文藝春秋社勤務を経てコラムニスト、写真家。フィリピン動乱、湾岸戦争、北朝鮮などを取材。フリーに転じてからは食や旅のエッセイ、イラク戦争の取材、社会時評、小説などで健筆を振るう。月刊『Hanada』の連載コラムをはじめ、雑誌に多数連載を持ち、『イラク生残記』『バカが隣に住んでいる』『この国を滅ぼすバカとアカ』、小説『平壌で朝食を。』『ディアスポラ』など著者も多数。
サンテレビ「カツヤマサヒコSHOW」でMC、CS(DHCシアター)「ニュース女子」にコメンテータとして出演中。ギネスの噂もある365日休み無し朝10時までに、ウクライナのドネツクにいても配信する『勝谷誠彦の××な日々』に信者多し。詳細はhttp://katsuyamasahiko.jp/を!
1960年、兵庫県尼崎市生まれ。文藝春秋社勤務を経てコラムニスト、写真家。フィリピン動乱、湾岸戦争、北朝鮮などを取材。フリーに転じてからは食や旅のエッセイ、イラク戦争の取材、社会時評、小説などで健筆を振るう。月刊『Hanada』の連載コラムをはじめ、雑誌に多数連載を持ち、『イラク生残記』『バカが隣に住んでいる』『この国を滅ぼすバカとアカ』、小説『平壌で朝食を。』『ディアスポラ』など著者も多数。
サンテレビ「カツヤマサヒコSHOW」でMC、CS(DHCシアター)「ニュース女子」にコメンテータとして出演中。ギネスの噂もある365日休み無し朝10時までに、ウクライナのドネツクにいても配信する『勝谷誠彦の××な日々』に信者多し。詳細はhttp://katsuyamasahiko.jp/を!
本書の要点
- 要点1大吟醸造りをわかっていなかった杜氏を雇ったからこそ、旭酒造の「蔵元が味を決める」という体制はできあがった。
- 要点2業界向けの雑誌にかかれていたレポート通りに吟醸酒を造ったところ、旨い酒ができあがった。この経験から、桜井は理論がきわめて重要だと実感した。
- 要点3さらなる挑戦を求め、地ビール造りにも挑んだが大失敗。莫大な借金をかかえた。
- 要点4大口の問屋との付き合いをやめたことが、結果的には蔵の再生につながった。
- 要点5「獺祭」の生みの親のひとりである杜氏が辞めたことで、桜井は蔵元と杜氏を兼任するプレイングマネージャーになる決意をかためた。
要約
「獺祭」が生まれる前
後悔しないために蔵元になった

tomorca/iStock/Thinkstock
日本酒の出荷量は2010年に底を打ち、その後上向きはじめている。海外では、日本酒は「サケ」と呼ばれ、最もクールな飲み物のひとつとなった。現在、その先頭を走っているのが「獺祭」だ。
獺祭をうみだしたのは、山口県の旭酒造である。ただ、旭酒造がもともと売りだしていたのは「獺祭」ではなく、「旭富士」という酒だった。そのほとんどが地元で消費されたが、当初は地元の小さな競争のなかでも、十分にやっていけていた。
ところが1973年のオイルショックを境にして、世の中の流れが大きく変わった。大手の酒が地方に流れてくるようになり、縮小した市場を小さな酒造が奪いあうようになった。
その頃、やがて「獺祭」の生みの親となる桜井博志は、親元から離れて大手酒造の営業を行なっていた。1976年にいったん旭酒造に戻るものの、当主の父とは対立するばかり。結局、桜井は旭酒造を離れ、しばらく石材業を営んだ。
そんな桜井だったが、父親の死をきっかけにして、ふたたび旭酒造に戻ることになった。「ここで継がずに出て行ったら一生後悔する」と語った桜井氏。しかし彼はその後、多くの困難に直面することになる。
ただ真面目にやるのは逃げである
桜井が後を継いだ当時、旭酒造の状況はひどいものであった。1973年には2000石(一升瓶で20万本)を醸していたのが、その10年後には700石まで落ちこんでいた。
突然後を継ぐことになった桜井は、こうした状況を不思議に思った。あきらかに売上が落ちこんでいるにもかかわらず、社内には緊張感がなかったからだ。たしかに従業員は真面目に働いてはいたが、むしろ精一杯やっているということが逃げ道となっており、本当の売れない理由から逃げているのではないかと思わされた。
桜井はテコ入れとして、箱酒、すなわち一升の紙パック詰めをはじめた。今となってはコンビニエンスストアなどで当たり前に見られる形式だが、当時は郊外のバイパス沿いにできた大量酒販店などで売られ、劇的に安く、人々の注目を集めていた。
するとこれが驚くほど売れた。蔵には活気が戻り、桜井も調子にのった。今度は紙カップ(一合)の酒をつくると、これもよく売れ、一時は箱酒と紙カップが全出荷量の2割を占めるほどとなった。
だが、栄光は長く続かなかった。大手の物量戦術にはかなわなかったのである。また、会社に来て、仕事がないと文句を言い、ぶらぶらしていた社員たちは、いざ忙しくなると辞めてしまっていた。
蔵元が味を決める

GI15702993/Thinkstock
酒造りにおいて、蔵元はいわばプロデューサーであり、杜氏はディレクターである。
当時、旭酒造における杜氏の高齢化は深刻な状況にあった。

この続きを見るには...
残り3275/4384文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2017.04.25
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約