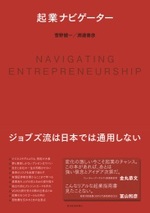「想い」と「アイデア」で世界を変える

「想い」と「アイデア」で世界を変える
著者
著者
中台 澄之(なかだい すみゆき)
ビジネス・アーティスト。株式会社ナカダイ常務取締役。モノ:ファクトリー代表。
1972年生まれ。東京理科大学理学部数学科卒業後、証券会社勤務を経て、1999年ナカダイ入社。ISO14001の認証取得や中古品オークションを行うリユース市場の立ち上げなど総合リサイクル業として事業を拡大。また、“使い方を創造し、捨て方をデザインする”リマーケティングビジネスを考案し、“発想はモノから生まれる”をコンセプトに、モノ:ファクトリーを創設。自治体や大学での講演や企業研修、廃棄物に関する総合的なコンサルティング業務や、廃棄物を使ったイベントの企画・運営を手がける。
リマーケティングビジネスは2013年度グッドデザイン賞Best100、特別賞の未来づくりデザイン賞を受賞。
また、平成26年度群馬県優良企業表彰にて商業・サービス部門 大賞受賞。
ビジネス・アーティスト。株式会社ナカダイ常務取締役。モノ:ファクトリー代表。
1972年生まれ。東京理科大学理学部数学科卒業後、証券会社勤務を経て、1999年ナカダイ入社。ISO14001の認証取得や中古品オークションを行うリユース市場の立ち上げなど総合リサイクル業として事業を拡大。また、“使い方を創造し、捨て方をデザインする”リマーケティングビジネスを考案し、“発想はモノから生まれる”をコンセプトに、モノ:ファクトリーを創設。自治体や大学での講演や企業研修、廃棄物に関する総合的なコンサルティング業務や、廃棄物を使ったイベントの企画・運営を手がける。
リマーケティングビジネスは2013年度グッドデザイン賞Best100、特別賞の未来づくりデザイン賞を受賞。
また、平成26年度群馬県優良企業表彰にて商業・サービス部門 大賞受賞。
本書の要点
- 要点1株式会社ナカダイは鉄スクラップの解体事業で会社を成長させてきたが、1990年代後半に総合リサイクル事業に進出した。様々な産業廃棄物処理の許可を取得していたため、順調に顧客を増やすことができた。
- 要点2著者は、廃棄物処理に関するビジネスモデルに潜む矛盾を感じ、「量から質へのシフト」を追い求めた結果、廃棄物から「素材」を生み出すことを思いついた。
- 要点3ナカダイは「モノ:ファクトリー」を設立し、リマーケティングビジネスの拠点とした。
要約
リサイクルとの出会い
学業の挫折を経て金融の世界へ
株式会社ナカダイの前身は、著者の祖父が東京・品川に設立した中台商店という鋼鉄商である。スクラップの解体事業で会社は高度成長期に急成長し、群馬県前橋市にスクラップ解体処理工場を建設した。著者の一家は群馬に移った。
著者は数学が得意な少年だった。家業を継ぐことは頭になく、大学は数学科を選んで教師になることを考えていた。だが、大学で学ぶ数学はこれまで慣れ親しんでいた、筋道を立てて解き進めていくものではない。世の中にないことを式に表す純粋数学の世界についていけず、数学に対する興味もすっかり失ってしまった。こうして学業は挫折したものの、サークル活動に励んだこともあって大学生活は充実していた。そんな著者が卒業後に選んだのは金融業界であった。
証券マンからの転身

OcusFocus/iStock/Thinkstock
著者はコミュニケーション力に自信があり、個人の力がストレートに評価される証券会社が向いていると考えた。国際証券(現在は三菱UFJモルガン・スタンレー証券)に入社し、京都支店の営業職に配属となった。著者は客の機嫌取りなどをせず、資料をしっかり用意して提案するといった「正攻法」の営業スタイルを貫いた。すると2年目には法人営業チームに抜擢され、売上ランキングでトップに躍り出た。
3年目に転機が訪れた。関東のある支店に異動が命じられ、法人営業を支援する役割を課せられた。しかし、異動先はこれまでの正攻法が通じる場所ではなかった。悪く言えば、客をだまして収益をつくる手法が横行していた。著者は支店長とぶつかり、新規の顧客を開拓してきても担当を外されるといったひどい仕打ちを受けた。ストレスは極限に達し、とうとう出社できなくなった。さらには劇症肝炎と診断され、自宅療養を余儀なくされた。
復帰後はナカダイの社長である父親に会いに行く機会が増えた。その中で、父親からナカダイが「スクラップ屋」から「総合リサイクル業」に大きく転換しようとしていると聞いた。しかも、総合リサイクル業に必要な国際規格であるISO14001を取得するための事業部のリーダーをやってみないかと誘ってきたのである。決断まで時間はかからなかった。著者は証券会社を退職し、1999年の春にナカダイに入社した。
総合リサイクル事業への挑戦
インパクトを与えた営業手法

karandaev/iStock/Thinkstock
社長の息子とはいえ、著者は入社時にはただの新入社員の扱いであった。まずは鉄スクラップ事業を熟知し、現場で戦力として認められるために、誰よりも早く出社し、鉄スクラップの山で汗を流すことから始まった。夜間には会社の全体像を知るために、経理資料のチェックに明け暮れ、総合リサイクル業のスキームづくりとISO14001の取得の準備に向けて独学を続けた。どの廃棄物をどのようにリサイクルしていくのかという計画を、役所に提出しなくてはならないということもわかってきた。
著者が最初に目をつけたのは、プラスチックだ。一般利用されているプラスチックだけでも10種類以上あり、例えばペットボトルの場合、本体はペット樹脂でキャップはポリプロピレン(PP)である。きちんと分別して回収すればリサイクル効率が格段に上がる。
つまり、ナカダイがプラスチックのリサイクルを事業の一部とするには、顧客が出したプラスチックの種類をその場で判断する力が必要というわけだ。しかし、社内に分別のノウハウはなく、専門書を暗記するのも非現実的だった。
そこで著者は、火を点けて判断する方法を見つけた。プラスチックは種類によって燃え方と臭いが微妙に異なるからだ。試行錯誤の末、著者は1年ほどで区別がつくようになった。営業先の廃棄物置き場で火を点けてプラスチックを判別していくと、相手は驚きの表情を見せ、すぐに具体的な契約の話が進んだ。このように、顧客にインパクトを与える手法で、取り扱う廃棄物の種類をどんどん増やしていった。
社長の慧眼と事業拡大
ナカダイは、鉄スクラップとは直接関係のない木くずや廃プラスチックなどの産業廃棄物処理の許可を取り始めていた。これは、今後規制が厳しくなることを見越しての社長の慧眼であった。
産業廃棄物には18ほどの種類がある。限定した許可だけで仕事をしていると、例えば木くずの処理しかできない業者が木と金属の複合材の回収を求められたときに、金属を外す余計な作業を顧客にお願いしなくてはならない。しかし、様々な種類の許可を取得していれば、その必要はないため、顧客は少ない負担で依頼ができる。
産業廃棄物処理の許可を取るには、いくつものハードルがあるため、最短でも1年を要する。よって、他社が追い上げを見せてきても、ナカダイの優位性はそう簡単に崩れるものではなかった。こうした強力な武器をもとに、ナカダイの総合リサイクル業は拡大の一途をたどっていった。
リユースの立ち上げ
ところがナカダイは、発泡スチロールの処理という課題を抱えていた。

この続きを見るには...
残り2330/4340文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2017.04.26
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約