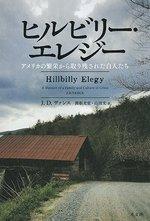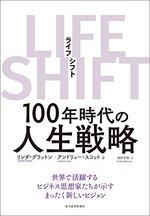対立するイギリス
イギリスとEUの厄介な関係
2016年の国民投票により、イギリスのEU離脱が決まった。しかしイギリスはそもそも、EU加盟国のなかでは最もEUと疎遠な関係にあった。共通通貨ユーロも採用していないし、国境を超えた人の行き来を可能にするシェンゲン協定からも除外されている。また、イギリスはもともと他の加盟国と比べ、「ヨーロッパ」というアイデンティティが弱く、EUへの信頼性も低かったという。
このように、EUとイギリスの関係性は多元的かつ複雑であり、それゆえ保守党・労働党両方の内部で、EUの扱いについての意見は対立していた。両党のリーダーたちはEU問題となると、党内をまとめるのに苦戦した。そしてそのような混乱のなか、EUとの関係に特化した新しい政党が拡大する余地も生まれた。
UKIPの伸長

反EUを鮮明に打ちだし、単一争点政党として勢力を拡大してきたのがUKIP(英国独立党)である。UKIPは、イギリスでヨーロッパ懐疑主義が広がりだしていた1993年、ロンドンの大学の研究者であったアラン・スケッドを中心として結成された。当初は、総選挙における得票率が1%にも満たない泡沫政党であったが、2000年以降に勢力を伸ばし、2015年には保守党・労働党に次ぐ12.6%の票を得た。特にヨーロッパ議会選挙でその勢いはすさまじく、2014年のヨーロッパ議会選挙では二大政党を抑え、イギリスの第一党となっている。
UKIPが勢力を伸ばした理由は2つ考えられる。ひとつは、ヨーロッパ議会選挙という場があったことだ。比例代表制が採用されたことで、二大政党には反映されない民意の行き場として、UKIPが注目を浴びるようになった。
もうひとつの理由は、反EUを軸とし、現状に不満を持つさまざまな民意の受け皿になったことが挙げられる。2010年以降、保守党は自由民主党と連立を組んだことで、中道化・リベラル化した。その結果、「右」や「保守」の位置が空白になり、UKIPがそこに入り込んだ。特に象徴的なのが移民の扱いだ。UKIPは移民問題について強硬な態度をアピールし、2013年にはUKIPの支持理由の第1位が「移民問題」となった。
「大統領型」リーダーシップと党内対立

イギリス国内の対立が拡大した背景には、政治の「大統領制化」も大きく影響している。
政治の「大統領制化」とは、議院内閣制の国において、首相に権限を集中させる事例を指す。イギリスではサッチャー政権期からこのような傾向が見られたが、最も制度的かつ戦略的にそのスタイルを確立したのは、1997年から首相となった労働党のトニー・ブレアであろう。「大統領制化」は、特に外交において効果を発揮する。首相官邸が主導することで、交渉が円滑に進むようになるからだ。
その一方で、「大統領制化」には負の側面もある。その最も大きなきっかけとなったのが2003年のイラク戦争だ。首相官邸は強い批判の対象となり、ブレアの人気は失墜。それに伴い、与党労働党の支持率も低下し、公然とブレアの方針に反対する労働党議員も増加した。
ブレアによる「大統領型」リーダーシップとそれがもたらした対立、さらにはその後に拡がった議員全体への不信感は、小選挙区制をもってしても、単独政権を不可能にさせるほどの多党化をもたらした。その結果、保守党と自由民主党との間で、戦後初の連立政権が形成されるに至ったのである。
緊縮財政と社会の分断
2010年から始まった、保守党による政府支出削減の規模は、それまでで最も大きかった。