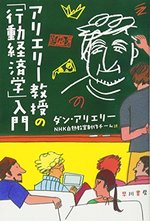バッド・フェミニスト
著者
ロクサーヌ・ゲイ
1974年ネブラスカ州生まれ。2011年に短編小説集『アイチ』を上梓。2014年、初のエッセイ集『バッド・フェミニスト』(本書)と長編小説『アンテイムド・ステイト』で人気作家に。「ニューヨーク・タイムズ」に寄稿。マーベル社のコミック『ブラックパンサー:ワールド・オブ・ワカンダ』の原作者でもある。2017年には体重と自己イメージの問題をテーマにつづったエッセイ集『ハンガー』、短編小説集『ディフィカルト・ウィメン』を刊行。
1974年ネブラスカ州生まれ。2011年に短編小説集『アイチ』を上梓。2014年、初のエッセイ集『バッド・フェミニスト』(本書)と長編小説『アンテイムド・ステイト』で人気作家に。「ニューヨーク・タイムズ」に寄稿。マーベル社のコミック『ブラックパンサー:ワールド・オブ・ワカンダ』の原作者でもある。2017年には体重と自己イメージの問題をテーマにつづったエッセイ集『ハンガー』、短編小説集『ディフィカルト・ウィメン』を刊行。
本書の要点
- 要点1フィクションの世界に登場する女性たちについては、男性たちと違って、好感度がクローズアップされてしまう。
- 要点2巷にあふれるポップ・ソングにも、女性蔑視や、性暴力が隠れていることがある。
- 要点3フェミニズムという運動にはあまりに多くのことが背負わされ、フェミニストを名乗る人にも多くのことを期待されてしまう。著者は、フェミニストの主流から外れた関心や意見も持っているし、フェミニストの看板は背負えないが、それでもなおフェミニストでいたいと思う。だからこそ「バッド・フェミニスト」を名乗る。
要約
ジェンダーとセクシュアリティ
ミス・アメリカ

eskaylim/iStock/Thinkstock
ヴァネッサ・ウィリアムスは、1984年に黒人女性として初めてミス・アメリカになった人物だ。彼女は、著者をはじめとする黒人少女たちに、自分たちだって美しくなれると夢を与えた。
一方で、典型的なアメリカン・ガールのイメージは、明るい南カリフォルニアのブロンドの少女だった。それが描かれていたのが、著者が小さいときに読んだ、『スイート・ヴァレー・ハイ』シリーズだった。主人公は、対照的な性格をした双子で、ブロンドでやせていて、みんなの人気者だ。
著者の実際の学校生活は、物語の逆だった。著者は教室で唯一の黒人で、見た目はさえなかった。ハイチ訛りの英語もクラスメイトのからかいの種になっていて、校内の階層の最下層近くにいた。クラスの人気者たちのグループと仲良くなりたくて、自分もクールだということを示すため、ある日いじめられた著者はこう叫んだ。「いまに見てろよ。私はミス・アメリカになるんだから」。ミス・アメリカというのは、母親が著者を呼ぶあだ名だった。母親にとって、著者は大事な長女、アメリカで生まれた最初の子どもなのだった。人気者の子たちは笑いころげ、長いあいだ「ミス・アメリカ」とからかい続けた。
しかし、それでも著者はヴァネッサ・ウィリアムスがミスになれるなら自分もなれると信じていたし、『スイート・ヴァレー・ハイ』シリーズにも熱中し、双子の、反抗的で賢くセクシーな方に自分を重ねていた。スイート・ヴァレーの物語が、ブロンドのやせた白人を美しいとしていて、異人種がほとんど登場しないことを不自然には感じていた。けれど、著者は物語に熱中して新刊を待ち望み、大人になって、続編が刊行されると知ったときはカレンダーに印をつけて発売日を待った。
ハイチ系で黒人の女の子である著者は、物語の中に自分自身を見出すことを期待されていなかった。けれど、著者はそうしていたし、物語から慰めや静かな喜びを得ていた。
好感問題

Avosb/iStock/Thinkstock
著者は幼い頃から知っていた。女の子が好感を持たれない場合、その子が問題児といわれることを。正直である、人間でいる、ということは、めったに女性の好ましい性質とはされない。
『ヤング≒アダルト』という映画で、シャーリーズ・セロンが演じたメイヴィスという女性は、キャラクターとしての「好感の持てなさ」を、映画評で称賛された。計算高く、自己陶酔的で、無神経、という彼女の性質は、つまり人間的な性質にほかならないが、それはそのまま観客に受け入れられるのではなく、あえてクローズアップされて説明されるべきことだったということだ。
しばしば、似たような反応は文芸批評の中にもある。フィクションの女性は、現実の人生を生きる女性と同様に、ある規範を守るよう求められている。そして彼女らの好感度の低さは、小説のクオリティに関わるかのように、論点になってしまう。一方で、アンチヒーローとして活躍する感じの悪い男や、規範から逸脱した男は、『ライ麦畑でつかまえて』のホールデンにはじまり、作品の中に多々登場する。
好感度についての問いかけがあることは、私たちはフィクションに、人々が理想的にふるまう理想の世界を求めているのではないか、と考えさせられる。

この続きを見るには...
残り2510/3838文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2017.09.23
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約