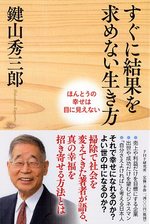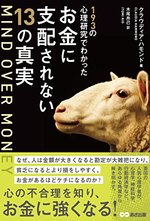行動経済学の逆襲
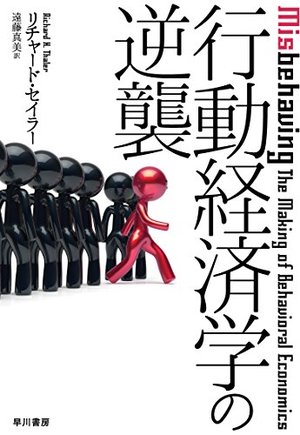
行動経済学の逆襲
著者
リチャード・セイラー (Richard H. Thaler)
シカゴ大学ブース・スクール・オブ・ビジネス教授。全米経済研究所(NBER)の研究員。行動科学と経済学を専門とし、行動経済学のパイオニアの一人に数えられる。正しい行動を促す概念として提唱した“ナッジ”は一世を風靡し、各国政府の政策に取り入れられている。2015年にはアメリカ経済学会会長に選出。著書に『実践 行動経済学』『セイラー教授の行動経済学入門』『市場と感情の経済学』があり、いずれもベストセラーとなっている。2017年にノーベル経済学賞を受賞。
シカゴ大学ブース・スクール・オブ・ビジネス教授。全米経済研究所(NBER)の研究員。行動科学と経済学を専門とし、行動経済学のパイオニアの一人に数えられる。正しい行動を促す概念として提唱した“ナッジ”は一世を風靡し、各国政府の政策に取り入れられている。2015年にはアメリカ経済学会会長に選出。著書に『実践 行動経済学』『セイラー教授の行動経済学入門』『市場と感情の経済学』があり、いずれもベストセラーとなっている。2017年にノーベル経済学賞を受賞。
本書の要点
- 要点1著者はつねに合理的な意思決定をする架空の人間を「エコン」と呼んでいる。従来の経済モデルはエコンを想定してつくられていた。だが実際の人間はエコンのようには動かない。
- 要点2行動経済学とは、エコンの意思決定には無関係だと思われてきた要因を、従来の経済学に組み込んだアプローチのことである。
- 要点3人は「状態」ではなく「変化」に反応する。いくら高年収でもやがてはそれに反応しなくなる一方で、少額でも臨時収入に大喜びするのはそういうわけだ。
- 要点4お得感やぼったくり感といった「取引効用」は、ヒューマン特有のものである。
- 要点5ナッジ(誘導)とは、私達の注意を引きつけて行動に影響を与える、ちょっとした工夫を指す。
要約
はじまりの第一歩
「エコン」と「ヒューマン」

thomasandreas/iStock/Thinkstock
従来の経済学で想定されていた人間を、著者は「エコン」と呼んでいる。これは「ホモエコノミカス」の略で、経済学者が経済モデルを考えるときに設定する人間のことである。エコンは限られた予算の中ですべての選択肢を検討し、最良の選択をするとされている。
しかしエコンを前提にした経済モデルには無理がある。なぜなら実際の「ヒューマン」(人間)の思考にはバイアスがかかっているからだ。従来の経済モデルは、そもそも前提部分に欠陥があるのである。
とはいえ著者は、エコンとヒューマンは違うと主張しつつも、エコンの経済モデルそのものを否定しているわけではない。あくまでエコンの意思決定において無関係とされている要因を、経済モデルに組み込むアプローチの重要性について指摘しているのだ。そうすれば、経済理論に基づいた予測の精度はさらに高まるだろう。
正統的な経済理論への疑問
著者が正統的な経済理論に疑問をもったのは、ロチェスター大学大学院で「命の価値」というテーマの博士論文に取り組んだときだった。次の2つの質問を学生にしたとき、論理的に説明がつかない不可解なことが起こったのだ。
質問A:あなたは致死率の高い病気に感染している可能性がある。罹患率は1000分の1。感染すると来週には突然苦しむことなく死ぬ。死亡リスクをゼロにする治療薬は1人分のみ。もっとも高い金額で買い取る人だけが飲める。いくらまでなら払うだろうか(お金がなければ返済期間30年・金利なしで貸与可能という条件)。
質問B:この病気について調査している大学病院がボランティアを募集している。内容は、ある部屋に歩いて入って5分間じっとしているだけ。部屋の中で病気にかかる確率は同じく1000分の1。治療薬はない。いくらもらえば参加するだろうか。
学生の典型的な答えは、「質問Aでは2000ドル以上払いたくないが、質問Bでは最低50万ドルはほしい」というものだった。エコンの世界だと、質問の答えは同じになるにもかかわらず、である。
機会費用と保有効果
経済学には「機会費用」という概念がある。ある選択をすることで、失われる利益のことをいう。
クレジットカードで買い物をするときを考えてみよう。後から利用手数料を上乗せされるのと、すでに上乗せした金額から割り引きをするのとでは、客の反応は異なる。割増分を支払うと実際にお金を失ったことになるが、割り引きを受けられないことはただの機会費用にすぎないと考えられるからだ。
著者はこの現象を「保有効果」と呼んでいる。人はまだ手に入れていないものより、すでに自分が保有しているものに、より高い価値を感じるのである。
人間のおかしな行動リストとバイアス

SIphotography/iStock/Thinkstock
著者は経済学の合理的選択モデルに合致しない不可解な事例を集め、「人間のおかしな行動リスト」としてリストアップした。それらをどう解決すればいいか考えあぐねていたところ、ダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーの論文「不確実性下における判断──ヒューリスティクスとバイアス」を読み、一筋の光明を見出した。
この論文によると、意思決定を下すときの時間や知力には限界があるため、何かを判断するときにはどうしてもヒューリスティクス、つまり経験則に頼ってしまう。このときに「予測可能なエラー」が生じやすい。
たとえば「アメリカの銃による死亡者数は、殺人と自殺のどちらが多いか」と尋ねてみると、ほとんどの人は殺人による死亡者のほうが多いと答える。

この続きを見るには...
残り3273/4714文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2017.12.19
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約