新編 教えるということ
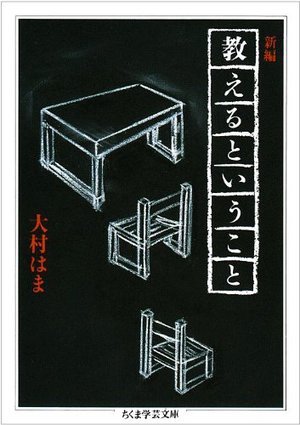
新編 教えるということ
著者
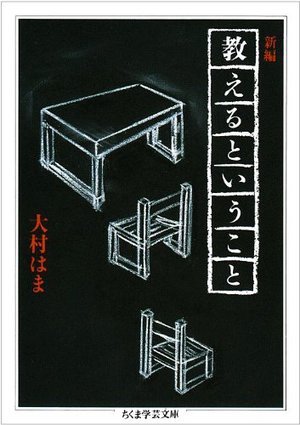
著者
大村 はま(おおむら はま)
1906年、横浜生まれ。1928年、東京女子大学卒業後、国語科教師として長野県の諏訪高等女学校に赴任。1947年、新制中学の教師に転出し、以来、単元学習など数多くのユニークで実践的な指導を重ねる。優劣の意識を超えたところで生徒を授業に熱中させる、新鮮で画期的な「大村国語教室」は子供たちを育てるばかりではなく、教師・研究者・親にも貴重な刺激を与えてきた。著書に『大村はま国語教室』(全15巻・別巻1)をはじめ、『日本の教師に伝えたいこと』など多数。2005年没。
1906年、横浜生まれ。1928年、東京女子大学卒業後、国語科教師として長野県の諏訪高等女学校に赴任。1947年、新制中学の教師に転出し、以来、単元学習など数多くのユニークで実践的な指導を重ねる。優劣の意識を超えたところで生徒を授業に熱中させる、新鮮で画期的な「大村国語教室」は子供たちを育てるばかりではなく、教師・研究者・親にも貴重な刺激を与えてきた。著書に『大村はま国語教室』(全15巻・別巻1)をはじめ、『日本の教師に伝えたいこと』など多数。2005年没。
本書の要点
- 要点1教師たるもの、子どもたちに「読んできましたか」と確認する「検査官」や、黙って書かせる「批評家」になってはいけない。
- 要点2教師の役割は、温かくもきびしい目をもち、子どもを一人でも生き抜ける人間に鍛え上げることである。そのためには真摯な研究とすぐれた指導が必要だ。
- 要点3学力不足や活字離れが起きるのは、教室に魅力がないからである。たしかな成長感を得られる場であれば、生徒は教室に魅力を覚える。
- 要点4多様な学習を行なう「単元学習」なら、優劣にとらわれることなく、子どもたちに学習の楽しさを実感させることができる。
要約
教えるということ
長い教師生活のなかで

vtmila/iStock/Thinkstock
著者の大村はま氏が教師になったのは、昭和3年(1928年)のことだ。当時は不況による就職難で、世の中に人が溢れていた。とにかく就職できたら上々という状況だ。東京女子大を卒業した大村氏も、東京はもちろんのこと、関東近郊にも勤め口を見つけられなかった。しかしちょうどいいタイミングで、長野県の学校に勤めていた友人が東京に出ることになり、その代わりとして教職に就けることになった。
大村氏は長野で10年間、国語を教える唯一の女教師として過ごした。女性は半人前と思われていた時代である。だがそのおかげで雑務に追われることなく、教育にとことん打ち込めた。
長い教師生活だったが、大村氏は「研究」から一度も離れなかった。「研究を失った教師は、子どもと全然違った世界にいる」という考えがあったからだ。毎月1回、研究授業を行ない、誰も使ったことがない教材を用意し、新たな教育法を開拓していった。
教えない教師が多すぎる
ここからは大村氏が、研修会で若い教師に語った内容を取り上げていく。
大村氏がある研修会の題を「教えるということ」にしたのは、「教える」ことをしない教師があまりにも多くて困ったからだ。「教えない」教師というのは、「検査官」や「批評家」のようにふるまう人たちのことである。
「検査官」のような教師は、教室に子どもを入れると開口一番、「読んできましたか」と尋ねる。これではまったく教えることにならない。子どもが学習をするのはあくまでも「学校」である。そもそも「家庭」は生活の場であり、本来勉強するところではない。学校で「読んできましたか」と問うことは、「読む」という一番大事なことを家庭へ預けることに他ならない。
また「批評家」も「教えていない」教師の代表例だ。こういう教師は作文を家で書かせたがる。学校で書かせる場合でも、生徒が書いている間はじっと教壇のところで見ているだけで、書かせたものを集めては「これは下手だ、これは上手だ」と批評する。こんな教師は指導者ではない。
見ているだけの教師は、「自分だけ書けない」と苦しんでいる子どもを助けられない。書き出しに困っている子どもがいたら、冒頭を書いて、「続けてごらん」と勢いをつけてあげることだ。そうすれば子どもたちが劣等感を抱くこともなくなるし、どんどん先を書いていけるようになる。つっかえている子どもには質問してあげて、見たものを思い出させてあげるのもいいだろう。これこそが「書くことを教える」ということなのだ。
子どもに敬意をもつ

Jupiterimages/Stockbyte/Thinkstock
一般的には、劣った子どもに親切なのがよい教師ということになっている。たしかにそれも大切なことだ。しかし教師たるもの、落後者を生まないことだけに腐心してはならない。
教育現場では「中ぐらいの生徒を目当てに授業を進めればよい」と言われることがあるが、これは空論である。子どもと接する際は、常に一人ひとりを見るべきであって、束にして見るべきものではない。ときにグループ学習をさせることもあるが、すべては個人を生かすためである。根本は個人を伸ばすことにあると心得るべきだ。
大切なのは、教師が子どもを尊敬することである。

この続きを見るには...
残り2605/3910文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.02.04
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











