トップも知らない星野リゾート
「フラットな組織文化」で社員が勝手に動き出す
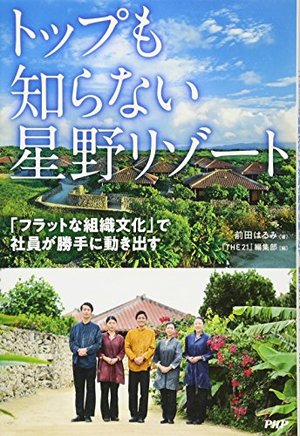
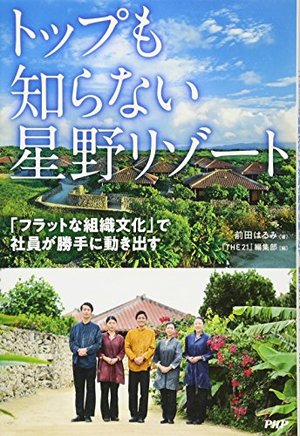
著者
前田 はるみ (まえだ はるみ)
ライター。ビジネス誌を中心に取材・執筆を行なっており、丹念な取材力には定評がある。過去数十回にわたり、星野リゾートを取材しており、星野リゾートの組織文化をよく知る人物。
ライター。ビジネス誌を中心に取材・執筆を行なっており、丹念な取材力には定評がある。過去数十回にわたり、星野リゾートを取材しており、星野リゾートの組織文化をよく知る人物。
本書の要点
- 要点1星野代表は、各ホテルが提供するアクティビティに関して意見は言うが、最終決定は現地スタッフに委ねている。
- 要点2世代や性別、部門、ポジションの垣根を越えたメンバーがフラットに議論することで、新たなアイデアが生まれる。
- 要点3星野リゾートでは、入社2年目以降の社員であれば誰でもリーダーや支配人に立候補できる。立候補者は、組織運営の目標や戦略を全社員に向けて発表する「立候補プレゼン」を行い、社員の評価をもとに判断される。
要約
【必読ポイント!】 勝手に決める社員たち
好きなことにかける情熱が強みになる

tomorca/iStock/Thinkstock
星野リゾートでは、それぞれの地域の魅力を発掘し、発信し、演出する運営手法を実践している。一例として、青森県にある「星野リゾート 奥入瀬渓流ホテル」を紹介しよう。
同ホテルは、青森県屈指の景勝地であり、国立公園に属する渓流の目の前に位置している。渓流に生える「苔」をテーマにしたプログラムやサービスを充実させていることが特徴だ。
実は、数年前までは、誰も苔に注目していなかった。観光客の目当ては、渓流散策だった。そればかりか、星野リゾート代表の星野佳路氏ですら「苔の魅力はわからない」と言っていたほどだ。しかし今や、苔は奥入瀬渓流ホテルを象徴する存在になっている。
その立役者が、自ら「苔メン」を名乗るほどの苔好きで、同ホテルで「苔」をテーマにしたプログラムをスタートさせた丹羽氏である。最初の2年ほどは、宿泊者を「苔さんぽ」(渓流を散策しながら苔を観察するプログラム)に誘っても、期待したような反応は返ってこなかった。それでも彼は、苔に熱中し、苔の魅力を伝え続けた。やがて彼の情熱は、同僚やメディアにも伝播していくこととなる。「苔さんぽ」への参加者が増え始めたことをきっかけに、オリジナル苔玉を作るアクティビティを用意したり、オリジナルスイーツ「苔玉アイス」を提供したりと、「苔」をホテル全体で取り組むプロジェクトへと発展させていった。
星野代表は、「苔」プロジェクトの成功要因は、現地スタッフが信じる「その地域の魅力」をサービスに落とし込み、最後までやり切ったことだと分析している。その地域の魅力を一番よく知っているのは、その土地に暮らすスタッフだからだ。だから星野代表は、各ホテルの運営方針や提供サービスに関して意見は言うが、最終決定は現地スタッフに任せるようにしている。
フラットな組織文化が斬新なアイデアを生む

LeeYiuTung/iStock/Thinkstock
2017年、「星野リゾート 軽井沢ホテルブレストンコート」は、まったく新しいウエディングサービスをスタートさせた。マルシェ(市場)のような開放的な空間を用意し、参列者が自由に時間を過ごしながら交流を深め、新郎新婦の門出を祝うパーティを設計したのだ。
新しい結婚式を提案することを決めたのは、入社以来、15年間にわたってブライダル事業を担当してきた鈴木氏だ。彼の呼びかけによって15人のメンバーが集まり、世代や性別、部門、ポジションの垣根を越えて自由な議論を行った。互いの発言からインスピレーションを得て議論を深化させるうちに、新しいウエディングサービスの骨格が見えてきたのだ。アイデアを星野代表にプレゼンしたところ、彼のアドバイスは「ターゲット世代のスタッフの意見をよく聞いて」ということに尽きた。
議論が紛糾したのは、料理についてだった。調理担当メンバーから、1人1コースを配膳する通常の結婚式と比べて、多くの労力がかかるという意見が出た。彼らの発言には、「これまでの倍の人数のシェフが必要かも」「シェフを増やしたら、とても利益なんて出ません」などと、否定的なニュアンスが濃くなっていった。それでも、役割の異なるメンバーを交えて議論を進めるうちに、突破口が開いた。
結果、新サービスはたった3カ月で初年度目標を達成した。役割や得意分野の異なるメンバーがフラットに議論した賜物である。何を発言してもいいという安心感があり、自分が得意な分野で活躍すればいいという場が用意されていることで、社員は自由に発言できる。
組織の常識に挑む社員たち
説得力のある意見が採用される
冒頭に登場した奥入瀬渓流ホテルは、2008年から観光客が激減する冬季の営業を停止してきた。しかし2017年、9年ぶりの冬季営業に踏み切ることとなった。その中心となったのは、同ホテルの総支配人・宮越氏だった。
同ホテルの客室稼働率は、紅葉の見ごろである10月をピークに、11月に入った途端に落ち込む。一方、旅行ニーズに合わせて施設の魅力を高めていった。加えて「苔さんぽ」などプログラムを充実させたこともあり、2016年の春から秋の客室稼働率は平均で80%を超えた。そんな背景があり、宮越氏は、次なる挑戦として冬季営業の再開を考えたのだった。
しかし星野代表は、冬は無理だと絶対に譲らなかった。星野代表を説得するため、宮越氏は現地の冬の魅力を再発見すべく奔走する。するとそこには、凍てついた渓流の滝をはじめとし、美しい景色が広がっていた。宮越氏は、「冬の奥入瀬も魅力的だ」という確信を深めた。スタッフや旅行代理店、行政にも相談したところ、宮越氏の考えに賛同してくれ、冬季営業が再開したのだった。
驚くことに、星野代表は冬季営業再開をOKした覚えはなく、むしろいまだに反対の立場だと言う。冬季営業を再開すると決めたのは、トップではなく現場だったのだ。星野リゾートには「トップにお伺いを立てる意思決定プロセス」は存在しない。トップの意見ではなく、説得力のある意見が採用されるのだ。
立候補プレゼン制度で能力を試し、伸ばす

eternalcreative/iStock/Thinkstock
星野リゾートでは、入社2年目以降の社員であれば誰でも、ユニットディレクター(UD)や支配人に立候補できる仕組みがある。立候補者は、組織運営の目標や戦略を全社員に向けて発表する「立候補プレゼン」を行い、社員の評価をもとに判断される。
これまで3つの施設で総支配人を務めた永田氏も、立候補プレゼンから活躍のフィールドを広げてきた。スパ業務を担当するスタッフの育成を担当していた彼女は、退職していくスタッフの多さに胸を痛めていた。その現状を星野代表に訴えるも、具体的な改善策を持たなかったために、取り合ってもらえなかったという。正義感に燃えた永田氏は、スパ統括部門を新たに設置することを提案するとともに、そのUDに立候補した。部門新設は見送られたが、彼女は、スパ設備を持つ施設「星野リゾート ウトコ オーベルジュ&スパ」の総支配人に就任することとなった。永田氏のマネジメント経験はまだ浅く、リーダーとしては未知数だったが、会社は永田氏の意欲と可能性に懸けたのだ。
永田氏が総支配人に就任した「星野リゾート ウトコ オーベルジュ&スパ」は、東京から遠く、業績が低迷していた。しかし永田氏が総支配人に着任して1年が経過すると、業績は上向いてきた。彼女は、星野リゾートの総支配人の誰よりも多くスタッフとコミュニケーションを取るようにしていたのだった。コミュニケーションを取りながら、スタッフが自分で考え、動き始める現場を目指し、実現させたのだ。
実は星野代表は、「永田さんが総支配人としてここまで活躍するとは思っていなかった」という。上司が見るだけで、人の能力を把握することはできない。その人の能力は、やってみないとわからないし、ポジションに就くことで能力が伸びることもある。だからこそ、自分の力を自由に試せる環境が採用されているのだという。
職場を飛び出す社員たち
地域とリゾートを共存共栄させる
星野リゾートは2012年、沖縄の竹富島に「星のや竹富島」を開業した。竹富島の住民たちは、島の活性化に共に取り組むことを約束した星野リゾートを信じて開業に賛成したものの、着任したばかりのスタッフに対しては警戒心をもっていた。
そんな中、島民の懐に飛び込んでいったのは、サービススタッフの田川氏だった。オフの時間を使い、草むしりを手伝ったり、島の運動会に参加したりした。やがて田川氏は、ホテルスタッフとしてよりも、島に魅せられた1人として島の人たちと付き合うようになっていった。
田川氏が着目したのは、島最大の祭事である種子取祭だ。彼は、島民が大切に守り継いできたこの祭りを宿泊客に見てもらうことで、島の文化や伝統を肌で感じてもらえると考えたのだ。彼は、祭りの運営を手伝いつつ、島の人たちとの交渉に動き出した。
島の人たちにとって、祭りは神事である。神事を観光としても成り立たせるために、厳密な調整が求められた。鑑賞ルールやタイミング、人数などを細かく調整し、田川氏が協力を求めると、島民の気持ちがだんだん傾きはじめていった。そうして、彼が集落に出かけるようになって3度目の秋には、星のや竹富島のオリジナル企画がスタートしたのだった。
田川氏は、種子取祭だけでなく、島民との交流体験を次々とサービスに落とし込んでいった。彼は、星野リゾートが掲げる「日本を観光立国に」というミッションに共感し、その実現に向けて取り組んでいるのだ。
異文化を尊重しつつ、組織文化を根づかせる

Soft_Light/iStock/Thinkstock
2017年1月、星野リゾートは海外初となる「星のや」をインドネシア・バリ島に開業した。星野代表は、バリ島でも、星野リゾートの強みを実践することにした。つまり、地域の人たちが考える地域の魅力をサービスに落とし込む方法だ。加えて、言葉だけでなく文化や価値観も違う土地においても、星野リゾートのおもてなしの考え方や手法、フラットな組織文化を浸透させていくことを決めた。
サービスチームのUDとして現地に赴いたのが、小林氏だ。星野リゾートの組織文化を根づかせ、星野リゾート流のおもてなしとバリらしさを演出できるスタッフを育てることが、小林氏に託された使命であった。
インドネシアは階層社会であり、下の人が意見を言うことは滅多にない。それゆえ、フラットな組織を構築していくのが非常に難しかった。また、対立や争いを避けるため、発言をためらう傾向にあることも課題だった。そこで小林氏は、「言いたいことがあれば、誰でも発言していい」というメッセージを繰り返し伝えるようにした。加えて、ミスがあっても決して責めず、なぜミスが起こったのか、防ぐにはどうすればいいのかを伝える姿勢に徹した。そのうちに「ミスが起きて悔しい」といった発言が出るようになり、改善策の提案がなされるようになる。こうして、意見を出し合い、それを業務に反映させ、実践することができるようになったのは、大きな進歩だった。
文化や価値観が異なるため、まだまだ課題も多い。しかし小林氏は、文化の違いを理解し、尊重してマネジメントすることを心掛けている。こうした経験は、星野リゾートにとっても貴重なノウハウになるはずだ。

この続きを見るには...
残り0/4167文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.06.16
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











