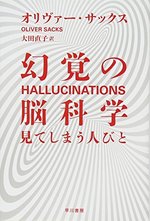世界を救った日本の薬
画期的新薬はいかにして生まれたのか?
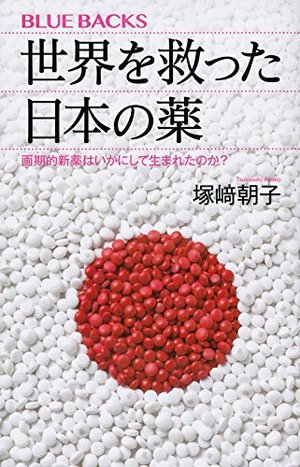
著者
塚﨑 朝子 (つかさき あさこ)
ジャーナリスト。読売新聞記者を経て、医学・医療、科学・技術分野を中心に執筆多数。国際基督教大学教養学部理学科卒業、筑波大学大学院経営・政策科学研究科修士課程修了、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科修士課程修了。専門は医療政策学、医療管理学。著書・編著書に『新薬に挑んだ日本人科学者たち』『慶應義塾大学病院の医師100人と学ぶ病気の予習帳』(以上、講談社)、『iPS細胞はいつ患者に届くのか』(岩波書店)などがある。
ジャーナリスト。読売新聞記者を経て、医学・医療、科学・技術分野を中心に執筆多数。国際基督教大学教養学部理学科卒業、筑波大学大学院経営・政策科学研究科修士課程修了、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科修士課程修了。専門は医療政策学、医療管理学。著書・編著書に『新薬に挑んだ日本人科学者たち』『慶應義塾大学病院の医師100人と学ぶ病気の予習帳』(以上、講談社)、『iPS細胞はいつ患者に届くのか』(岩波書店)などがある。
本書の要点
- 要点1現代医学は西洋医学が中心で欧米発の薬が多いが、日本人が開発した薬も少なくない。
- 要点2ノーベル賞を受賞した大村智が発見したのが、熱帯の寄生虫病オンコセルカ症の特効薬イベルメクチンだ。開発途上国で無償提供され、年間3億人以上を救っている。
- 要点3がん治療のひとつ「免疫療法」の発展に貢献したのが本庶佑(ほんじょたすく)である。免疫療法は着想から半世紀以上も実現されていなかったが、本庶が“免疫のブレーキ役”PD-1を発見したことで、開発が進展した。
- 要点4創薬は確率の世界だ。発見された有望な新規物質が実用化される確率は2万~3万分の1にすぎない。
要約
【必読ポイント!】 新薬開発における日本人の活躍
人類の歴史は薬の歴史

okskaz/iStock/Thinkstock
わたしたち人類の歴史は、ある意味で薬の歴史ともいえる。世界最古の薬の記録は、紀元前3000年頃までさかのぼるという。古代メソポタミアの粘土板に薬の処方が記されていたのが、それだ。
人の体は病に冒されるものである。人類は誕生とともに、病気と付き合うことを余儀なくされてきた。かつて天然痘、ペスト、チフス、コレラ、破傷風、結核などの伝染病(感染症)が猛威をふるい、多くの人々の命を奪った。
人類の命を救う抗生物質ペニシリンが、青カビのなかから発見されたのは1928年のことである。英国のアレクサンダー・フレミング(Alexander Fleming)が見つけたのち、米国人科学者が合成に成功。世界初の抗菌薬が開発された。これにより人類は感染症を乗り越え、より長生きできるようになった。寿命が伸びたら伸びたで、今度は生活習慣病や認知症と向き合うことになったのだが。
日本の薬の歴史
現代医学の中心は西洋医学だが、「薬」の歴史ではもともと東洋が先行していた。紀元前200年頃、中国最古の『黄帝内経(こうていだいけい)』が編纂され、後漢の時代(25〜220年)には治療法を記した『傷寒雑病論(しょうかんざつびょうろん)』がまとめられた。このなかには「葛根湯」など、生薬の処方に関する記載も見られる。
日本で歴史が長いのは漢方医学だ。6世紀頃、朝鮮半島を経由して日本へ伝わり、日本独自の民族性や風土に合わせて進化していった。日本人が考案した漢方もある。紀伊国(和歌山県)の外科医・華岡青洲(はなおかせいしゅう)による「十味敗毒湯(じゅうみはいどくとう)」がそれである。そのなかには桜皮(おうひ)という日本の生薬が含まれていた。華岡は世界ではじめて、全身麻酔下での乳がんの摘出手術に成功したことでも知られている。
一方で日本の薬学は、ヨーロッパの薬学を推進した合成化学を中心に発展。日本における創薬は戦後になって本格化し、1990年代以降は次々と新薬が日本から生み出されている。
ただしそうやって生み出された新薬が、常に完全な薬だったわけではない。たとえば熊本大学の満屋裕明(みつやひろゆき、現・国立国際医療研究センター研究所所長)は、世界ではじめてエイズ治療薬「逆転写酵素阻害薬アジドチミジン(AZT)」を開発した。この薬には強い副作用があり、薬価も非常に高額だった。だが満屋は延命を第一に考えており、その後も「生き延びよ、時間を稼げ」を合い言葉に、第2・第3のエイズ治療薬を世に送り出している。
意外と知られていない日本発の薬

Ca-ssis/iStock/Thinkstock
歴史的に見ると欧米発の薬が多いが、実は日本発の薬も少なくない。たとえば人類にもっとも貢献した日本発の薬に、抗寄生虫薬のイベルメクチンがある。2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智(現・北里大学特別栄誉教授)により発見された。

この続きを見るには...
残り3177/4379文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.07.15
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は 塚崎 朝子、株式会社フライヤー に帰属し、事前に山口 絵理子、株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ること なく本資料の活用、およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、 本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は 塚崎 朝子、株式会社フライヤー に帰属し、事前に山口 絵理子、株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ること なく本資料の活用、およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、 本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
一緒に読まれている要約