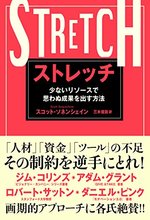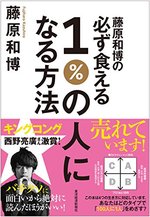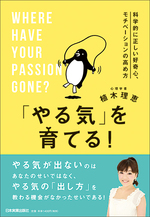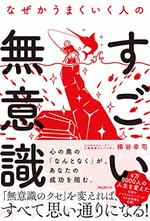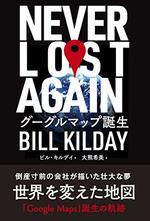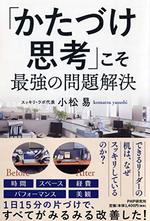未来をはじめる
「人と一緒にいること」の政治学
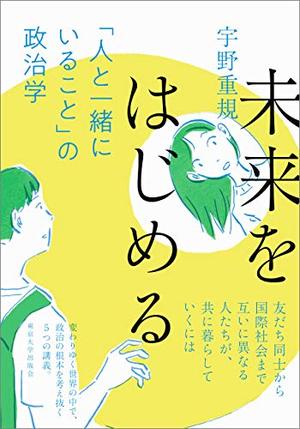
著者
宇野 重規(うの しげき)
東京大学社会科学研究所教授。専門は政治思想史、政治哲学。1967年東京都生まれ。1991年東京大学法学部卒業。1996年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。著書に、『デモクラシーを生きる――トクヴィルにおける政治の再発見』(創文社、1998年)、『政治哲学へ――現代フランスとの対話』(東京大学出版会、2004年)、『トクヴィル 平等と不平等の理論家』(講談社選書メチエ、2007年)。『〈私〉時代のデモクラシー』(岩波新書、2010年)、『民主主義のつくり方』(筑摩選書、2013年)、『西洋政治思想史』(有斐閣、2013年)、『政治哲学的考察――リベラルとソーシャルの間』(岩波書店、2016年)、『保守主義とは何か――反フランス革命から現代日本まで』(中公新書、2016年)ほか。
東京大学社会科学研究所教授。専門は政治思想史、政治哲学。1967年東京都生まれ。1991年東京大学法学部卒業。1996年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。博士(法学)。著書に、『デモクラシーを生きる――トクヴィルにおける政治の再発見』(創文社、1998年)、『政治哲学へ――現代フランスとの対話』(東京大学出版会、2004年)、『トクヴィル 平等と不平等の理論家』(講談社選書メチエ、2007年)。『〈私〉時代のデモクラシー』(岩波新書、2010年)、『民主主義のつくり方』(筑摩選書、2013年)、『西洋政治思想史』(有斐閣、2013年)、『政治哲学的考察――リベラルとソーシャルの間』(岩波書店、2016年)、『保守主義とは何か――反フランス革命から現代日本まで』(中公新書、2016年)ほか。
本書の要点
- 要点1現代の民主主義は、ルソーの思想に大きく影響を受けている。ルソーは、全ての人が自由かつ平等で、しっかりと判断ができるという前提のもと、一般意志に自発的に従うことで他者とつながることが可能だと説いた。
- 要点2多数決には不完全な面があり、選挙制度自体に工夫の余地がある。また、選挙だけに頼らない熟議民主主義という形態も登場しつつある。
- 要点3人が行動を変え、習慣も変えることで、その人の人格までもが変わるように、個々の変化が社会の変化にもつながっていく。
要約
変わりゆく世界で、人とともに生きていくには
未来予測の多くは外れる
現在の日本の状況を考えると、お先真っ暗と思う人もいるかもしれない。しかし、まず強調したいことは、多くの未来予測は外れるということだ。約30年前に作られた映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」では、2015年に偉そうな日本人上司が出てきて、主人公に「お前はクビだ」と宣告する場面がある。当時は、これからは日本の時代だという雰囲気があったためだろう。しかし、実際には予想はかなり外れたといえる。
同様に、現在の人々が「当たり前」と思っていることも、少し前までは全く常識ではないことも多い。思い込みを捨てて長い射程で考えることが重要だ。
グローバル化と民主主義は両立しない?

stocksdaily/gettyimages
かつて貴族は貴族、平民は平民と、まったく違う人間だと思われていた。しかし、それから世界がどんどんつながっていき、人々はみな同じ人間として平等化が進んだ。それに伴い、人々は互いの違いにいっそう敏感になった。違いがあると「不平等だ」と感じやすくなった。
こうした考え方は、グローバル化とデモクラシーが抱える問題にも関連してくる。世界はグローバル化によって緊密につながっていった。これにより、先進国の中間層以下の人々は、圧倒的に損をすることになった。ダメージを受けた人たちの声を反映するのが民主主義である。象徴的なことに、これまで新自由主義やグローバリズムを進めてきたイギリスとアメリカからとくに悲鳴が上がっている。
グローバル化で世界がつながっていくことと、民主主義で人々の意見を政治に反映すること。いずれもよいことであるが、これらが常に両立できるとは限らない。よって、どれだけ平等化が進んでも、対立や矛盾はまずなくならないだろう。
そんな中、異なる意見をもつ人がどう一緒に暮らしていくか。これを考えるのが、政治の役割である。学生にとって身近な例を挙げると、クラスで修学旅行の行き先を議論し、多数決で決めることも、広い意味では政治といってよい。
働くこと、生きること
実は「新しい」分業モデル
「男の人は外で働き、女の人は家にいるのが日本の伝統」といわれることがある。だが、歴史的には必ずしもそうではない。日本では、20世紀半ばまで、女性が働くのは当たり前とされていた。ある時期までは欧米と比較しても、日本の女性の就労率は高かった。むしろ欧米の方が、職場で女性が排除される傾向にあった。
日本で現在当たり前だと思われている「サラリーマン」という仕事の形態や、それを専業主婦が支えるというモデルは、高度経済成長期以降に生まれたものである。この分業モデルはもうすぐ終焉を迎えるだろうが、そもそも日本の伝統というわけではないという点を、著者は強調する。
多くの場合、文化は仕組みや制度の問題である。仕組みや制度を変えれば、新しい働き方の文化をつくり出せる。
政治に何を期待するか

iamnoonmai/gettyimages
政治の大きな目的は経済発展である。ただし、市場経済では必然的に不平等が生じる。民主主義社会では、一定の平等性が必要だと著者は考えている。そのため、市場経済で生まれる格差はどこかで是正される必要がある。

この続きを見るには...
残り2784/4074文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2018.12.30
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約