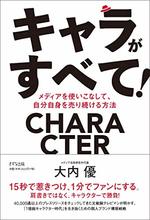AIをビジネスに実装する方法
「ディープラーニング」が利益を創出する

著者
岡田 陽介(おかだ ようすけ)
株式会社ABEJA代表取締役社長
日本ディープラーニング協会理事
1988年愛知県名古屋市出身。10歳でプログラミングをスタート。高校でCGを専攻し、全国高等学校デザイン選手権大会で文部科学大臣賞を受賞。大学在学中、CG関連の国際会議で発表多数。その後、ITベンチャー企業を経て、シリコンバレーに滞在中、人工知能(特にディープラーニング)の革命的進化を目の当たりにする。帰国後の2012年9月、日本で初めてディープラーニングを専門的に取り扱うベンチャー企業である株式会社ABEJAを起業。2017年には、ディープラーニングを中心とする技術による日本の産業競争力の向上を目指し、日本ディープラーニング協会の設立に参画、理事を務める。AI・データ契約ガイドライン検討会委員(2017年12月~2018年3月)、IoT新時代の未来づくり検討委員会 産業・地域づくりワーキンググループ構成員(2017年12月~2018年3月)、IoT推進コンソーシアム・カメラ画像利活用サブワーキンググループ構成員(2017年11月~2018年3月)、AI社会実装推進委員会委員(2017年12月~2018年2月)、Logitech分科会委員(2018年2月~、2018年8月末時点継続中)等、公的な審議会での委員も歴任。
株式会社ABEJA代表取締役社長
日本ディープラーニング協会理事
1988年愛知県名古屋市出身。10歳でプログラミングをスタート。高校でCGを専攻し、全国高等学校デザイン選手権大会で文部科学大臣賞を受賞。大学在学中、CG関連の国際会議で発表多数。その後、ITベンチャー企業を経て、シリコンバレーに滞在中、人工知能(特にディープラーニング)の革命的進化を目の当たりにする。帰国後の2012年9月、日本で初めてディープラーニングを専門的に取り扱うベンチャー企業である株式会社ABEJAを起業。2017年には、ディープラーニングを中心とする技術による日本の産業競争力の向上を目指し、日本ディープラーニング協会の設立に参画、理事を務める。AI・データ契約ガイドライン検討会委員(2017年12月~2018年3月)、IoT新時代の未来づくり検討委員会 産業・地域づくりワーキンググループ構成員(2017年12月~2018年3月)、IoT推進コンソーシアム・カメラ画像利活用サブワーキンググループ構成員(2017年11月~2018年3月)、AI社会実装推進委員会委員(2017年12月~2018年2月)、Logitech分科会委員(2018年2月~、2018年8月末時点継続中)等、公的な審議会での委員も歴任。
本書の要点
- 要点1AIは自社のボトルネックとなる経営課題を解決するために活用すべきである。
- 要点2ディープラーニングの画像認識の精度は人間以上になった。AIの導入によって非構造化データが宝の山に変わる。
- 要点3AIを導入することで、経験とカンだけに頼ることなく、ファクト・データをもとにした仮説の検証、施策の検討・立案が可能になる。
要約
なぜ、いまだにAI導入を躊躇するのか
ディープラーニングの衝撃を目の当たりに
2012年10月、人工知能、コンピュータービジョンの研究者・企業に衝撃が走った。世界的なAIの画像認識コンテストILSVRC。そこで、25~26%台だった画像認識のエラー率を10%以上下げることに成功したチームが出現したからだ。それがトロント大学のジェフリー・ヒントン教授率いるスーパービジョンチームだ。
彼らが用いた手法が「ディープラーニング(深層学習)」である。この結果を受け、さらなるエラー率の低下が可能だと踏んだ企業や研究者が、ディープラーニングの研究に取り組み始めた。そして2015年には、ディープラーニングの画像認識の精度は人間以上となった。
ディープラーニングは、もはや枯れた技術

Daisy-Daisy/gettyimages
著者は、2012年9月に日本で最初のディープラーニング企業ABEJA(アベジャ)を創業した。IT系の世界ではすでに、AppleのiPhoneやMacに搭載されているSiriなどの音声認識技術に、ディープラーニングが活用されている。また、Amazon EchoやGoogle Homeなどのスマートスピーカーにも、ディープラーニングが活用されている。このように、IT企業ではAIは以前から活用されており、それ以外のビジネスでも、AIを当たり前に使うフェーズに入っている。
Googleは「ディープラーニングは、もはや枯れた技術だ」とすら公言している。彼らの認識はこうだ。「いまになって、一般企業が導入するかどうかで迷うなんて、論外だ。なぜ活用しないのか? だって、もう枯れ始めている(十分に使われている)技術なんだから」。
ディープラーニングのすごさ
従来の機械学習とディープラーニングを用いた機械学習の違いについて説明する。前者は「特徴量の抽出方法」を人が設計して入力する。これに対し、後者はコンピューターにそれを自動でやらせるという違いがある。
従来の機械学習では、たとえば犬と猫の識別をしたいなら、「犬である」あるいは「猫である」ことを指し示す特徴量を、人間が設計しなければならない。一方ディープラーニングを用いた場合だと、大量の教師データから特徴量の抽出を自動で行ってくれる。これにより推論の精度を高められるのだ。
AIの導入前に知っておきたいこと
ボトルネックにAIを注ぎ込む

Jirapong Manustrong/gettyimages
現状では、企業利益に貢献しないAI投資・導入をしている企業が多い。その原因は、導入のROI(投資対効果)を考えずに、「AIでこんなことができる」と知って、導入に走ってしまうからだ。そうではなく、自社のボトルネックとなる経営課題を解決するためにAIを活用すべきである。
そのためには仮説を立てることが重要となる。まずは、自社の事業や業務プロセスを分解する。どの工程から付加価値が出ていて、どのあたりがボトルネックになっているか。そのうち、どの部分を変えると利益が伸びそうか。こうした点を、実証実験を通じて検証していく。
小売・流通業の例を挙げよう。ショッピングセンターの来店客の人数を詳細にカウントするために、人を置くとする。時給1000円で1日1万2000円。1か月36万円。10カ所でカウントするならば、1か月で360万円、1年で4320万円になる。
一方、AIを活用すると、1台あたり月1万6000円でカメラを取り付けて、来店客の人数をカウントできる。10カ所で16万円、1年で192万円。こうした結果を見ると、「コスト・正確性・データ量」の観点から、人間よりもAIの方が優れていることは明らかである。
非構造化データは宝の山
画像、音声などの非構造化データは、従来は自動判定が難しいものだった。それがディープラーニングによって、高い精度で自動的に判定できるようになり、ビジネスの現場でも活用され始めている。
小売店の例を見ていこう。ディープラーニングで「顔データ」などの非構造化データを分析する。そうすれば、来店客の属性だけでなく、店内のどこで立ち止まっているのか、どういった導線行動を取っているのかがわかる。そこから「買わなかった」理由を推定できる。

この続きを見るには...
残り2718/4410文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2019.01.03
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約