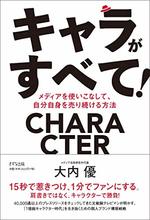メルカリ
希代のスタートアップ、野心と焦りと挑戦の5年間


著者
奥平 和行 (おくだいら かずゆき)
1999年、日本経済新聞社入社。東京本社編集局産業部(現企業報道部)に配属となり、商社、自動車、電機、通信などの業界を担当。2010~2014年には米シリコンバレー支局でITやスタートアップを取材した。2017年より編集委員。IT、自動車、スタートアップなどをカバーする。
1999年、日本経済新聞社入社。東京本社編集局産業部(現企業報道部)に配属となり、商社、自動車、電機、通信などの業界を担当。2010~2014年には米シリコンバレー支局でITやスタートアップを取材した。2017年より編集委員。IT、自動車、スタートアップなどをカバーする。
本書の要点
- 要点1山田進太郎を中心とする創業メンバーがめざすのは、「世界で使われるインターネットサービスを創る」というビジョンである。そこで生まれたのがメルカリだった。
- 要点2メルカリが短期間でフリマアプリ市場のシェアをとれた要因は、使いやすいユーザーインターフェース、改善のスピードの速さ、そしてマーケティングの巧みさなどであった。
- 要点3メルカリは、急成長のひずみを経験しながらも、テックカンパニーとしてのプレゼンスを高め、さらなる成長に向けた新たな挑戦を続けている。
要約
メルカリ誕生
再起動
東京・六本木で、コウゾウというちょっと変わった名前の企業が誕生した。2013年2月のことだ。9ヶ月後にメルカリに社名を変更し、現在ではフリマアプリ業界を代表する企業となった。共同創業者の山田進太郎にとっては、過去に創業したウノウを米ソーシャルゲーム大手のジンガに売却して以来の「再起動」である。
共にメルカリ創業メンバーとして集まったのは、バンク・オブ・イノベーションというスタートアップで動画検索サービス「Fooooo」を世に出した経験のある富島寛。そして、米国のゲーム開発会社であるロックユーの創業メンバーであり、日本法人ではCOOも務めていた石塚亮の2人だった。
「世界で使われるインターネットサービスを創る」。こうしたビジョンのもと、スマートフォンの急速な普及を背景に、山田はスマートフォンを利用したフリマに可能性を感じていた。
後に引けない戦い

gorodenkoff/gettyimages
滑り出しは順調ではなかった。会社を登記した直後には、8人のエンジニアがメルカリに関わっていた。その多くは、まだ本業を持っている掛け持ち状態だった。そんななか、開発の中核を担っていたエンジニアが突然離職する事態になった。また、当初は開発言語にHTML5を用いていた。だが、技術的な問題から、ネーティブで一から作り直すことを余儀なくされた。
そんな苦難を乗り越えた後、イーストベンチャーズから、シードマネーとして5000万円の出資を受けることが決まった。イーストベンチャーズのパートナーを務めるのは、山田が唯一無二のメンターと慕う人物、松山太河である。ベンチャーキャピタルの資金を受け入れることは、責任が格段に増し、後に引けない戦いに臨むことを意味していた。
割り切る
エンジニアの数や資金にも限りがあるなか、iPhoneとアンドロイド両方のアプリを開発するのは困難だった。アプリのリリースを予定していた2013年7月まで、3週間を切った頃のことだ。リリースを延期するか、一部機能の実装を見送るか。メルカリのメンバーはこうした選択を迫られた。結果、商品の検索機能の開発を見送ることとなった。
さらには、売上金を銀行口座に振り込むための機能の開発が間に合わず、それなしでリリースすることを決めた。元々、規約で最初に出金できるようになるのは、販売から2週間後と決めていた。よって、それまでにアプリを更新して間に合わせればいいと割り切ったのだ。まさに綱渡りだったといえる。こうして、フリマアプリ「メルカリ」が公開された。
【必読ポイント!】 メルカリ逆転劇
焦る理由

maroke/gettyimages
インターネットを使って個人が物品を売買する。こうしたサービスの国内での歴史は、ヤフーが1999年に始めた「ヤフオク!」にさかのぼる。同サービスは、パソコンの普及を追い風に成長を続けた。しかし、携帯電話やスマートフォンの利用増加にうまく対応できず、伸び悩んでいた。フリマアプリ市場の成長の背景には、ヤフオク!の取りこぼしが目立っていたという事情もある。
フリマアプリのライバルとして名前があがることが多かったのが、インターネット企業のファブリックが運営する「フリル」だ。フリルはメルカリよりも1年早くサービスを開始し、若い女性にターゲットを絞ったことで成果を上げつつあった。

この続きを見るには...
残り1853/3194文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2019.01.14
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約