センスメイキング
本当に重要なものを見極める力
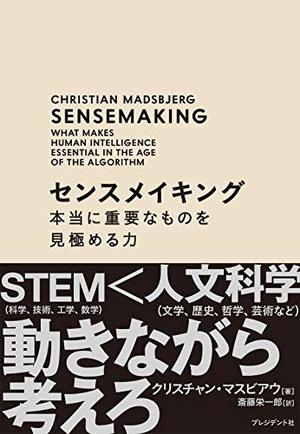
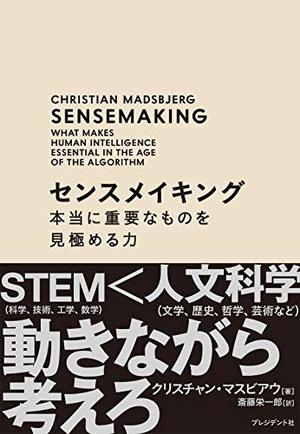
著者
クリスチャン・マスビアウ (Christian Madsbjerg)
ReDアソシエーツ創業者、同社ニューヨーク支社ディレクター。ReDは人間科学を基盤とした戦略コンサルティング会社として、文化人類学、社会学、歴史学、哲学の専門家を揃えている。マスビアウはコペンハーゲンとロンドンで哲学、政治学を専攻。ロンドン大学で修士号取得。現在、ニューヨークシティ在住。
ReDアソシエーツ創業者、同社ニューヨーク支社ディレクター。ReDは人間科学を基盤とした戦略コンサルティング会社として、文化人類学、社会学、歴史学、哲学の専門家を揃えている。マスビアウはコペンハーゲンとロンドンで哲学、政治学を専攻。ロンドン大学で修士号取得。現在、ニューヨークシティ在住。
本書の要点
- 要点1IT至上主義のいま、教育の現場でも理系ばかりが重視される傾向にある。しかし経営者や高い地位にいる高収入者、世界でイノベーションを起こすような人々には、文学、哲学、歴史学、政治学などの人文学系大学出身者が多い。
- 要点2知性、精神、感覚といった「人間性」をフル活用させ、人文科学に根ざした実践的な知の技法を「センスメイキング」と呼ぶ。
- 要点3シリコンバレーを中心にはびこる「何ごとも技術が解決する」「あらゆるものを数値化する」という態度は、センスメイキングの対極にある。
要約
【必読ポイント!】 センスメイキング
本当に成功しているリーダーとは?

Benjavisa/gettyimages
アマゾンやグーグルをはじめ、数多くの企業がビッグデータを各々のビジネスに利用している。いまや誰もが「データは多ければ多いほど、気づきやひらめきが増える」と信じている。そういった風潮のなか、教育の世界で工学や自然科学などの理系ばかりが重要視されるのは当然の流れだ。1960年代以降、人文科学系大学の学位数は半減し、助成金も減額の一途を辿っている。文学や歴史、哲学、芸術、心理学、人類学といった文化を探求する学問は、「社会的要請」に応えられないというレッテルを貼られているのが現状だ。
しかしここに「意外な」事実がある。2008年の『ウォール・ストリート・ジャーナル』で報じられた国際的な報酬に関する調査結果によると、理系専攻(科学・技術・工学・数学)の学生は、大学卒業後はたしかに良い職に恵まれている。しかし全米で中途採用の年収上位10%となると、政治学や哲学、演劇、歴史といった教養学部に強い大学の出身者が大半を占めるのだ。つまり経営を取り仕切るような地位にいる高収入者、ガラスの天井を突き破る力のある人、世界でイノベーションを起こすような人の多くは、人文学を学んでいるのである。
もちろん理系の知識も不要なわけではない。しかし本当に成功しているリーダーは、「好奇心旺盛で幅広い教育を受けていて、かつ小説も帳簿も読める」能力を持った人物ということである。
人間力をフル活用した知の技法
スターバックスは全世界に支店を持っている。同社の成功の背景には当然、最先端の技術と定量分析がある。最新型のコーヒーマシンや焙煎機、効率的なサプライチェーン、きちんと作りこまれた携帯アプリ。しかし彼らの成功の根幹は、「シンプルかつ深い文化的洞察力」にこそあるという。
35年前、北米のコーヒー文化はいまとはまったく異なるものだった。どの家庭にもあるような生ぬるいカップコーヒー程度しかなく、カフェ=コミュニティスペースという概念もなかった。
あるときスターバックスの中興の祖であるハワード・シュルツは、イタリアの言葉や文化を学ぼうと直感的にひらめいた。シュルツは早々にイタリアへ飛び、有名なバール(伝統的なカフェ)で学んだ後、当時コーヒー豆や紅茶の販売しかしていなかったスターバックスをカフェとして新たに立ち上げた。そしてシュルツはイタリアのコーヒー文化に手を加え、米国のライフスタイルに合わせた新しい文化を作ったのだ。これが成功したのは、シュルツが「文化的な知」を動員させたからに他ならない。
このように知性、精神、感覚といった「人間性」をフル活用させ、文化を調べ理解することを、著者は「センスメイキング」と呼んでいる。センスメイキングは、人文科学に根ざした実践的な知の技法だ。データ至上主義であるアルゴリズム思考の対極にあると言っていい。
1回のウィンクからわかること

Photos.com/gettyimages
センスメイキングのもとをたどれば、はるか昔のギリシャ時代、アリストテレスにたどり着く。アリストテレスは「フロネシス」を提唱した哲学者だ。フロネシスとは、知識と経験を融合させた「実践知」のことである。熟練した有能な政治家がフロネシスを発揮すれば、自身の選挙区内で起きそうなあらゆる出来事を一瞬で想像できる。あるいはベテラン管理職であれば、組織内に漂う些細な変化も察知できる。豊富な知識と経験を併せ持つリーダーの多くは、社会や制度、組織を自身の延長だと捉え、自分自身もそれらの一部であると考えている。
センスメイキングは一朝一夕で身につくものではない。

この続きを見るには...
残り2752/4229文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2019.01.24
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











