なぜ倒産
23社の破綻に学ぶ失敗の法則
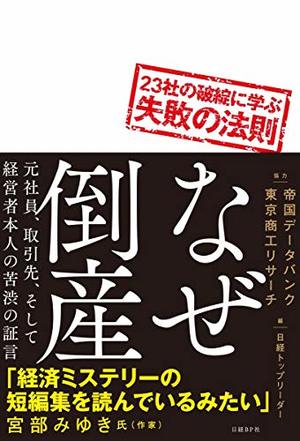
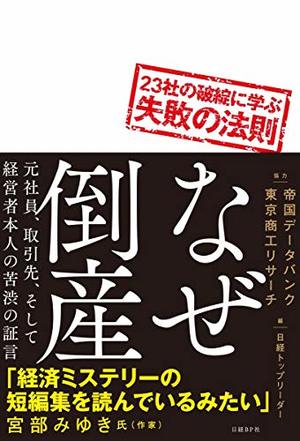
著者
日経トップリーダー
企業経営者向けの月刊誌(日経BP社刊行)。1984年「日経ベンチャー」として創刊し、2009年「日経トップリーダー」に誌名変更。次世代の経営者を育てるべく、名経営者の独自の発想や高収益企業を支えるユニークな仕組みなどを取材、分かりやすく解説する。本書の題材となった「破綻の真相」は、1992年「倒産の研究」として始まり、四半世紀以上続く人気連載。
企業経営者向けの月刊誌(日経BP社刊行)。1984年「日経ベンチャー」として創刊し、2009年「日経トップリーダー」に誌名変更。次世代の経営者を育てるべく、名経営者の独自の発想や高収益企業を支えるユニークな仕組みなどを取材、分かりやすく解説する。本書の題材となった「破綻の真相」は、1992年「倒産の研究」として始まり、四半世紀以上続く人気連載。
本書の要点
- 要点1他社の成功事例をそのまま自社に当てはめても、同じように成功するとは限らない。再現性の高い失敗の定石を学ぶことによって、自社の経営に役立てることが重要だ。
- 要点2倒産を迎えた企業には、経営状況の把握やリスク対策の甘さ、変化への対応力の低さといった共通のパターンが見られる。
- 要点3企業の明暗を分けるのは、変化に対応するスピード感のわずかな差だといえる。
要約
【必読ポイント!】 急成長には落とし穴がある
脚光を浴びるも内実が伴わない
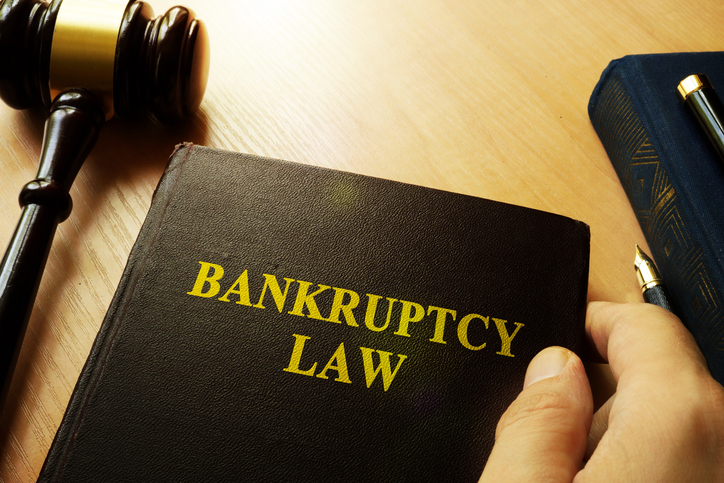
designer491/gettyimages
優れた業態を生み出しても、内実が伴わなければ経営不振に陥る。この事実を教えてくれるのが、遠藤商事・ホールディングスだ。
同社は2011年、東京・吉祥寺に客単価3000円程度のイタリア料理店をオープンさせた。これを皮切りに、多店舗化を始めた。「マルゲリータ1枚350円」を打ち出して、東京・渋谷に出したFC1号店には女性客が殺到。他社と共同で「ナポリス」100店をめざすFC運営会社を設立する。誰でもピザがうまく焼けるという窯や生地伸ばし機をセットし、アルバイトでも1枚90秒で本格ピザが提供できる仕組みを構築。それが評価され、飲食業界を変える優れたベンチャー企業として表彰を受けるほどだった。
しかし、急成長に伴い店舗拡大を急ぐあまり、人材育成が追いつかなくなった。社長は100店達成の夢を追うため、いったん出した店の撤退を嫌った。利益が出なくなったFC店オーナーが撤退を申し出ても、社員による支援を強化するなどして乗り切ろうとした。
ところが、出店は金融機関からの借り入れに頼っていた。そのため、負債が増えて金融機関の姿勢が変わると、資金繰りが苦しくなった。次第に取引先への支払いが滞るようになり、従業員への給与支払いも停止へ。従業員が出社しないようになると、一部の店は閉店に追い込まれた。手元の資金はさらに減少。ついには営業を続けられず破産に至った。
「ナポリス」の業態自体は優れたものであり、業界内外から注目を集めていた。しかし、いかに優れたビジョンを持っていても、少ない投資で成長できるITベンチャーと、飲食ビジネスとでは、かかる費用が決定的に異なる。失敗の原因は、出店費用を甘く見て、手元資金の重要性を理解していなかったことにあるだろう。社内に財務に明るい人間がいなかったことも影響したと考えてよい。
幸運なヒットを契機に傾く経営
ヒットの誕生は、経営者の手腕によるものもあれば時の運もある。ヒットの勢いのまま積極投資をした結果、過剰債務が残って経営破綻につながる場合や、慢心から社員の信頼を失う場合も多いものである。
シリーズ累計250万部を超える大ヒット絵本『こびとづかん』で知られる長崎出版は、その一例といえよう。同社は、2014年に東京地方裁判所から破産手続き開始決定を受け、ファンの間で衝撃が走った。
2006年、児童書出版社から転職してきた編集者が入社早々に出したヒット作が、『こびとづかん』だ。このブームで、業績が右肩上がりで伸びていった。特定の商品に頼る事業構造の脆弱さに気づいていた当時の社長は、次の収益の柱を求めた。本業と離れた投資を繰り返すようになったが、これがつまずきの始まりだった。多角化を狙った投資で、少なくとも2億円以上の損失を被ったと見られる。
さらには、2012年に『こびとづかん』の担当編集者が辞職。経理や財務は社長が管理していたが、お金にルーズなところがあった。そのため、著者への印税支払い漏れが頻発していた。社外の活動が増えると、その傾向に拍車がかかり、編集者が不信感を抱いてしまったのだ。
退職した編集者は、『こびとづかん』のキャラクターグッズの権利を管理していた関連会社で、顧問に就任。著者との出版契約が見直され、最終的に長崎出版は『こびとづかん』の出版権を失った。社長のスポンサー探しも失敗に終わり、同社は営業停止となった。
急激に売上が上がると、事業継続に必要な運転資金も加速度的に増える。その途端に管理の難易度が上がっていく。この事例からは、急成長期こそ土台固めが重要という教訓が引き出せる。
ビジネスモデルが陳腐化したときの分かれ道
世代交代に失敗し、老舗が力尽きる

Zhenikeyev/gettyimages
どんなに優れたビジネスモデルでも、時代とともに陳腐化していく。そんなときに後継者がイノベーションを起こせるかどうかで、企業の明暗は分かれる。
高額宝飾品の輸入販売会社として、高い知名度を誇っていた平和堂貿易。同社の売上高は、1990年代前半には120億円以上であった。だが、2015年9月期には約11億円と、10分の1にまでに売上が縮小していた。
創業当初は「舶来品」にいち早く注目。海外高級腕時計の販売代理店契約を結び、百貨店テナントに卸販売をするというモデルで、業績を伸ばした。欧米ブランド信仰が強い消費者から支持を集め、自社名をセットにして売り出すことによって、会社の知名度を高めていった。
しかし、高額商品の市場が縮み、欧米高級ブランドが日本法人を設立するようになると、売上が減少傾向へ。くわえて、社員の引き抜きが相次いだ。百貨店頼みではダメだとわかっていても、従来の売り方を変えられない。財務体質の改革も遅きに失した。次の方向性を見つけられないまま、同社は自己破産に陥ってしまった。
起死回生を狙った一手が致命傷に
ビジネスモデルを変えるために狙った起死回生の一手が、ときに倒産の引き金になることがある。それを示すのが、切り餅の製造を主力としていた東京もちだ。同社は、冬場には切り餅、切り餅の売上が落ちる夏場にはフルーツゼリーを製造し、着実に事業を拡大していた。

この続きを見るには...
残り1671/3790文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2019.01.29
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約




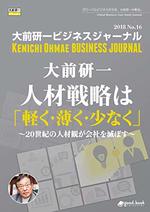
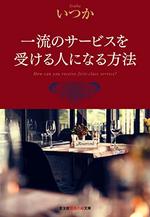




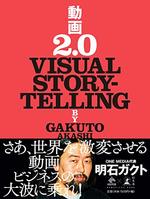
![[完全版]「20円」で世界をつなぐ仕事](https://fd-flier-static-prod-endpoint-b6g9b5dkedfkeqcc.a03.azurefd.net/summary/1763_cover_150.jpg)