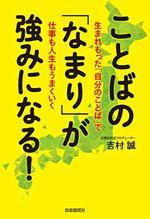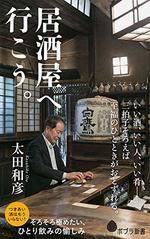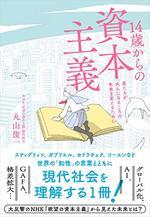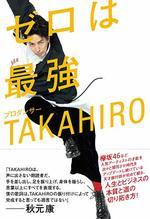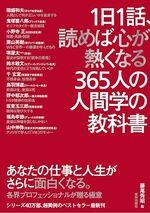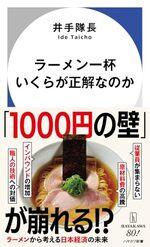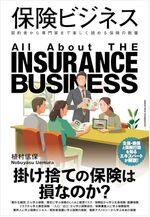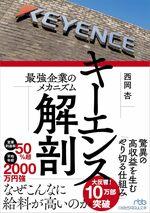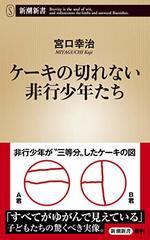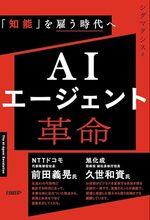【必読ポイント!】 「世界観」という切り口によるアニメ論
「教養」としてのアニメとは
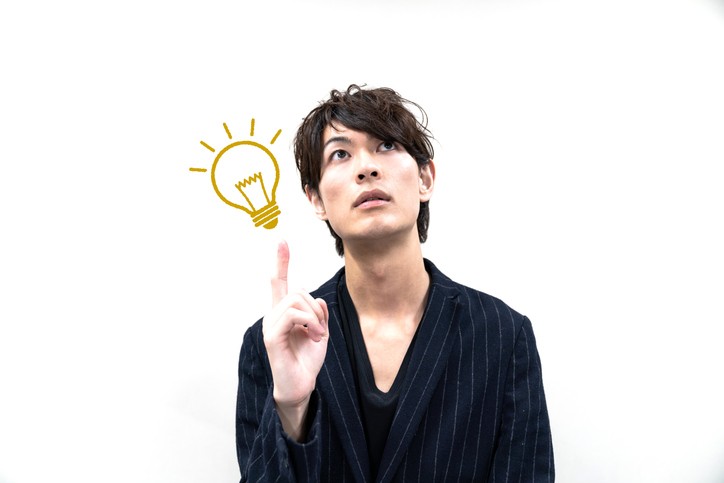
アニメはそれ自体が教養(文化)であり、同時に教養(学問)で分析するに足るものである。というのも日本の商業アニメーションは単なる娯楽ではなく、「インフォテインメント」(Infortainment)=情報娯楽だからである。情報娯楽とは「情報」(Information)と「娯楽」(Entertainment)からなる合成語だ。この情報の部分を教養(学問)で分析、解析するのである。
同時にアニメは「エデュテインメント」(Edutainment)=教育娯楽でもある。エデュテインメントという言葉は「教育」(Education)と「娯楽」(Entertainment)の合成語であり、一般的には「遊びながら学ぶ体験型学習」を意味する。これを転用し、アニメはある種の「教育」として機能するという論を展開することもできよう。こうした方針は、著者の前々著『教養としての10年代アニメ』(2017年)および前著『教養としての10年代アニメ 反逆編』(2018年)から基本姿勢として受け継がれている。
本書ではそれに加え、「世界観」という切り口からのアニメ論も試みる。この着想は文化人類学者であり漫画家でもある都留泰作(つるだいさく)が提唱した「世界観エンタメ」という考え方から来ている。
ただし本書では、文化人類学が定義する「世界観」ではなく、ドイツの哲学者ヴィルヘルム・ディルタイの「世界観学」を批判的に継承した方法を用いる。つまり作品の「世界観」を、読者の「世界像」(Weltbild)へと結びつける試みである。とくに10年代後半のアニメでは、「設定」に凝ったタイプのエンタメが増加傾向にある。物語の「世界観」を読者の有する「世界像」につなぐことができれば、それは読者に資することになるはずだ。
あの世とこの世
『君の名は。』と日本古来の「夢」

フランスの映画研究家ジャン=ルイ・ボードリーによると、映画は「シミュラークル(まがいものという意味だが、ここでは夢)を生み出す装置」だという。であればアニメは、強烈に視聴者の「欲望」を喚起するという意味で、映画よりも強烈な夢の再現装置といえるのではないか。
新海誠監督の第9作目『君の名は。』は、主人公の瀧とヒロインの三葉がみる「夢」を軸に展開するだけでなく、アニメ自体が「夢見の装置」として機能している。一般的に「夢」は、「過去」の経験が形を変えたものとされる。だが『君の名は。』にあらわれる夢は、日本の古代・中世における夢と同じだ。つまり過去よりも「彼方」(未来)に向いているのである。
『古事記』には、神を祀り夢の神告を受けるための寝床「神牀」に関する記載がある。当時は王の夢を見る力が、王権の維持のために必要とされていた。しかしやがて厩戸皇子(聖徳太子)の瞑想の場としての夢殿や、『万葉集』に見られる夢をモチーフとした歌などのように、夢は公的なものから私的、個人的なものになり、「夢の民主化」がなされていく。
平安時代や中世になると、夢は神仏・死者からのメッセージとされた。この時期は夢のメッセージを解読してもらう「夢解き」が、巫女や修験者、陰陽師のような霊能者によって行われていたという。