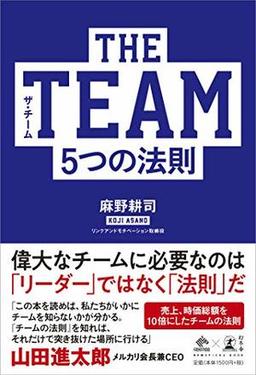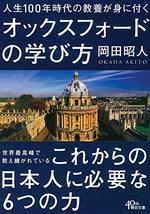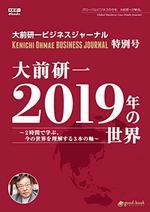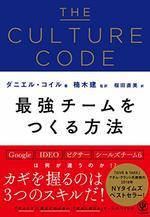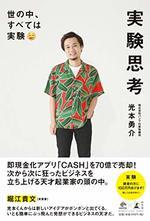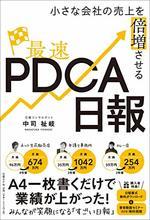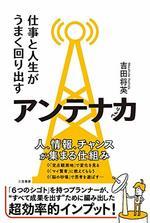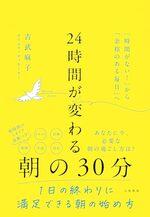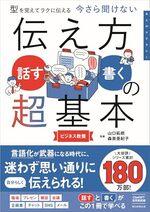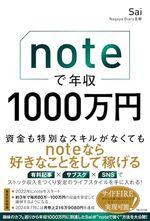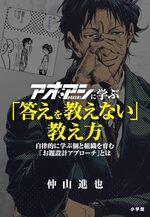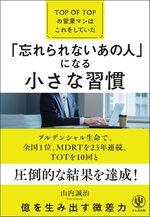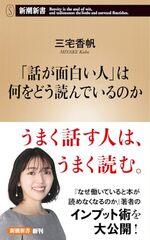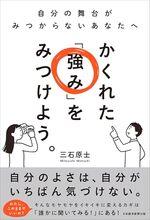目標を設定すれば、チームが変わる
「共通の目的」がある集団は「チーム」になる
まずはチームの定義を確認しよう。2人以上の人間が集まって活動するだけの集団は、「グループ」である。ここに「共通の目的」が加わって初めて「チーム」となる。
本書のチームの定義は「共通の目的を持った2人以上のメンバーがいる集団」だ。「共通の目的」があれば、企業内のチームや学校の部活はもちろん、旅行にいく友人や食事に出かける家族にも、「チームの法則」を活用できる。この法則は、Aim(目標設定)の法則、Boarding(人員選定)の法則、Communication(意思疎通)の法則、Decision(意思決定)の法則、Engagement(共感創造)の法則から構成される。本要約では、著者の提案する5つチームの法則のエッセンスを順に紹介する。
効果的な目標を設定するAimの法則

チームのパフォーマンスは目標設定に大きく左右される。チームの目標を何にするかによって、メンバーの思考や行動が変わるからだ。すると、「目標を確実に達成するチーム」がよいチームだと思うかもしれない。だが、本来大事なのは、「目標を適切に設定する」ことである。Aimの法則では、チームにおける効果的な目標設定の方法を解き明かしていく。
目標には3種類ある。メンバーが取り組むべき具体的な行動の方向性を示す「行動目標」。チームとして手に入れるべき具体的な成果を示す「成果目標」。そして、最終的に実現したい抽象的な状態・影響を表す「意義目標」だ。
ビジネスで重視される目標は、「行動目標」「成果目標」「意義目標」の順に、時代とともに変化してきた。高度経済成長期の日本企業においては、安くてよいものを速く作って届けることが共通の勝ちパターンとされた。それぞれの役職に求められる行動目標を、定められた通りに遂行するチームが評価されたのである。
しかし、ビジネス環境がより速く変化するようになると、勝ちパターンが陳腐化するのも速くなっていく。そこで、1990年代の日本では、チームごとに定量的な成果目標(MBO:Management By Objectives)を定め、期末時点の達成度で評価するようになった。成果を創出するための行動はメンバー自らが考えるようになっていった。
ビジネスのブレイクスルーを生み出す意義目標
しかし、ビジネス環境の変化は加速度を増すばかりだ。チームで設定した成果目標が、半年や一年で効果的でなくなる場合も増えてきた。そこで普及してきたのが、チームが実現すべき目的やチームの存在意義を見据えた「意義目標」に基づく、OKR(Objectives and Key Results)だ。
たとえば、あなたがビールメーカーの営業チームに所属していたとしよう。チームの成果目標は売り上げ1000万円だ。この目標しかなければ、メンバーは、量販店や飲食店に何回訪問するかといったことしか考えないかもしれない。しかし、「ビールの販売を通じて、幸せな食事の時間を届ける」という意義目標が加わるとどうか。たとえば、量販店向けにビールの美味しい飲み方を紹介するポップを提案する。飲食店に向けてビールに合う季節の料理を提案する、といったメンバーが現れるかもしれない。
意義目標は、ブレイクスルーを生み出すきっかけになる。重要なのは、意義目標をチームメンバーが意識し、自発的に行動して成果をあげることである。
状況に合わせてメンバーの「乗り降り」を決める
「誰とやるか」を考えるBoardingの法則

「何をやるか」以上に、「誰とやるか」は、チームのパフォーマンスに多大な影響を与える。Boardingの法則では、誰をチームに入れ、また誰をチームから降ろすかについて探っていく。
そもそも、チームづくりには唯一絶対の正解があるわけではない。自分のチームに合ったアプローチを思考し、選択する必要がある。チームのタイプは「環境の変化度合い」と「人材の連携度合い」の2軸の掛け算で4つに分類できる。まずは自分のチームがどのタイプにあたるかを考えなければならない。