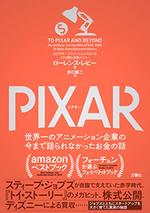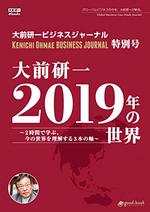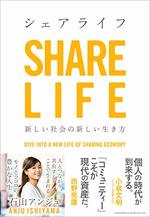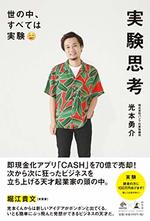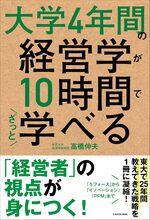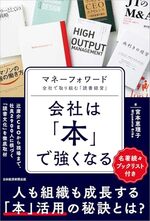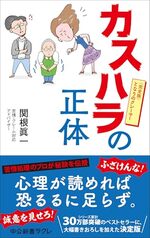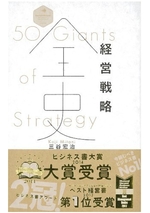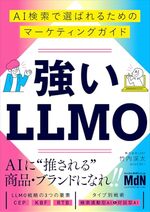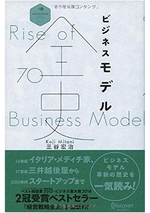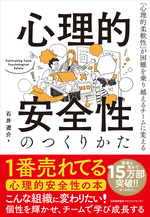コーポレートファイナンス
経営戦略におけるファイナンスの位置づけ
企業の経営戦略には、マーケティング、生産、人材開発、R&Dなどがある。ファイナンス(財務戦略)はそのなかの1つで、資金の調達と投資を通じて企業価値の向上を担う。マネジメントの対象は「貸借対照表(B/S)」「損益計算書(P/L)」「キャッシュフロー計算書(C/F)」の財務3表であるため、この3表の構造を知ることがファイナンス戦略の第一歩となる。
それに対して、ファイナンス以外の戦略は、収益(売上)・費用・利益さえ押さえておけばなんとかなる。そのため、これまでは、一般の社員にはファイナンスは少し遠い世界のことだった。しかし、昨今は、M&A(買収、合併、売却)やベンチャーへの投資といった案件が日常的になってきている。メーカーなどの事業会社でも、ファイナンスは経営を担う人材に不可欠の知識といえる。
【必読ポイント!】 キャラクター分析
現状を知る

ファイナンスの世界では、企業の実力を「企業価値」という言葉で定義する。企業価値は、将来獲得するキャッシュフローの大きさによって決まる。この将来のキャッシュフローを求める作業を「バリュエーション」という。
バリュエーションは、企業の事業計画に基づいて、将来生み出すであろうキャッシュフローと理論的な株価をはじきだす。企業の本質的な価値は、その将来にかかっているという考え方である。
将来を予測するには、まずは正確な現状分析が必要だ。そのために効果的なアプローチが「企業のキャラクター分析」である。人間一人ひとりにキャラクター(個性)があるように、どの企業にも、どこにどんな強みや弱みがあるかというキャラクターがある。そのキャラクターこそが、その企業の将来を形づくっていく。
収益性と生産性
企業のキャラクターは、「収益性」「生産性」「安全性」「成長性」の4つの要素に集約される。相対的に重要なのは収益性と生産性である。この2つが優れていれば、安全性や成長性は必然的に強くなるからだ。
そうした観点から、諸々の財務指標のなかで最初に見るべきものが、「総資産利益率」(ROA:Return On Assets)である。ROAは、企業が投下したすべての資産を使って、どれだけのリターン(利益)を得たかを示す指標だ。「ROA=営業利益/総資産」という式で求められる。この式の右辺は「営業利益/売上高×売上高/総資産」と分解することができる。
「営業利益/売上高」は「営業利益率」、つまり「顧客から獲得した売上高のうち、どれだけの儲け(付加価値=利益)を残すのか」を示す指標で、収益性を表している。
一方、「売上高/総資産」は「総資産回転率」、つまり「企業が本業の事業に投下した総資産を使って、どれだけの成果(売上高)を獲得したのか」を示す指標で、生産性を表している。
キャッシュを生み出す力、ROA

ROAは、収益性と生産性のかけ合わせであり、企業価値のもととなるキャッシュを生み出す力を端的に表す指標だ。
日本の上場企業のROAの平均値は5%である。さらに、売上高営業利益率は6%、総資産回転率は0.8回である(2018年3月期)。そこで、ROA5% ≒ 営業利益率6% × 総資産回転率0.8回という式を頭に入れておく。
そうすれば、得意先や買収対象先の財務内容を調べる際、この平均よりも数字が上か下かで、普通より「良い会社」か「悪い会社」かを判断できる。本書の巻末には、さらに業種別の平均がリスト化されているのでぜひ参照してほしい。
分析の作法
キャラクターの分析には基本的な作法がある。それが「並べる」と「比べる」である。分析の対象となる企業の営業利益率や総資産回転率を時系列に並べることによって、その企業の勢いや傾向を感覚的に把握する。これが「並べる」である。