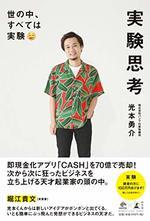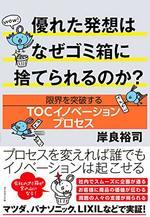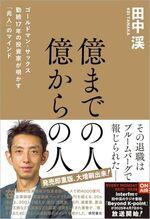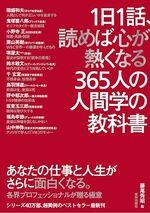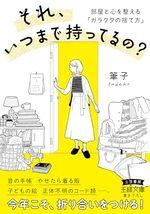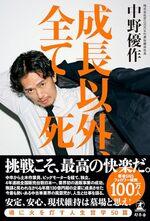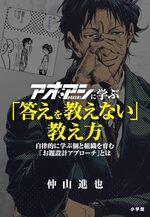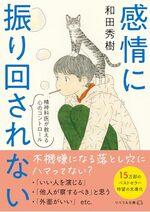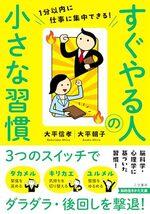【必読ポイント!】 なぜ「自己肯定感」なのか
チャレンジしない子どもたち
子どもは好奇心旺盛なもの。そんな著者の思い込みに反して、「子どもがチャレンジをしない」という悩みを持つ親は少なくないという。親は子どもに新しいことにチャレンジしてほしいと願っている。その一方で、当の子どもはチャレンジせず、そもそも自分のやりたいことがわからない、どうでもいいという状態にある。こうした状況の根源には、子どもたちの自己肯定感の低さがあると著者はいう。
自己肯定感とは、「自分はここにいていい」という感覚のことである。自己肯定感を充分に持てない子どもは、失敗を恐れ、新しいことに取り組もうとしない。
子育てや教育の目標は、子どもの「自立」である。子どもが自立し、成長し続けるには、大人たちが子どもの自己肯定感を支えることが重要なのである。
成果ではなくプロセスに着目する

子どもの自己肯定感を育むうえで留意したいのが、「ほめる」という行為だ。子どもがテストでいい点を取ったり、サッカーの試合で勝ったりしたとする。そのとき多くの親は、子どもの能力や成果に注目しがちだ。
しかし、親が成果や結果だけを評価してしまうと、子どものなかにこうした感情が芽生えていく。「価値があるのは自分ではなく、あくまで〇〇ができる自分であり、ただの自分には価値がない」。こうした価値観は無意識に刷り込まれ、漠然とした不安や焦りとなって、子どもの心に棲みついてしまう。
子どもの自己肯定感を支えるのは、無条件に自分の存在を受け入れてくれる「安全基地」の存在である。親には、成果に関してはどんな結果であっても受け入れる一方で、挑戦したプロセスを認めることが求められる。たとえば、子どものテストの結果が良かったとしよう。その際は、点数だけに着目するのはNGだ。「週末によく勉強していたからだね、頑張ったね」などと、プロセスに着目した声かけが望ましい。
子どもを「ちょっと前の子ども」と比べよう
子どもとの関わりで避けたほうがいいのは、我が子を他の子どもと比べることだ。子どもは周囲と比べられると、自分の努力よりも、周囲の客観的な評価ばかり気にするようになる。何かを達成したときには、自分が成長している実感を得られる。にもかかわらず、比較によって委縮してしまうのは、もったいない。
子どもを評価するときには、「以前のその子と比べる」のがよい。誕生日、年末などの節目で、子どもを一年前と比べてみると、その子のさまざまな成長に気づける。「だいぶ〇〇ができるようになったね!」という伝え方なら、うまく子どもをほめられるため、子どもを叱りがちな親御さんにおすすめである。
「大人も失敗する」ことを教える
そもそも子どもがチャレンジしなくなった背景には、大人の失敗経験が減り、寛容さが減ったことがあるのではないか。そう著者は推察している。いまや、何をするにしても、その場で効率のいい方法や他者の評価を調べられる。そのため、失敗して恥をかいたり、周囲に迷惑をかけたりする機会が少なくなっている。親も子どもに失敗をさせて恥をかきたくないため、先回りして手を打つことが増えた。その結果、子どもが挑戦を恐れるようになったと考えられる。