「カッコいい」とは何か

「カッコいい」とは何か
著者
著者
平野 啓一郎 (ひらの けいいちろう)
1975年愛知県生まれ。北九州市で育つ。京都大学法学部卒。大学在学中に文芸誌「新潮」に投稿した『日蝕』により第120回芥川賞を受賞。以後、数々の作品を発表し、各国で翻訳紹介されている。著書は『一月物語』、『葬送』、『滴り落ちる時計たちの波紋』、『決壊』(芸術選奨文部科学大臣新人賞)、『ドーン』(ドゥマゴ文学賞)、『空白を満たしなさい』、『モノローグ(エッセイ集)』、『ディアローグ(対談集)』、新書『本の読み方―スローリーディングの実践』、『私とは何か 「個人」から「分人」へ』など。
1975年愛知県生まれ。北九州市で育つ。京都大学法学部卒。大学在学中に文芸誌「新潮」に投稿した『日蝕』により第120回芥川賞を受賞。以後、数々の作品を発表し、各国で翻訳紹介されている。著書は『一月物語』、『葬送』、『滴り落ちる時計たちの波紋』、『決壊』(芸術選奨文部科学大臣新人賞)、『ドーン』(ドゥマゴ文学賞)、『空白を満たしなさい』、『モノローグ(エッセイ集)』、『ディアローグ(対談集)』、新書『本の読み方―スローリーディングの実践』、『私とは何か 「個人」から「分人」へ』など。
本書の要点
- 要点1何を「カッコいい」と見なすかの基準は、「しびれる」という自らの“体感”にもとづいている。ゆえに何をもって「カッコいい」とするかは人それぞれである。
- 要点2「カッコいい」は外見だけでなく内面にも関わる価値観であり、だからこそ「カッコ悪い」と思われることを私たちは恐れる。
- 要点3「カッコいい」という価値観は一見すると個人主義的かつ民主主義的だが、国家権力や宗教に悪用される危険性もはらんでいる。
- 要点4「カッコいい」について考えることは、そのまま自らの「生き方」を考えるということだ。
要約
【必読ポイント!】 「カッコいい」は“体感主義”である
語源は「恰好」にあり

takraw/gettyimages
「カッコいい」という言葉は、戦前の楽隊や軍隊で使われ始めた。そして1960年代のロック・ブームをきっかけに、人口に膾炙(かいしゃ)した。とはいえ「カッコいい」という日本語が、この時期に突然生まれたわけではない。その語源は「恰好(格好)」と考えるのが妥当である。
日本語学者の小野正弘によると、「恰好」という言葉が日本で使われるようになったのは中世後期だった。ただしそのときの意味は、「あるものとあるものとがうまく調和する・対応する」というものだった。これは今日でも「この議論をする上では、恰好の事例だ」といった用法に見ることができるが、この言葉は近世初期に至るまで、ほとんど一般的に使われていなかった。
近世中期になると「恰好」はさまざまな文献で見られるようになり、原義に加えて「全体的な見栄え・様子」(=外観)を意味する言葉として用いられるようになる。「恰好が良い」、「恰好が悪い」という言葉が随所で使われるようになり、「格好」という表記もこの時期に出てきた。この漢字の変化については、「恰」のもつ「さながら、まるで」というニュアンスの薄れとも関係しているのだろう。「不格好」「背格好」「年格好」といった複合語も生まれ、今日に至っている。
「恰好が良い」と「カッコいい」の違い
私たちが「恰好(格好)が良い」というとき、それは単に見栄えを指すとはかぎらない。そこには「あるべき理想像に合致しているかどうか」という価値基準がある。するとひとつの疑問が浮かぶ。絶対的に「恰好が良い」というのはありえるのか。もしありえるとすると、それを判断するのは誰になるのか。
結論から述べると、江戸時代や明治時代において「恰好が良い」という表現が用いられたとき、そこにはジャンルごとの理想像があり、そのジャンルの知識や経験が豊富な人の判断ほど重要視された。そしてその判断基準を理解するためには、「達人」との直接的な対人関係を通じて経験を積まなければならないとされた。その基準はあくまでも厳格だった。
ところが「カッコいい」という言葉の場合、マスメディアの隆盛によって、より開かれた場で用いられてきたという経緯がある。さらには第二次世界大戦後という事情も重なった。総動員体制から解放された日本人たちは、画一的な上からの押しつけではなく、別の基準を求めるようになった。ゆえに「カッコいい」の基準は「恰好が良い」よりも緩やかだ。スポーツカーとカラーテレビ、ネイマールとEXILE、エルメスの「バーキン」と困っている人をさりげなく助けること(!)は、すべて「カッコいい」に分類されうる。そしてそのなかで何が一番かを比較することも可能になる。
そういう意味で「カッコいい」は、「恰好が良い」から直接に派生した言葉とは言えない。なによりも「カッコいい」にあって、「恰好が良い」にはない意味合いがある。それは生理的興奮としての「しびれ」である。
「しびれる」という“体感”
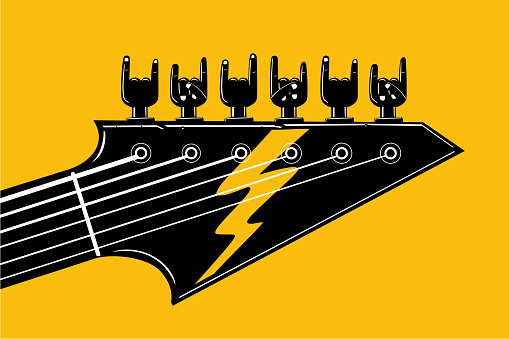
ne2pi/gettyimages
「しびれる」という体感は、「カッコいい」にあって「恰好が良い」にないものである。それは非日常的な興奮だ。私たちは「カッコいい」ものに憧れ、夢中になる。体が自然と反応したものに対して、反論することは難しいからだ。

この続きを見るには...
残り3053/4408文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2019.07.16
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は株式会社フライヤーに帰属し、事前に株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
一緒に読まれている要約











