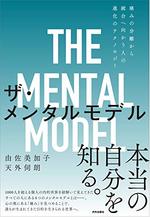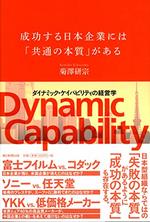教え学ぶ技術
問いをいかに編集するのか

著者
苅谷 剛彦 (かりや たけひこ)
1955年生まれ。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。ノースウェスタン大学大学院博士課程修了、Ph.D(社会学)取得。東京大学大学院教育学研究科教授を経て、オックスフォード大学教授。専攻は社会学、現代日本社会論。著書に『知的複眼思考法』(講談社+α文庫)『大衆教育社会のゆくえ』『教育と平等』(中公新書)などがある。
石澤 麻子 (いしざわ あさこ)
1989年生まれ。国際基督教大学(文化人類学専攻)卒。オックスフォード大学大学院現代日本研究修士課程修了。帰国後、コンサルティング会社に入社。退職後、フリーで記事の翻訳、執筆を中心に活動。
1955年生まれ。東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。ノースウェスタン大学大学院博士課程修了、Ph.D(社会学)取得。東京大学大学院教育学研究科教授を経て、オックスフォード大学教授。専攻は社会学、現代日本社会論。著書に『知的複眼思考法』(講談社+α文庫)『大衆教育社会のゆくえ』『教育と平等』(中公新書)などがある。
石澤 麻子 (いしざわ あさこ)
1989年生まれ。国際基督教大学(文化人類学専攻)卒。オックスフォード大学大学院現代日本研究修士課程修了。帰国後、コンサルティング会社に入社。退職後、フリーで記事の翻訳、執筆を中心に活動。
本書の要点
- 要点1生産的な議論をするための思考力を鍛えるには、「問いを編集する」技術が必要になる。
- 要点2エッセイを通じて学生の思考過程を想像しつつ、より論理的に考える方法を教えるのが、オックスフォードの「チュートリアル」におけるもっとも基本的なやり方だ。
- 要点3知的なキャッチボールを通して、学生の関心領域からカギとなる言葉や視点を引き出し、問いを発展させるのが教師に求められる技術=アートである。
要約
議論をする力を養うためには
「問いを編集する」技術

Melpomenem/gettyimages
議論が噛み合うことで、新たな認識が生まれ、自分の見方が相対化される。そしてより広い視野に立った議論ができるようになる――これが理想的な議論のあり方だ。しかし実際は、賛否両論の意見が飛び交って「炎上」し、互いの主張をぶつけ合うだけで、議論が噛み合わないことが多い。逆に顔見知り同士だと「空気を読む」ことが期待され、議論が発展しないということもままある。これらの事象は両極端のように見えるが、議論の捉え方と進め方に問題があるという点では共通している。
人とは異なる考えをうまく伝えたり、なれ合いになりがちな議論の場で自分の考えを明確に示したりするのに必要なのが、「問いを編集する」という技術だ。議論が噛み合わない原因のひとつは、互いの問いにすれ違いが生じていることにある。問いが共有されず、ずれが認識されないままでは、いくら意見を言い合っても議論は平行線のままだ。重要なのは、問いをどこまで明確に意識するかである。
「問いを使いこなす」技術
議論(argument)をするとき、私たちはあるテーマ (主題)について考える。そして日常会話と違い、議論においてはなんらかの発展や展開が期待される。では、あるテーマにアプローチするとき、どのように切り込んでいけばいいのか。どうやって自分の見解や意見を考え、まとめていくべきなのか。
自分なりに問いを立て、その問いに答えようとすることで、考えを展開していく。それが「問い」からのアプローチである。あるテーマについて賛成か反対か、具体的な例証はなにか、他のことばで言い換えるとどうなるのか、どんなことに例えられるのか……このように問いを立てていくことで、多角的な視点から物事をとらえ、複雑で高度な議論への足がかりをつくることができる。
これは大学の小論文や卒業論文を書くときにだけ必要な技術ではない。社会に出てからも、私たちはさまざまな問題や課題(problem)に直面し、そのたびに解答が求められる。そのときも問いとして課題をとらえ直し、問いへの答えを考えることで、適切な解決策を導くことが可能になる。コミュニケーションが不毛になるような状況を打開するのにも、問いへの自覚がカギとなるのだ。
「批判的な思考」を育てる

SIphotography/gettyimages
どのように問いを立てるか、立てた問いをどのように展開していけばよいかという「思考の技術」を学ぶ機会は、残念ながら日本の教育に十分に備わっているようには見えない。「探究学習」や「アクティブ・ラーニング」のような新しい学習法も奨励されているが、そもそも教える側にそのような思考や教える技術が十分に備わっているとは限らないのだ。
他方で著者の苅谷氏が在籍するオックスフォード大学では、「チュートリアル」(大学院の場合は「スーパービジョン」)と呼ばれる学生への個人指導が行われている。週に1回1時間、学生1人~3人に対し1人の教員がついて、小論文を書くための問い(エッセイ・クエスチョン)と、読むべき課題文献(毎週10冊ほど)のリストが渡される。学生は小論文を執筆し、それを元に教員との間で質疑応答や議論が行われる。こういった読み書きを中心とした個別学習を通じて、「批判的な思考」を育てるのである。
問いの立て方と思考法
エッセイを元にした指導
ここからは苅谷氏が「先生」役に、石澤氏が「学生」役になり、実際にチュートリアルを行なっていく。

この続きを見るには...
残り2010/3418文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2019.11.03
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約