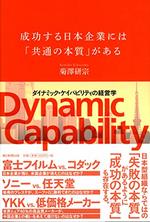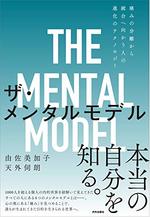本業転換
既存事業に縛られた会社に未来はあるか
著者
山田 英夫 (やまだ ひでお)
1955年東京都生まれ。早稲田大学大学院経営管理研究科(ビジネススクール)教授。慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了(MBA)。三菱総合研究所にて大企業の新事業開発のコンサルティングに従事。1989年早稲田大学に転じ、現職。専門は競争戦略論、ビジネスモデル。博士(学術、早稲田大学)。ふくおかフィナンシャルグループ、サントリーホールディングスの社外監査役。主な著書に、『異業種に学ぶビジネスモデル』『競争しない競争戦略』『ビジネス版 悪魔の辞典』以上:日本経済新聞出版社、『成功企業に潜むビジネスモデルのルール』ダイヤモンド社、『マルチプル・ワーカー「複業」の時代』三笠書房、『ビジネス・フレームワークの落とし穴』光文社、など。
手嶋 友希 (てじま ゆき)
1980年東京都生まれ。大学卒業後、大手金融会社に勤務。企業派遣生として、2019年3月早稲田大学大学院経営管理研究科(ビジネススクール)修了(MBA)。
現在、企業営業向けの企画立案等を行う業務に従事。
1955年東京都生まれ。早稲田大学大学院経営管理研究科(ビジネススクール)教授。慶應義塾大学大学院経営管理研究科修了(MBA)。三菱総合研究所にて大企業の新事業開発のコンサルティングに従事。1989年早稲田大学に転じ、現職。専門は競争戦略論、ビジネスモデル。博士(学術、早稲田大学)。ふくおかフィナンシャルグループ、サントリーホールディングスの社外監査役。主な著書に、『異業種に学ぶビジネスモデル』『競争しない競争戦略』『ビジネス版 悪魔の辞典』以上:日本経済新聞出版社、『成功企業に潜むビジネスモデルのルール』ダイヤモンド社、『マルチプル・ワーカー「複業」の時代』三笠書房、『ビジネス・フレームワークの落とし穴』光文社、など。
手嶋 友希 (てじま ゆき)
1980年東京都生まれ。大学卒業後、大手金融会社に勤務。企業派遣生として、2019年3月早稲田大学大学院経営管理研究科(ビジネススクール)修了(MBA)。
現在、企業営業向けの企画立案等を行う業務に従事。
本書の要点
- 要点1衰退する本業に代わる事業を考える際、「どの事業を選ぶか(What)」と「新事業の開始時期(When)」という2つの視点が重要になる。
- 要点2社内においては、事業の衰退を感じ取ることすら難しい。「後退は一時的なもの」といった楽観論が好まれるからだ。しかしそのような既存事業に縛られた企業に未来はない。
- 要点3重要なのはWhenである。組織の柔軟性が残っており、キャッシュフローが潤沢な成熟期にこそ、本業転換の準備を始めるべきだ。衰退期に入ってから動いたのでは、選択肢は限られてしまう。
要約
本業の転換
転換と衰退

Eoneren/gettyimages
製品や事業にライフサイクルがある以上、本業が衰退してしまう現象は、どの時代にも、どの企業にも起こりうる。
本業衰退のきっかけは、フィルム業界のようにアナログからデジタルという技術の変化であったり、グローバル化であったり、規制緩和であったり、さまざまだ。たとえば自動車の自動運転が実現すれば、自動車業界にとどまらず保険業や物流業にも大きな影響を与えることが、容易に想像される。
本書の目的は、同じ業界に位置していた競合企業のうち、本業の転換に成功した企業と、変化に対応できず倒産・解体されてしまった企業の戦略を比較することによって、本業転換のポイントをあぶり出すことである。
具体例として取り上げられているのは、(1)富士フイルムとイーストマン・コダック、(2)ブラザー工業とシルバー精工、(3)日清紡とカネボウ、(4)JVCケンウッドと山水電気、という4つのペアだ。いずれにおいても、前者が成功した企業であり、後者が消失した企業である。
WhatとWhen
ブラザー工業は編機、タイプライターという2度の本業衰退に直面したが、粘りの戦略でこれを克服した。紡績を創業とする日清紡は、現在ではブレーキ、エレクトロニクスがコアとなっている。JVCケンウッドは高級チューナーから、無線機、オーディオ、カーナビと舵を切り続けた。
こうした企業の生き残り戦略を整理すると、本業に代わる事業として「どの事業を選ぶか(What)」と、「新事業の開始時期(When)」という2つの視点があることがわかる。本業に代わる新たな収益源として、自社の技術やノウハウを生かすことのできる分野を選定したこと(What)、本業から得られるキャッシュフローがまだ十分にあり、企業体力のある時期に新しい事業を開始したこと(When)が、存続企業の共通点だったのだ。
一方で衰退企業では、本業に代わる新たな事業として何をやるべきか、何をやるべきでないかという事業選択がうまくできていなかった。また戦略を実行に移す時期が遅すぎた。つまりWhatとWhenのいずれかにつまずいたか、もしくはその両方につまずいていた。
What(どの事業を選ぶか)
関連領域と非関連領域

ojogabonitoo/gettyimages
一般的には本業と関連の高い領域への転換のほうが、成功確率は高いと言われている。ただしその関連性を考えるうえでは、ふたつの注意点がある。それは「遠そうで近いもの」と、「近そうで遠いもの」があるということだ。
富士フイルムの化粧品・医薬品への進出、日清紡のブレーキへの進出は、リスクが高いと言われる非関連多角化である。しかし両事業は軌道に乗っている。これらは業種的に見ると非関連分野になるが、コア・テクノロジーは本業で培ったものを応用できるため、技術面での関連が高いと考えられる。一見すると遠そうだが、根っこは比較的近かったのである。
逆に関連した領域なのにうまくいかなかった例として、LCC(格安航空会社)の運営に手を染めた米国コンチネンタル航空、ジェネリック薬品の会社を設立し黒字化したものの、最終的には手放してしまったエーザイなどが挙げられる。領域としてはまさに隣合わせなのに、基幹のところが離れていたのである。
評価尺度と体内時計
このように領域の関連性だけで、多角化の成否を論じることは難しい。そこには「評価尺度」と「体内時計」の違いがある。

この続きを見るには...
残り2740/4125文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2019.11.08
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約