風姿花伝 創造とイノベーション
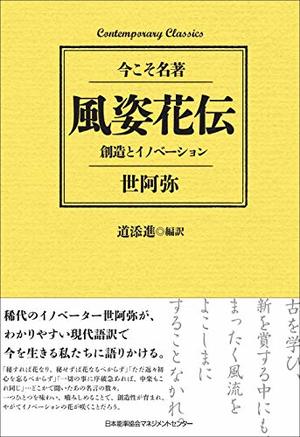
風姿花伝 創造とイノベーション
著者
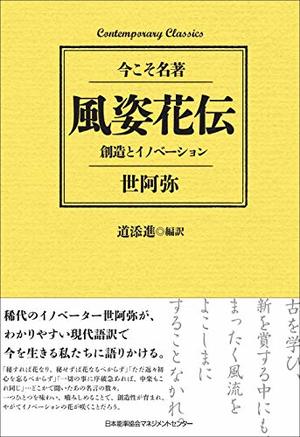
著者
道添 進(みちぞえ すすむ)
1958年生。文筆家、コピーライター。国内デザイン会社を経て、1983年から1992年まで米国の広告制作会社に勤務。帰国後、各国企業のブランド活動をテーマにした取材執筆をはじめ、大学案内等の制作に携わる。企業広報誌『學思』(日本能率協会マネジメントセンター)では、全国各地の藩校や私塾および世界各国の教育事情を取材し、江戸時代から現代に通じる教育、また世界と日本における人材教育、人づくりのあり方や比較研究など幅広い分野で活動を続けている。著書に『ブランド・デザイン』『企画書は見た目で勝負』(美術出版社)などがある。本シリーズでは『論語と算盤 モラルと起業家精神』『代表的日本人 徳のある生きかた』『学問のすすめ 独立するということ』に続いて編訳。
1958年生。文筆家、コピーライター。国内デザイン会社を経て、1983年から1992年まで米国の広告制作会社に勤務。帰国後、各国企業のブランド活動をテーマにした取材執筆をはじめ、大学案内等の制作に携わる。企業広報誌『學思』(日本能率協会マネジメントセンター)では、全国各地の藩校や私塾および世界各国の教育事情を取材し、江戸時代から現代に通じる教育、また世界と日本における人材教育、人づくりのあり方や比較研究など幅広い分野で活動を続けている。著書に『ブランド・デザイン』『企画書は見た目で勝負』(美術出版社)などがある。本シリーズでは『論語と算盤 モラルと起業家精神』『代表的日本人 徳のある生きかた』『学問のすすめ 独立するということ』に続いて編訳。
本書の要点
- 要点1『風姿花伝』は、世界最古の演劇論でありながら、ビジネス書としても読むことができる。
- 要点2能の命は「花」にある。若い役者は新鮮さから「時分の花」を咲かせ、時には名人に勝つこともあるが、それは一時的なものに過ぎない。散ることのない誠の花を咲かせることが大切である。
- 要点3花があるということを人に隠せば、それが花になる。秘伝の内容だけでなく、それが存在していることすら、観客に悟らせてはならない。
要約
世阿弥と『風姿花伝』
世界最古のビジネス書としての『風姿花伝』

cruphoto/gettyimages
『風姿花伝』は、世阿弥(ぜあみ)によってたった一人の跡継ぎのために記された秘伝書だ。その性質上、明治期に入るまで、一般の人の目に触れることはなかった。
世阿弥は室町時代の能役者で、父の観阿弥(かんあみ)とともに現代の能を完成させた人物だ。『風姿花伝』は、そんな世阿弥の能芸人生の絶頂期に書かれた。芸術にふれる際の目のつけどころだけではなく、組織運営や人材育成のヒントなどを読み取ることもできるだろう。
世阿弥が活躍した室町時代の前期から中頃にかけては、新しいエンターテインメントが生まれつつある時代だった。それまで貴族のためのものだった芸能は、庶民たちが入場料を払って観るものとなった。神社やお寺の行事の一環として行われていた猿楽(さるがく)は、村落共同体の行事から、都市型の商業的興業へとシフトしていった。
そこは、地縁や既得権ではなく人気が物を言う世界であった。庶民から喝采を浴びた人物は、やがて貴族や将軍の目に止まり、さらなる活躍を約束されるようになったのだ。
そんな時代背景にあって、世阿弥は、能をより多くの人に届けるためのマーケティングを行うとともに、20歳そこそこの若さで一座を統率し経営した。そして、世界最古の演劇論にして世界最古のビジネス書と言われる『風姿花伝』を書き残した。
名声と弾圧
世阿弥は1363年、伊賀国(三重県)で生まれた。父は天才肌の役者と称賛されていた観阿弥だ。世阿弥は12歳の頃、将軍足利義満によって見出され、寵愛を受けた。
36歳の時、京都で将軍足利義満が臨席する中、3日間に渡る興行を成功させたのが、世阿弥の青年期から壮年期にかけてのハイライトである。そして翌年、『風姿花伝』を書き始めた。
世阿弥が45歳の時、パトロンであった義満が亡くなると、義持の時代となった。義持は世阿弥のライバルを好んだため、世阿弥は危機感を抱いてますます芸に邁進した。60歳になると出家し、長男に後を継がせたが、演技や指導は続けていた。
義持が亡くなり義教の時代になると、世阿弥父子を取り巻く環境は大きく暗転する。義教によって佐渡へ島流しにされたのは、世阿弥が72歳の時だった。
佐渡で10年を過ごした後、世阿弥は京の都へ帰る。没したのは1443年頃だと言われているが、それもさだかではない。佐渡に渡った以降の世阿弥については、はっきりとわかっていないのだ。
序
能を極めるための心得

Gilmanshin/gettyimages
『風姿花伝』は序に続く7つの巻からなる。要約では序、第1巻、第3巻、第5巻、第7巻の巻の中から、いくつかのポイントを取り上げて紹介する。
能を学ぶ際にはまず、昔ながらの伝統を知らなければならない。そして、新しい能を鑑賞する際にも、芸能の本質とも言える風流さがあるかどうかを見極める必要がある。言葉遣いに品格があり、姿形に幽玄(ゆうげん)さをまとった演技ができてこそ、一流だといえよう。
能の道を極めようとするなら、他の芸能に手を出さず、能にだけ集中しなければならない。だが、和歌だけは別だ。和歌は、能の原形である猿楽と同様、自然の風景を愛で、長寿を願う芸能である。だから能を目指す者は、和歌を積極的に学ぶとよい。
能を習得するうえで肝心なことがらは、2つある。まず、好色、博打、酒に溺れることを三大悪と心得ること。そして、驕(おご)り高ぶって自己流に固執することなく、稽古に一心に打ち込むことである。
第一巻
それぞれの年代で学ぶべきこと
能の稽古は、7歳ぐらいから始めるのがならわしになっている。子どもなりにあれこれとやり出したら、その子の好きなようにやらせてみよう。あまり口うるさく指図すると、子どもはみるみるやる気を失い、芸の上達が止まってしまう。この年頃の子には、舞い、能の動き、謡いといった基本的な稽古でじゅうぶんだ。
12、3歳くらいの年頃の子どもは何をやっても愛らしく、声も際立って美しいため、華やかに映える。けれども、この花は、本物の花ではなく、この年代だからこそ咲かせられる「時分の花」にすぎない。この年頃の稽古は、基本の技能を習得することを大事にし、そのうえで本人がやりやすい得意なものを「花」とすべきだ。
17、8歳になると、声変わりを経験し、身長も伸びて子どもらしさがなくなる。だからこの年頃を迎えたら、笑われようとも気にしないよう導いてやることだ。
24、5歳の頃には、若々しい芸が花開き、世間に注目される者もでてくる。役者自身もついその気になって、慢心してしまうこともある。だが、この年頃の演技は花とは言えない。ただ若々しさをもてはやされているだけだ。たとえ人に褒(ほ)めそやされ、名人に競って勝っても、それは今だけ咲いためずらしい花のせいだと自覚させるべきである。
役者として腕を上げていくのは34、5歳の頃までで、この頃になってもまだ世の中から認められていないのなら、自分が能を極めた役者だと思ってはならない。そして44、5歳の頃には、身に咲く「花」も、舞台における「花」も衰えていく。脇の役者の引き立て役として、控えめに演じるよう心がけるべきだ。
50歳以上になると、能の役者としては変化のしようもない。だが、真に能を習得した達人なら、老いても花だけは散らずに残るものである。
第三巻
ライバルに勝つためには

kentoh/gettyimages
役者が競演して芸の優劣を競う「立ち会い」で勝つためには、演目のレパートリーをたくさん用意して、相手とはまったく異なる能を演じられるようにしておくとよいだろう。特に、意のままに演じられる自作の能が望ましい。和歌の才能を兼ね備えていれば、自作できるはずだ。どれほど達者な役者であっても、自ら創作した作品を持っていない者は話にならない。
相手が華やかな能を演じたら、こちらは静かな演技で勝負する。そうすれば、相手が上出来であっても負けないし、こちらが上手にできれば、自分の勝利は揺るぎないものとなる。
勝負を分ける「花」
名人であっても、若い役者との立ち会い勝負に敗れてしまうことがある。それは、まさに「時分の花」がなせるわざである。新鮮味が感じられなくなった役者に真新しい花が挑戦すると、若いほうが勝ってしまうこともありえるのだ。
どれほど銘木であろうとも、花が咲いていない木は見向きもされない。一重のありふえた桜であっても、新しい花が咲き誇っているとしたら、観客はそちらに目を奪われてしまうだろう。
能の命は「花」にある。花がすでに失われてしまったことに気づかないで、かつての名声ばかりを頼みにする古参役者は、まったく残念としか言いようがない。
舞台の見せ方を工夫できる役者なら、技術は劣っていたとしても、花は残るだろう。花さえ残っていれば、観客を惹きつけられるものだ。散ることのない誠の花を咲かせることが大切である。
【必読ポイント!】第五巻
芸の神髄としての花
能の作風や演技の様式は、それぞれの流派で異なる。だが、観客を楽しませる要素はどんな能にも共通だ。だからそれらを醸成する花を持っている役者なら、天下に認められ、名声を得ないはずはない。
たくさんの芸ができるわけでなくても、10あるうちの7つ、8つを極めた役者がいるとする。そして、その中でもとりわけ得意な能を、自分の一座を代表する演目になるまで磨き続けたとしよう。この演技にさらなる工夫を重ねていったなら、この役者はおそらく、京の都において天下の名声を得ることができるに違いない。
すべての人を楽しませるためには
芸能は、人の心を和ませ、身分の上下にかかわらず皆が一体となれる感動を生み出し、人々に幸福をもたらすものだ。
上流の人々が観るのならば、芸を極めた役者の演技がぴったりだろう。上流の人々は、レベルが高い演技であってもすんなりと理解できるものだ。
一方で、鑑識眼が備わっていない観客もいる。例えば京の都から遠く離れた地方や、身分の低い人々は、どうしてもレベルの高い演技についていけないことがある。
だから、あまりに高尚な芸風ばかりに固執していては、広くさまざまな観客を喜ばせ、幸福に導くことはできない。能の初心を忘れることなく、時と場所に応じ、芸の良しあしがわからない観客をも感動させる能を見せてこそ一流だ。
第7巻
散るからこそ、新鮮な花

borchee/gettyimages
花は、四季の折々で咲くものだ。そのときどきに新鮮な感動を呼び覚ますから、私たちは花を愛するのだろう。
猿楽も花と同じだ。観客が演技に新鮮な魅力を感じることが、おもしろいという感覚に繋がるのである。花を愛でる気持ちと、おもしろいと思う心と、新鮮な感動とは、どれも同じ心から発するものだ。
散らずにずっと咲き続ける花などない。能もまた、習得した芸を磨き続け、折々の流行を心得た上で、当日の観客の好みそうな演目を披露すれば、新鮮な感動を呼び起こすことができる。花というのは、観客にとって新鮮に感じられるものだけが花なのである。
秘すれば花
秘して隠すことによって花になる――これはどういうことか。それは、花があることを人に隠せば、それが花になるということだ。秘密にしないことには、花になりえない。
あらゆる芸事には、秘伝と言われるものがある。これは、秘密にしているからこそ効用を発揮するのだ。この花の口伝をあらかじめ皆が読んで、観客が「なるほど、新鮮であることが花を演出する元になるものか」と知っていたらどうだろうか。観客は「さては、どこかで真新しいものを見せるにちがいない」というふうに期待して能を観ることになる。これでは観客を感動させることはできない。
そうではなく、「ほう、思いのほかおもしろい演技をする。上手な役者ではないか」と、自然に感動させなければならない。見る者にことさら意識させず、思いがけない感動をもたらすのが、役者にとっての花なのだ。
秘事は、内容さえ知られなければいいというわけではない。その秘事を自分が知っているということすら、観客に悟られてはならないものだ。だから、わが観世家の秘伝として、秘事が存在することそのものは絶対に口外してはならない。この秘事が、生涯に渡って能の花の主になるための手立てなのである。

この続きを見るには...
残り0/4127文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2019.11.28
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











