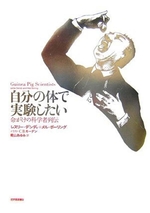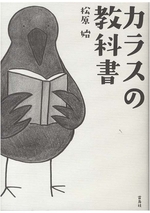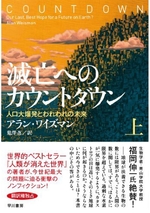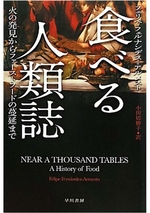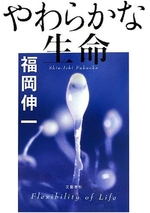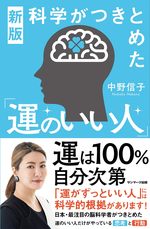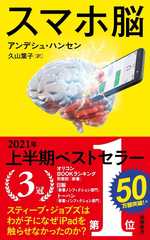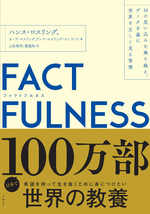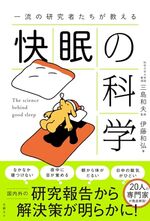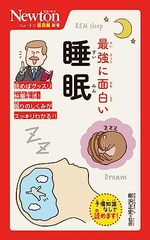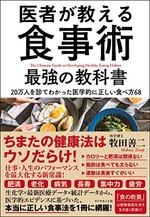太陽エネルギーの獲得と食物連鎖
太陽エネルギーを取り込んだ有機物を、スクラップ・アンド・ビルドしながら生きている
原核生物の誕生、真核生物の誕生、さらに多細胞生物が獲得した移動性など、地球46億年の歴史の中で生物は多様性を維持しながら生存してきた。地球が氷で覆われる前は、シアノバクテリアや藻類のような太陽の光からエネルギーをつくり出す光合成を行う独立栄養生物のプランクトンが繁殖していた。
ところが、氷河期になり、これら光合成を行うプランクトンに十分に太陽光が当たらなくなり、浮遊性の栄養源が乏しくなるという事態が起こった。その結果、移動性をもつ多細胞生物が、栄養源となる堆積物の上を這い回ることで、エネルギーを効率よく獲得できるようになったと考えられている。
多細胞生物は移動のために「骨格」をそなえることで、より速く動けるようになった。食物連鎖の視点でみると、原核生物である光合成細菌やシアノバクテリア、真核生物である植物は、太陽エネルギーを光合成という形で取得する独立栄養生物である。それに対して、これを食べて生命を維持する従属栄養生物は消費者にあたる。従属栄養生物は、植物をおもな餌とする草食動物と、草食動物を食べる肉食動物、肉食動物を食べる肉食動物などに分けられる。
すべての生物が食べては分解し、細胞で吸収し栄養としているものは有機物である。有機物は、食物連鎖の始まりにおいて、太陽光を使った光合成により作られている。つまり『動物は、植物を取り込んでも動物を取り込んでも、もともとは太陽から降り注いだエネルギーを利用して合成された各種有機物を、スクラップ・アンド・ビルドしながら利用している』と言えるのだ。
「食う食われる」個体から環境変化に適応できる個体群へ
環境変化に適応した効率的な情報戦略をもった生物が生き残る
それぞれの集団や種が、他とどのような関連をもっているかといった視点を中心にした学問が「生態学」だ。生態学は生物の相互作用の研究であると定義されてはいるものの、著者は『空間と物質(個体も含む)とエネルギーの経済学的モデルである』ことが多いと感じているという。
個体群の単位空間あたりの個体数は個体群密度といい、外的要因によって変動する。ひとつ例を出してみよう。バッタは大量発生すると、その個体間の密度が集団に影響を及ぼし、相変異を起こすのだ。