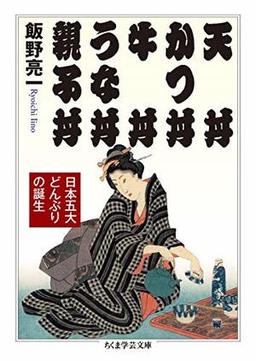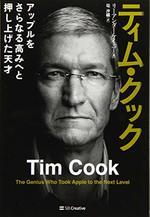【必読ポイント!】 鰻丼の誕生
鰻飯というアイディア

江戸時代の人は、ヌルヌルとしてつかみどころのないウナギをつかんで裂き、美味しい蒲焼きにすることに成功した。ただ、蒲焼きは主に酒の肴として食べられており、客層が限られてしまうため、うなぎ屋はご飯をつけて出すことを思いついた。
そして、蒲焼きとご飯を一緒に盛り合わせた「鰻飯」が考案されると、蒲焼きにはない魅力から、人気食となっていった。鰻飯の始まりについては、宮川政運(まさやす)の「俗事百工起原(ぞくじひゃっこうきげん)」で言及されている。それによると、文化年間(1804〜18)に、堺町の芝居小屋、中村座のスポンサーのような役割をしていた大久保今助という鰻好きの男がいた。大久保が、蒲焼きが冷めないようにと、丼の飯の間に挟ませて芝居小屋に届けさせていたのが鰻飯の起源だという。風味がよいのでみんなが真似をするようになり、他の店でも出すようになったそうだ。
こうして文化年間に鰻飯が売り出されたが、大久保以前に同じような工夫をしている人がいたことが過去の文献からはわかっている。したがって、大久保今助は鰻飯が売り出されるきっかけを作った人ではあるが、鰻飯を最初に工夫した人、とはいえないようだ。
鰻飯から鰻丼へ
鰻飯はふた付きの丼で出されていた。保温するには食器にふたをすることが望ましいからだが、その結果、鰻飯は蒲焼きにはない演出効果をもたらし、江戸っ子の食欲をそそった。
江戸時代の蒲焼きはタレを付けて焼き上げた地焼きだったが、明治時代になると焼く過程で蒸す方法が取り入れられ、大正時代には蒸す技術が確立された。そうすると、飯の間に蒲焼きを挟むと二重に蒸すことになるので、東京では中入れタイプの鰻飯は姿を消し、現在のようにウナギはご飯の上に乗るようになった。
明治時代になると、鰻飯は鰻丼(うなぎどんぶり)とも呼ばれるようになり、そしてまもなく鰻丼(うなどん)と略称され、名が定着した。さらにはウナギが丼だけではなく重箱に盛りつけられるようになると、うな重と呼ばれ、鰻丼よりも見栄えが良いことから鰻丼の人気をしのぐようになっていった。
天丼の誕生
天麩羅蕎麦、天麩羅茶漬の登場
天麩羅はそもそも、屋台で売り始められ、江戸っ子はそれを立ち食いしていたという。
やがて江戸っ子は蕎麦屋の屋台で蕎麦を買い、それに好みの天麩羅をトッピングして、天麩羅蕎麦として食べるようになった。揚げたての天麩羅を蕎麦に合わせれば、天麩羅には蕎麦のつゆがしみ、蕎麦には天麩羅のうま味が加わる。江戸っ子のアイディアから生まれたこの方法に蕎麦屋が注目し、蕎麦屋のメニューに天麩羅蕎麦が登場するようになった。
蕎麦屋に次いで天麩羅をメニューに加えるようになったのは、茶漬店だった。天麩羅の屋台が出現した安永年間(1772〜81)には茶漬店も現れており、江戸っ子が小腹を満たしていた。嘉永年間(1848〜54)ごろになると、天麩羅茶漬店が生まれた。
淡泊な味のものを食べていた江戸時代の人々にとっては、天麩羅は油っこくて異質だったため、屋台では天麩羅に大根おろしがサービスされていた。この大根おろしの役割を担ったのが、茶漬の茶だった。天麩羅茶漬店は繁盛し、やがて明治時代に天麩羅専門店が生まれてからも、天麩羅茶漬は食べられていた。
屋台の食べ物だった天麩羅は、こうして、茶漬店の座敷へ、そして天麩羅専門店の座敷へ上っていった。
天丼の普及

明治時代になって現れた天麩羅専門店の中から、天丼という新メニューを開発した店が出てきた。
東京、神田鍛冶町の、