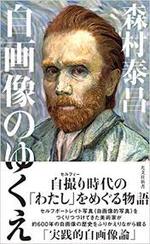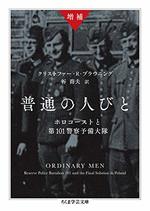コラプション
なぜ汚職は起こるのか


著者
レイ・フィスマン(Ray Fisman)
ボストン大学スレーター家「行動経済学」寄付講座教授。著書に『会社は意外と合理的』(ティム・サリバンと共著、日本経済新聞出版社)。『悪い奴ほど合理的』(エドワード・ミゲルと共著、NTT出版)。
ミリアム・A・ゴールデン(Miriam A.Golden)
カリフォルニア大学ロサンジェルス校政治学教授。コーネル大学でPh.D.を取得。ヨーロッパ、アジア、アフリカの腐敗や不正行為のフィールド研究に取り組む。現在のプロジェクトとしてパキスタンの政治における反応の実験デザインを行っている。
ボストン大学スレーター家「行動経済学」寄付講座教授。著書に『会社は意外と合理的』(ティム・サリバンと共著、日本経済新聞出版社)。『悪い奴ほど合理的』(エドワード・ミゲルと共著、NTT出版)。
ミリアム・A・ゴールデン(Miriam A.Golden)
カリフォルニア大学ロサンジェルス校政治学教授。コーネル大学でPh.D.を取得。ヨーロッパ、アジア、アフリカの腐敗や不正行為のフィールド研究に取り組む。現在のプロジェクトとしてパキスタンの政治における反応の実験デザインを行っている。
本書の要点
- 要点1汚職は「均衡」である。国や地域全体を見ると、汚職がまったく発生していないか、全員が汚職に関与するかのいずれかに均衡することがわかる。
- 要点2汚職は特定の貧困度、政治体制、文化特性などが原因で発生するのではなく、それぞれが複雑に関連して起きている。一方で、「汚職があるから特定の状況に陥っている」と言える場合もある。
- 要点3汚職を完全になくすのは至難のわざだ。だが市民の努力によって改善し続けることはできる。
要約
汚職を定義する
汚職という「均衡」

Kritchanut/gettyimages
世界人口の半分以上は、汚職が当たり前の国で暮らしている。著者は汚職を「経済効率を下げ、社会的格差を拡大し、民主主義の機能を損なうもの」と定義する。しかし汚職は、万人に直接的な害を及ぼすわけではないので、解決が難しい。
汚職はさまざまな観点で研究されてきたが、著者は経済学でいう「均衡」という切り口から捉える。規範や周囲の期待から逸脱するほど、個人にとっては「高くつく」。その結果として、まったく汚職が発生しないか、全員が汚職に関与するかのいずれかに均衡する。普段は汚職と関係ないように思える一般市民であっても、法で保証された公的サービスを当たり前に享受できるように、他の人と同じように賄賂を支払ったりする。ここには、権威と権力の格差も存在している。
汚職は社会的期待にもとづいているので、この期待をどう変えるかが、汚職をなくすカギになる。
汚職をどう不当と捉えるか
本書はとりわけ公共部門が関係する汚職に焦点を絞る。政治学者ジェイムズ・スコットの『比較政治腐敗』では、役人の行動が汚職かどうかを判断する3つの基準が提示されている。すなわち(1)公共の利益の基準、(2)世論の基準、(3)法の基準だ。この3つに反している場合は明らかに汚職と見なせる。ただしこれらのバランスをどう見るかは難しい。
違法かどうかの基準は、国際的に大きな差がなくなってきた。だが合法でも汚職と見なされる場合もある。加えて、世論や公共の利益に照らして不適切と思える行動も汚職と捉えられるが、これは地域ごとに感覚が違っていることも多い。しかもそうした汚職は、報道機関や法執行機関と完全に独立していない場合が多く、明るみに出ていないこともある。
公共部門が関わる汚職にはさまざまな種類が考えられる。役人による職権濫用は、政治家が見て見ぬふりをする、あるいは積極的に奨励するような不当な影響力が絡んでいる。民間部門の経済詐欺も、たいていは共犯の役人がいる。また合法的になされる企業への利益誘導のなかには、専門知識の必要性ではなく、きわめて個人的なつながりにもとづく結びつきも存在している。
正当な価値を追求した有権者への恩顧ではなく、党派への忠誠心を約束させることを目的とした見返りシステムは歪んでいる。そしてこれらの汚職を実現するために、たいていの場合、不正選挙が行なわれているのだ。
貧しいから汚職が起きるのか

SIphotography/gettyimages
たとえばトランスペアレンシー・インターナショナルの腐敗認識指数を見ると、貧困国や一人当たりのGDPが相対的に低い国の方が、腐敗度は高い。これは一国の中で地域ごとに比較しても同様である。汚職が起きている国や地域では、政府のリソースが教育やインフラなどに割かれないことが多く、外部の投資家もそうした状況に対して資金を投入したがらない。一方で貧しいからこそ、享受できるはずの権利を得るために賄賂を支払ったり、低い賃金を補填するために、公共部門の人たちが不正に手を染めたりしてしまう。
国や地域が裕福になると、監視システムにかかるコストを支払えるようになる。ただし富裕国であっても汚職を根絶できていないことからわかるように、反汚職運動のためには、なにかしらのシステムを導入するだけでは不十分で、大きな努力を継続することが欠かせない。
なお不祥事が目立つようになったからといって、かならずしもその地域が腐敗している証拠とは言えない。きちんと司法機関や報道が機能している表れとも考えられるからだ。
汚職の広がり
経済だけの問題ではない
「汚職は経済成長を促す」という議論がかつてあった。市場の「見えざる手」を阻害するのは政府の手だから、賄賂は無意味な規制を脇に追いやり、人々をよい状態に導くという「次善の論理」である。しかし実際のところ、汚職が一般的となっている国は、数十年にわたって経済が停滞している。

この続きを見るには...
残り2956/4547文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.01.23
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約