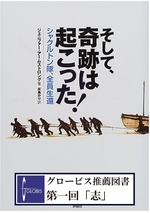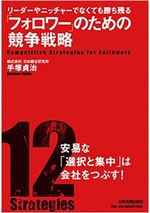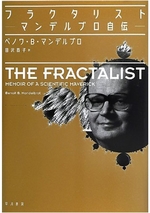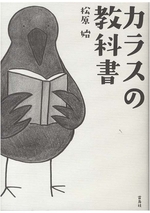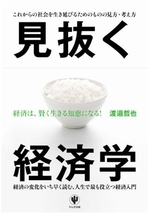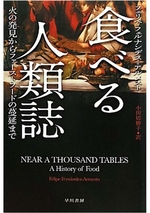独裁力
ビジネスパーソンのための権力学入門


著者
木谷哲夫(きたに てつお)
京都大学産官学連携本部イノベーション・マネジメント・サイエンス(IMS)寄附研究部門教授。1960年神戸生まれ。東京大学法学部卒、シカゴ大学政治学修士(MA)、ペンシルバニア大学ウォートンスクールMBA。マッキンゼー・アンド・カンパニーに10年間在籍し、金融機関、自動車・機械・ハイテク・通信業界における数多くの新規事業戦略立案、業務改善プロジェクトを手がける。日本興業銀行で企業金融業務、アリックス・ パートナーズで企業再建業務に従事。2007年より現職、起業家教育を担当。九州大学、龍谷大学客員教授。企業戦略、国際ビジネスについて講義している。
京都大学産官学連携本部イノベーション・マネジメント・サイエンス(IMS)寄附研究部門教授。1960年神戸生まれ。東京大学法学部卒、シカゴ大学政治学修士(MA)、ペンシルバニア大学ウォートンスクールMBA。マッキンゼー・アンド・カンパニーに10年間在籍し、金融機関、自動車・機械・ハイテク・通信業界における数多くの新規事業戦略立案、業務改善プロジェクトを手がける。日本興業銀行で企業金融業務、アリックス・ パートナーズで企業再建業務に従事。2007年より現職、起業家教育を担当。九州大学、龍谷大学客員教授。企業戦略、国際ビジネスについて講義している。
本書の要点
- 要点1自分の理想の実現には、社内の抵抗をイメージし、乗り越える方法を考える権力リテラシーが必要。従業員のレベルは高いにも関わらず、受験エリートである意思決定者の独裁力は高くない、というのが日本の平均的組織の現状。
- 要点2著者は、コア支持層はできる限り少人数に絞り、不安定な状態に置く一方で、競争力を上げるために支持基盤は社員全員をターゲットにすべきであると説く。古い滅私奉公の考え方を超える、今の時代に合致したそれぞれの大義を明確化し、新たな統合原理をつくった企業が強い時代。
- 要点3権力リテラシーとは、権力を必須の道具としてとらえる考え方であり、権力エンジニアリングとは、権力を可能な限り望ましい方向に活かすようにする方法である。日本は一体感を生みやすい文化のため、トップが独裁力を発揮しながらも社員全員がハードワークするポテンシャルがある。つまり、日本企業は、権力エンジニアリングによりグローバルビジネスの場で勝ち抜く素地を持っているのである。
要約
内なる敵を知る 独裁力を阻むイデオロギー

Kninwong/iStock/Thinkstock
反権力イデオロギーすりあわせ至上主義と強みの功罪
リーダーが自分の理念を貫こうとする場合には、様々な反独裁、反権力イデオロギーを破ることが求められる。著者はその反権力イデオロギーを4つのタイプに分けて分析している。
1つ目は「すりあわせ至上主義」。組織の意思決定がトップではなく、「すりあわせ」の専門スキルを持つ中間管理職によって担われているという点である。何をするにも「すりあわせ」が必要になるとともに、多くの部署が関わるケースが多く、結果として意思決定が異常に遅くなることが問題だ。多くの日本企業が、社内調整に時間を空費する「重たい」組織になってしまっているのである。
2つ目は、「『強みを生かす』というお題目」である。ここでは初期の段階で同等の性能を実現しながらも、競合他社にモバイルプロセッサーで抜かれてしまった日立製作所の例が挙げられる。「強みを生かす」ことで現状維持が正当化されている場合、トップが中間層に負けて組織が自己保全を図っているだけの可能性がある。特に「当グループの総力を結集する」という表現には注意が必要となる。本来プロの経営者にとっては、あくまで勝つことが目的のはずであり、強みを生かすのは手段なのだ。
組織文化と間違った権限委譲
まともな決断をするためには組織に染みついた慣性を打破する必要があるが、そこで反論に出てくるのが3つ目である、「組織文化のせいにする」イデオロギーである。社内慣習を固定的なものととらえ、変えられないものとして組織変革を拒むのである。
「日本の組織」だから東電が問題を起こしたのではなく、ベンチャー起業家であった東電の創立者の独裁力が3代目、4代目以降で失われたことが、組織退化につながったと捉えるべきだ。
4つ目は、権限委譲を「現場に丸投げ」と勘違いしてしまうことで、トップが宙に浮いてしまう「間違った権限委譲の信奉」である。日本企業では意思決定する権力が拡散してしまった結果、妥協の産物のような分厚い取り扱い説明書や、奇怪な日本商品が出来上がった。アップル商品のような、1人の意思決定者の意向が製品の細部にまで反映されている製品か、それとも多くの日本製品のように「中心がいない組織」で生み出された製品かが成否を分けている。
【必読ポイント!】権力基盤を構築する

Ingram Publishing/Thinkstock
権力メカニズムは普遍
反権力イデオロギーを打破するには、理論武装と権力の「活用」が必須である。右肩上がりの高度成長期には強い権力での意思決定が不必要であったため、従業員のレベルは高いにも関わらず、受験エリートである意思決定者の独裁力は高くない、というのが日本の平均的組織の現状である。
自分の理想の実現には、社内の抵抗をイメージし、乗り越える方法を考える権力リテラシーが必要である。まず、権力とは腹黒い独裁者だけが特別に持つものではなく、本人が努力すれば普通の人でも握れるものである。自分の権力を確かなものにするためには、確固とした支持基盤を構築し、自分の命令を組織の末端まで聞かせることが重要となる。太陽王と呼ばれたルイ14世も、自分で選んだ支持勢力を立ち上げ、古くからの勢力の権力を削ぎ、自分の権力基盤を確実なものにしていた。一見些細な、味方を作るための細かい工作を積み重ねているのである。

この続きを見るには...
残り2314/3681文字
4,000冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2014.07.15
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約