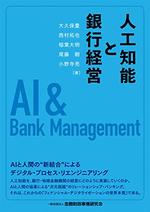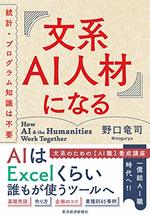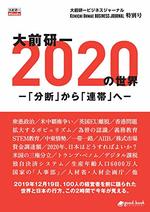2060 未来創造の白地図
人類史上最高にエキサイティングな冒険が始まる
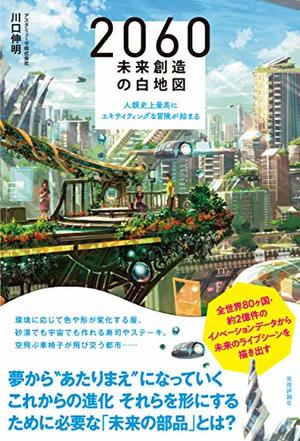
著者
川口伸明 (かわぐち のぶあき)
アスタミューゼ株式会社 テクノロジーインテリジェンス部部長。薬学博士(分子生物学・発生細胞化学)。
1959年4月、大阪生まれ。東京大学大学院薬学系研究科 後期博士課程 修了。
博士号取得直後に起業、国際会議プロデューサーなどを経て、2001年より、株式会社アイ・ピー・ビー(Intellectual Property Bank)に参画。取締役技術情報本部長、Chief Science Officerなどを歴任、世界初の知財の多変量解析システム構築、知財力と経営指標の総合評価による株式投信開発、シードベンチャーへのプリンシパル&ファンド投資、事業プロデュースなどに携わる。
2011年末、アスタミューゼ入社。広範な産業分野の技術・事業コンサルティング、約180の有望成長領域の策定、世界の研究・技術・グローバル市場(ベンチャー、上場)の定量評価手法の開発、医学会などでの招待講演、各種執筆などに奮闘中。
おもな編著書は『生体データ活用の最前線』(共著、サイエンス&テクノロジー社/2017年)、『IoTビジネス・機器開発における潜在ニーズと取り組み事例集』(共著、技術情報協会/2016年)、『実践 知的財産戦略経営』(共著、日経BPコンサルティング/2006年)、『特許四季報1・2・3』(共著、IPB/2003・2004・2005年)、『新たな文明の創造をめざして』(編著、秋桜社/1994年)、『細胞社会とその形成』(共著、東京大学出版会/1989年)ほか。
アスタミューゼ株式会社 テクノロジーインテリジェンス部部長。薬学博士(分子生物学・発生細胞化学)。
1959年4月、大阪生まれ。東京大学大学院薬学系研究科 後期博士課程 修了。
博士号取得直後に起業、国際会議プロデューサーなどを経て、2001年より、株式会社アイ・ピー・ビー(Intellectual Property Bank)に参画。取締役技術情報本部長、Chief Science Officerなどを歴任、世界初の知財の多変量解析システム構築、知財力と経営指標の総合評価による株式投信開発、シードベンチャーへのプリンシパル&ファンド投資、事業プロデュースなどに携わる。
2011年末、アスタミューゼ入社。広範な産業分野の技術・事業コンサルティング、約180の有望成長領域の策定、世界の研究・技術・グローバル市場(ベンチャー、上場)の定量評価手法の開発、医学会などでの招待講演、各種執筆などに奮闘中。
おもな編著書は『生体データ活用の最前線』(共著、サイエンス&テクノロジー社/2017年)、『IoTビジネス・機器開発における潜在ニーズと取り組み事例集』(共著、技術情報協会/2016年)、『実践 知的財産戦略経営』(共著、日経BPコンサルティング/2006年)、『特許四季報1・2・3』(共著、IPB/2003・2004・2005年)、『新たな文明の創造をめざして』(編著、秋桜社/1994年)、『細胞社会とその形成』(共著、東京大学出版会/1989年)ほか。
本書の要点
- 要点1新たな技術が次々と生まれており、人類が思い描いた未来予想図へ近づいていることは間違いない。そこで大切になるのが、「テクノロジーをどこに使い、人の手をどこに残すか」という視点だ。
- 要点2センシング技術により、空間自体がIoT化していくだろう。蓄積されたデータを活用したビジネスが数多く登場すると予想される。
- 要点3農業や漁業でもデータ化が進む。今後懸念される食糧不足は、テクノロジーが解決するはずだ。
- 要点4自動運転技術が移動の概念を変える。社会構造の変化により、街のあり方も変わっていく。
要約
【必読ポイント!】 2030年のテクノロジーと生活
2030年のスマート漁師が送る生活とは

Besjunior/gettyimages
まずは、本書冒頭に描かれるショートストーリーを紹介したい。物語の主人公は2030年の漁師だ。ぜひ想像力をフルに働かせて、2030年の世界を思い浮かべてほしい。
――自称「スマート漁師」の私は情報通信系のベンチャー企業で、スマート海洋牧場の研究開発をしている。今進めているのは、海中で魚群観察をおこない、精度の高い水産資源管理をめざすプロジェクトだ。そのなかでも私の担当は、「魚型ロボット」の研究である。魚の形や動きを模倣した「バイオミメティック」なロボットを完成させることで、海を泳ぐ自然の魚群に近づき、その生態や行動パターンを解析・把握しようという目論見だ。
今日は久しぶりに、実際に海に出て海洋実験をおこなう日である。私の住む地域は、かつては過疎であった。だが現在は、複数企業合同の研究施設ができたことをきっかけに、小規模都市へと返り咲いた。街に高層ビルはないものの、アーティスティックな現代建築や、自然に溶け込んだ環境建築がたくさん存在する。建物の外壁は日差しの強さに応じて反射率を変える「アルベド調節性」の素材が採用されている。これにより冷暖房効率が上がり、環境負荷の軽減につながっている。人々はキックボード型、立ち乗り型、自立走行車いすなど、パーソナルモビリティに乗って移動をしているし、浮遊しながら移動するドローンバイク、ドローンタクシーも走っている。
私はドローンタクシーに乗り、港に到着。海上にカモメがたくさん飛んでいると思ったら、「バイオニックバード」の群れであった。バイオニックバードは鳥型ソフトロボットで、別の研究グループがそれを使って海上・海中通信の移動型中継基地や海洋資源の調査をおこなっている。さて、それでは研究船に乗って海に出るとしよう。
テクノロジーとの距離感のバランス
いかがだろうか。これが著者の描く2030年の未来予想図である。あと10年でどこまで実現するかはわからないが、新たな技術が日々誕生し、思い描いた未来へと近づいていくことは間違いなさそうだ。
そのうえで著者が重要だと考えているのが、「どこにテクノロジーを使い、どこに人の手を残すか」という視点だ。テクノロジーと付き合う際は、このバランス感覚が重要になる。たとえば自動運転技術が普及し、運転の楽しみがなくなってしまえば、クルマ文化は衰退しかねない。
人間は自分の体を動かして、多少の汗をかいたほうが充実感を得られる生き物である。技術でなんでもかんでも代替すればいいのではなく、テクノロジーはあくまで生活を補助する役割だと心がけよう。
心躍る楽しい未来
空間そのものがIoT化する

metamorworks/gettyimages
2020年代前半にポイントとなるテクノロジーは、「センシング」だと著者は見ている。現在でもスマートウォッチやスマートスピーカーなど、センサーをベースにしたテクノロジーが台頭しているが、今後さらに高感度・高解像度化していくと予想される。家具や家電はもちろんのこと、空間それ自体がIoT化し、センサーネットワークがありとあらゆるものを検知する。そして蓄積されたデータに基づき、最適化が絶えずおこなわれていく。
たとえば未来のベッドルームはこうだ。ベッドに装着されたセンサーにより、寝ている間の体温や心拍、体動などをモニタリングする。日々の就寝状態をベッドサイドのプロジェクターで投影すると、ベッドルームがそのままプライベート遠隔医療システムに早変わり。そのデータをもとに、主治医と話ができるようになるといった具合だ。

この続きを見るには...
残り2943/4422文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.06.07
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約