世界観をつくる
「感性×知性」の仕事術
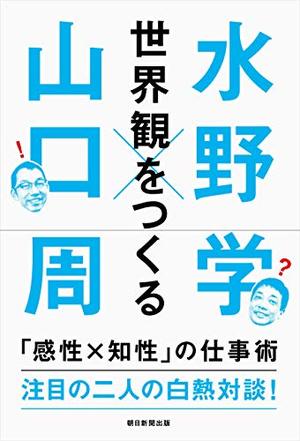
著者
水野学(みずの まなぶ)
クリエイティブディレクター/クリエイティブコンサルタント。1972年、東京都生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業。1998年、good design companyを設立。ブランドや商品の企画、グラフィック、パッケージ、内装、宣伝広告、長期的なブランド戦略までをトータルに手がける。主な仕事に相鉄グループ全体のクリエイティブディレクション及び車両、駅舎、制服等、熊本県「くまモン」、三井不動産、JR東日本「JRE POINT」、中川政七商店、久原本家「茅乃舎」、黒木本店、Oisix、NTTドコモ「iD」、「THE」ほか。2012-2016年度に慶応義塾大学SFCで特別招聘准教授を務める。The One Show金賞、CLIO Awards銀賞ほか国内外で受賞歴多数。著書に『センスは知識からはじまる』(朝日新聞出版)など。
山口周(やまぐち しゅう)
1970年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部哲学科美学美術史学専攻、同大学院文学研究科美学美術史学修士課程修了。電通、ボストン・コンサルティング・グループ、コーン・フェリー等で企業戦略策定、文化政策立案、組織開発等に従事した後に独立。現在は「人文科学と経営科学の交差点で知的成果を生み出す」をテーマに、独立研究者、著作家、パブリックスピーカーとして活動。現在、株式会社ライプニッツ代表、世界経済フォーラムGlobal Future Councilメンバーなどの他、複数企業の社外取締役、戦略・組織アドバイザーを務める。著書に『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(光文社)、『武器になる哲学』(KADOKAWA)、『ニュータイプの時代』(ダイヤモンド社)など。
クリエイティブディレクター/クリエイティブコンサルタント。1972年、東京都生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業。1998年、good design companyを設立。ブランドや商品の企画、グラフィック、パッケージ、内装、宣伝広告、長期的なブランド戦略までをトータルに手がける。主な仕事に相鉄グループ全体のクリエイティブディレクション及び車両、駅舎、制服等、熊本県「くまモン」、三井不動産、JR東日本「JRE POINT」、中川政七商店、久原本家「茅乃舎」、黒木本店、Oisix、NTTドコモ「iD」、「THE」ほか。2012-2016年度に慶応義塾大学SFCで特別招聘准教授を務める。The One Show金賞、CLIO Awards銀賞ほか国内外で受賞歴多数。著書に『センスは知識からはじまる』(朝日新聞出版)など。
山口周(やまぐち しゅう)
1970年、東京都生まれ。慶應義塾大学文学部哲学科美学美術史学専攻、同大学院文学研究科美学美術史学修士課程修了。電通、ボストン・コンサルティング・グループ、コーン・フェリー等で企業戦略策定、文化政策立案、組織開発等に従事した後に独立。現在は「人文科学と経営科学の交差点で知的成果を生み出す」をテーマに、独立研究者、著作家、パブリックスピーカーとして活動。現在、株式会社ライプニッツ代表、世界経済フォーラムGlobal Future Councilメンバーなどの他、複数企業の社外取締役、戦略・組織アドバイザーを務める。著書に『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(光文社)、『武器になる哲学』(KADOKAWA)、『ニュータイプの時代』(ダイヤモンド社)など。
本書の要点
- 要点1日本企業はこれまで「役に立つ」という価値で戦ってきた。しかしこれからは「意味がある」という価値に軸足を移すべきだ。
- 要点2「意味がある」とはストーリー、世界観があるということだ。スターバックスはコーヒー店というレッドオーシャンの極致のような市場で、世界観だけで勝負して世界中に広がった。
- 要点3デザインの役割とは、未来を連れてくることだ。いまここにない世界を想像し、鮮明に思い浮かべて実現への道筋を考え、最終的なアウトプットまでつくりあげることだ。
要約
未来の会社がつくっていく「価値」とは?
過剰な便利さは価値を下げる

a40757/gettyimages
会社が生み出している価値とはそもそも何だろうか。企業が社会に対して何か価値を提供できればその対価がもらえる、というのがビジネスの仕組みだ。しかしその価値自体は社会のあり方によって変わっていく。「過剰になったモノ」の価値は下がるし、「希少になったモノ」の価値は上がる。毎日ステーキが出てくればそれは普通のおかずになってしまうし、冷蔵庫を持っている家がまだ1割程度だった昭和30年代半ばだからこそみんながテレビを欲しがった。
今は、「みんなが心から欲しいと思うモノ」がなくなってしまっている。お金を払って解決したいと思うような「問題=困っていること」が、もはや希少になっているのだ。
そうして発生している問題が、「正解の過剰化」である。論理的な正しさを突き詰めた結果、みんなが正解に行き着いてしまって、デザインや機能に差の無い商品が市場にあふれるような状況になっている。どのような欲求に対する正解だったのか、という課題は置き去りにされ、技術の進歩で便利なモノが増え続ける、いわば「利便性が過剰」な状態だ。そうなると逆に便利さの価値が下がって、薪ストーブのような不便なものの価値が高まっている。ある意味、文明の否定と言える。
コストをかけてテレビのリモコンのボタンを増やしても、そこに顧客は価値を感じなくなっている。過剰な便利さを求めても、収益性の低い商品が生まれるだけだ。これは労働生産性を下げることにもつながっている。
物差しが「100メートル走」ではツラい
会社は、「役に立つという価値」か「意味があるという価値」かのいずれかを戦略として選ぶ。日本企業はこれまでずっと「役に立つという価値」で戦ってきた。しかし今はその価値が過剰となり、「意味があるという価値」が希少になっている。別の言い方をすれば、インターネットによる文明の大革命が十分進んで、文化の時代になっているということだ。
しかしこの観点でビジネスを転換していくことは、多くの組織にとって難易度が高い。

この続きを見るには...
残り3477/4334文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.07.13
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.Copyright © 2020 水野学 All Rights Reserved. Copyright © 2020 山口周 All Rights Reserved. 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は水野学、山口周および株式会社フライヤーに帰属し、事前に水野学、山口周および株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.Copyright © 2020 水野学 All Rights Reserved. Copyright © 2020 山口周 All Rights Reserved. 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は水野学、山口周および株式会社フライヤーに帰属し、事前に水野学、山口周および株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
一緒に読まれている要約











