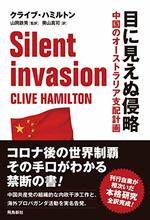デジタルテクノロジーと国際政治の力学

デジタルテクノロジーと国際政治の力学
著者

著者
塩野誠 (しおの まこと)
経営共創基盤(IGPI)共同経営者・マネージングディレクター
JBIC IG Partners代表取締役 CIO(最高投資責任者)
IGPIテクノロジー取締役
JB Nordic Ventures(Nordic Ninja, フィンランド)取締役
ニューズピックス社外取締役、ビーピット社外取締役
内閣府デジタル市場競争会議ワーキンググループ議員
元・人工知能学会倫理委員会委員
シティバンク、ゴールドマン・サックス、ペインアンドカンパニー、ライブドア、起業などを経て現職。現在はIGPIにおいて政府機関、グローバル企業に対するコンサルティングやM&Aアドバイザリー業務に従事。JBIC IG Partnersにおいてはロシア・北欧・バルト地域において投資業務を行う。通信・メディア・テクノロジー領域を中心にクライアントに提言を行い、15年以上の企業投資経験を持つ。
慶應義塾大学法学部政治学科卒 久保文明研究会(米国政治)
ワシントン大学セントルイス法科大学院 法学修士
フィンランド(ヘルシンキ)在住
IGPIはコーポレートトランスフォーメーション(CX)を掲げ、グローバル企業から日本のローカル企業までコンサルティング、M&A、財務アドバイザリーを提供している。また、AI・データサイエンス事業や、研究機関が保有する技術の事業化も行っている。
JBIC IG Partnersは国際協力銀行(JBIC)とIGPIの合弁会社である。
経営共創基盤(IGPI)共同経営者・マネージングディレクター
JBIC IG Partners代表取締役 CIO(最高投資責任者)
IGPIテクノロジー取締役
JB Nordic Ventures(Nordic Ninja, フィンランド)取締役
ニューズピックス社外取締役、ビーピット社外取締役
内閣府デジタル市場競争会議ワーキンググループ議員
元・人工知能学会倫理委員会委員
シティバンク、ゴールドマン・サックス、ペインアンドカンパニー、ライブドア、起業などを経て現職。現在はIGPIにおいて政府機関、グローバル企業に対するコンサルティングやM&Aアドバイザリー業務に従事。JBIC IG Partnersにおいてはロシア・北欧・バルト地域において投資業務を行う。通信・メディア・テクノロジー領域を中心にクライアントに提言を行い、15年以上の企業投資経験を持つ。
慶應義塾大学法学部政治学科卒 久保文明研究会(米国政治)
ワシントン大学セントルイス法科大学院 法学修士
フィンランド(ヘルシンキ)在住
IGPIはコーポレートトランスフォーメーション(CX)を掲げ、グローバル企業から日本のローカル企業までコンサルティング、M&A、財務アドバイザリーを提供している。また、AI・データサイエンス事業や、研究機関が保有する技術の事業化も行っている。
JBIC IG Partnersは国際協力銀行(JBIC)とIGPIの合弁会社である。
本書の要点
- 要点1テクノロジーは、いつだって国家の安全保障に影響を与えてきた。いま米国がファーウェイを排斥する動きを見せているのは、デジタルテクノロジーのパワーがますます強大になると考えているからだ。
- 要点2対立する国家の間では、情報は兵器化する。フェイクニュースで社会不安を煽り、国民を分断するといった世論操作も、きわめて安価に実現することができる。
- 要点3新型コロナウイルス感染症の拡大で、独裁国家で利用されている国民監視ツールが各国で導入されるかもしれない。米国が弱体化したいま、日本こそが自由と民主主義の砦となる可能性もある。
要約
デジタルテクノロジーの現代史
なぜ、米国はファーウェイを警戒するのか

Nuthawut Somsuk/gettyimages
2018年8月は、米中関係が変わるひとつのターニングポイントとなった。米国は安全保障を理由に、中国の通信機器メーカーであるファーウェイ製品を、政府機関や関連組織で利用することを禁じた。さらには、同社への半導体などの輸出も事実上禁じている。
通信機器において世界シェア30%を占めるファーウェイだが、それでも一民間企業にすぎない。なぜ米国政府は、ここまで厳しい制裁を課すのか。それは中国政府による軍民融合の方針から、通信ネットワーク上でスパイ行為を行う恐れがあるからだ。加えて、国家の覇権に技術が影響を与えてきたという歴史的経緯と、これまで以上にデジタルテクノロジーが影響力を発揮するという予測も関係している。
テクノロジー覇権を守るため、なりふり構わない米国の姿がそこにはある。
イノベーションは軍事的脅威から生まれてきた
1957年、米国と西側諸国にスプートニク・ショックが駆け巡った。旧ソ連が人類初の人工衛星、スプートニク1号の打ち上げに成功したのだ。これは、米国が旧ソ連に遅れを取ったことを意味していた。
翌年、米国では現在のNASA(米国航空宇宙局)とDARPA(国防高等研究計画局)が組織された。DARPAはインターネットの生みの親と言われているが、ドローンやGPS、ステルス技術、音声認識や翻訳技術などの研究も古くから手掛けている。
DARPAで革新的なイノベーションが生まれる理由は、プログラムを監督するプログラムマネージャの高い自由度にある。数年間、独裁的に資金や権限を采配できるのだ。この手法は、現在のスタートアップ企業に近いものといえる。
ビル・ゲイツが恐れたもの
マイクロソフトの元CEOであるビル・ゲイツ氏は、パソコン業界をいまよりも支配していた時代に、「もっとも恐れている競合は?」という質問に対して、「どこかのガレージでまったく新しいものを考えている誰か」と答えた。その懸念は現実のものとなった。1998年創業のグーグルは、翌年にはベンチャーキャピタルが30億円を投資する企業になっていた。
インターネットの黎明期から、DARPAのような政府機関、起業家が技術を学んだ大学、リスクをとるベンチャーキャピタルが一種の生態系をつくり、巨大デジタルテクノロジー企業の成立に寄与している。たとえば代表的なベンチャーキャピタルであるセコイアが投資した企業の時価総額は、合計でおよそトヨタ6つ分だ。ベンチャーキャピタルはツイッター、フェイスブック、Uberといったプラットフォーマーを生み出し、既存の産業構造を変えていった。
ハイブリッド戦争とサイバー攻撃
グレーゾーン化する日常

solarseven/gettyimages
2007年、人口130万人の電子立国エストニアが大規模なサイバー攻撃を受けた。これにより、デジタルテクノロジーに関する安全保障は新しい次元に入った。サイバー攻撃はこれまでの軍事行動に比べ、きわめてコストが低く、匿名性の高い攻撃手段だ。
デジタルテクノロジーの隆盛によって、国家間の紛争は平時とも有事とも言えないグレーゾーンの紛争へと姿を変えつつある。サイバー攻撃によって威嚇したり、デマ情報を流して他国に干渉したりすることは、もはや日常茶飯事である。
サイバー攻撃に武力で応じることは可能か。日本政府の見解は、

この続きを見るには...
残り3093/4467文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2020.11.14
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約