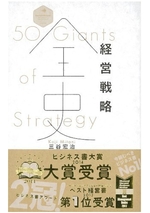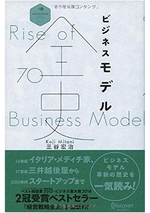コロナ禍のオフィストレンド
オフィスはもう不要?

新型コロナウイルスの蔓延により、テレワークは珍しいものではなくなった。その中で多くの企業が、オフィスの価値に疑問を持ち始めている。
サービス産業の生産性改善サービスを手がけるベンチャー企業、ClipLine(クリップライン)は、いち早くオフィス縮小を決断した企業のひとつだ。港区の一等地に構えたオフィスは180坪で、賃料は月額500万円。2020年4月8日から在宅勤務を導入したが、同月末にはオフィスオーナーに解約を申し出て、オフィス縮小へと動き出した。
出社率から試算したところ、今後、オフィス面積はたった60坪しか必要ないことがわかった。移転先として見つかった新オフィスの賃料は月額100万円で、大きなコストダウンとなる。縮小移転にあわせて働き方も見直し、オフィスを「他者と協調しながら作業する場所」と再定義した。
オフィスを完全撤廃する企業も出てきている。デジタルマーケティングなどを手がけるベンチャー企業、overflow(オーバーフロー)は、コロナ禍以前から新しいオフィスへの移転を決めていた。しかし、このたびの事態で考え方は一変。熟慮の末、オフィス不要と結論づけた。
同社のCEOである鈴木裕斗氏は、「もうオフィスでしか絶対にできないことなんて、ない」と語る。自然発生的な雑談は確かに必要だが、一方で、人間関係のストレスも無視できない。その考えのもと、適切なテレワーク環境を整えることを前提に、完全テレワークの決断を下した。
あえてオフィスを拡大させる理由
オフィス面積をあえて広げる企業もある。住宅などのデザインやリノベーションを手掛けるリノべるは、2019年からオフィス移転計画を進めてきた。そして今なお、拡大移転の決断に変わりはないとする。
その理由として、同社は、オフィスでの「空気」を挙げる。人は相手の声色や表情、しぐさなどを「空気」として察知している。時にはそれが人の心を動かし、やる気にさせることもあるだろう。そういった「空気」はオンラインコミュニケーションでは存在しづらい。加えて、社員からは、「在宅だと集中力が上がらない」という意見や、オフィスでこそ得られるインスピレーションがあるという声も上がっているそうだ。
オフィスのこれからについて、各社の判断は千差万別だ。ただ、いずれの会社も社員の意見や組織事情を考慮し、自社にとって最適な環境を整えている点は共通しているといえる。
働き方とオフィスに関する注目のキーワード
テレワークと相性のいい「ジョブ型雇用」

「ジョブ型雇用」「ワーケーション」「ABW」……コロナ禍では、こうしたキーワードがトレンドとなっている。
ジョブ型雇用は、テレワークとの相性がよいとされて注目を集めている。ジョブ型雇用とは、一般的に、従業員に対して職務領域やその具体的な内容を明確に定義し、その職務に対する成果を評価する雇用形態を指す。政府は2020年7月、「ジョブ型正社員のさらなる普及・促進に向け、雇用ルールの明確化や支援に取り組む」とし、ジョブ型雇用を「職務や勤務場所、勤務時間が限定された働き方などを選択できる雇用形態」と定義した。
これまで日本では、「メンバーシップ型雇用」、すなわち終身雇用制度や年功序列を基本とした雇用システムが一般的であった。メンバーシップ型雇用では、会社の一員であることが重視され、ゼネラリストが評価される傾向にある。
一方、ジョブ型雇用では、従業員の専門性を尊重し、本人の意思に反する異動や職務変更は行われない。人事評価は、本人の職務と専門性のレベルに応じてなされる。
テレワークにおいて、上司の指示を仰ぎ、細かなホウレンソウをしていては、生産性が落ちてしまう。その点、ジョブ型雇用では、従業員は自らの職務に応じて自律的に働くのが基本だ。新しい働き方がもとめられる中で、ジョブ型の長所を採用した人事制度に積極的になる企業が多いのもうなずけるだろう。
柔軟な働き方を実現する「ABW」
ABWは「アクティビティー・ベースド・ワーキング」の略で、自身の仕事内容に応じて、働く場所や時間を自由に選べる働き方を指す。一人で集中して作業したいときは個室や区切られた空間で、複数人で話し合いたいときはアイデアが出やすい開放的な空間で、といったふうに、アクティビティーに最適な場所を用意したオフィスが最先端とされてきた。
ABWを提唱したオランダの戦略コンサルティング企業、ヴェルデホーエンは、企業のオフィスにおけるアクティビティーを「高集中」「コワーク」「電話・Web会議」「2人作業」「対話」「アイデア出し」「情報整理」「知識共有」「リチャージ」「専門作業」の10種類に分類する。