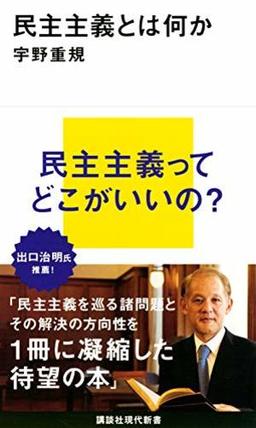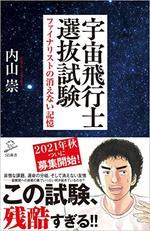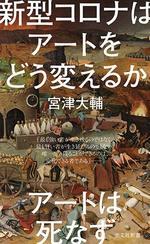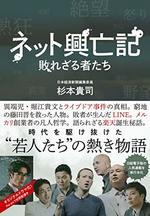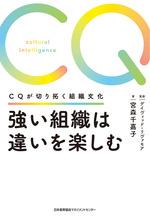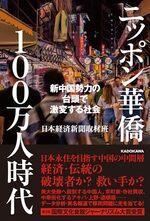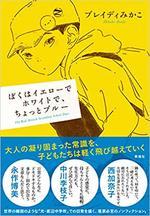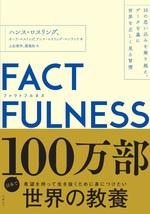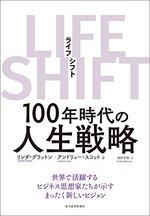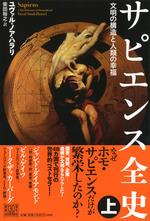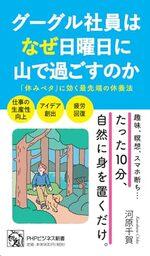民主主義の4つの危機
ポピュリズムの台頭
現代は民主主義がさまざまな危機に直面している時代であるが、本書では4つの側面から考える。
まず「ポピュリズムの台頭」であるが、それを強く印象づけたのは、2016年6月のブレグジットと同年11月のトランプ大統領の誕生である。その背景にあるのが、ポピュリストによって扇動された、経済的に没落した中間層の存在である。
格差の拡大する中で民主主義は維持可能なのか。格差によって国民の一体性の感覚が損なわれた先で起こる、世論の分断を乗り越えられるのか。ポピュリズムはこれらの問題を大きくクローズアップした。
独裁的指導者の増加

かつて世界の国々は、遅かれ早かれいつかは民主化するという「常識」があった。ところが、こうした考え方は現在、大きく揺さぶられている。経済成長にとって自由民主主義は本当に不可欠なのか。「独裁的指導者の増加」は欧米的価値観の問い直しにつながる可能性を秘めている。
中国も以前は欧米的な民主化を目指すとしていたが、現在の習近平体制に移行して以降、中国独自の路線を強調するようになった。重要なのは秩序の維持と国民生活の安定・発展であり、それには共産党の独裁体制の方が望ましい。
このような「チャイナ・モデル」はいまや、他国にとっても魅力的なものになっている。民主的な政治過程にはどうしても時間がかかるので、独裁的指導者によるトップダウン式の方が変化の激しい時代に適合的であるというわけだ。
第四次産業革命の影響
「技術革新による影響」でもっとも注目されているのが、AI(人工知能)が人々の雇用を奪うのではないかという懸念である。
また、イスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリは『ホモ・デウス』で次のような警告をしている。ビッグデータとアルゴリズムを保有する一部の有力者による「デジタル専制主義」が拡大する一方、その他の多くの人々は「無用階級」へと転落する、と。
いまや人々はアルゴリズムのメカニズムによって、自分が気に入る情報ばかりに接することで、特定の考え方ばかりが増幅される環境に置かれている。
こうした環境の変化は、1人ひとりの人間を平等な判断主体とみなす民主主義の前提に揺さぶりをかけている。
コロナ危機
新型コロナウィルスによる感染症の拡大において、緊急事態を理由にロックダウン(都市封鎖)をはじめとした、個人の自由や権利を大きく制限する施策が遂行された。
民主的な合意形成にはどうしても時間がかかる。結果として、民主主義はこのような緊急事態に迅速かつ適切に対応できないのではないかという意見も聞かれるようになった。
また民主主義においては、人と人が顔を合わせ、直接対話を行うことはきわめて重要な要素である。感染拡大を防止するため、こうした条件が阻害されることはけっして望ましいことではない。
こうした現状の危機を乗り越えるために、本書では歴史を遡りながら考えていく。