「なぜ」「どのように」科学について語るのか?
「外側」からの視点が不可欠な理由

もともと科学と技術はまったく異なる活動だ。前者は自然界の成り立ちを知ることで、後者は人工物をつくることである。しかし現在は、この2つが融合した領域が拡大している。たとえば生命医科学(生命科学+医学)や、情報理工学(情報科学+情報技術)などがそうだ。こうした融合領域の活動は社会との接点が多く、さまざまな問題を生みだしている。加えて、そもそも科学研究を行うこと自体が社会的な営みである以上、現実世界の複雑な問題を避けて通ることはできない。
ある領域のなかだけに閉じこもっていると、その領域そのものを絶対視してしまい、大きな文脈のなかで自分たちを位置づけることが難しくなってしまう。現在の科学技術に関わるということは、社会に関わるということであり、外側からの視点が不可欠である。
STAP細胞事件と科学における「事実」
2014年、理化学研究所で「STAP細胞事件」と呼ばれるスキャンダルが起きた。すでに分化した動物の細胞を弱酸性の溶液にひたすなどの刺激を与えることで、未分化の状態に戻せるという発見だった。しかし「実験結果が捏造ではないか」という声が上がり、最終的に論文は撤回された。
この事件で明らかになったのは、科学という活動の社会的なイメージが、専門分野の研究者たちの肌感覚と大きくズレていることだった。「STAP細胞はあるのか、ないのか?」という記者の質問は、このズレを象徴していた。
日常的に役立つ事実や知識であれば直観的・感覚的に判断すればいいが、科学的な知識を検証する場合は、これだと不十分だ。科学における「事実」とは、専門研究者集団がよってたかってアラを探し、それでも瑕疵が見つからなかったとき、はじめて認定される。認定までには、それだけ長い時間がかかるのだ。
科学技術は誰のものか
「役に立つ」とはどういうことか
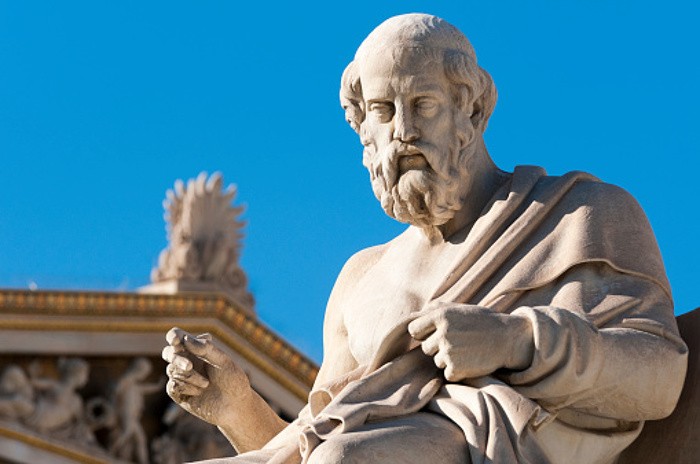
いま科学技術のイメージは、「科学研究には基礎的なものと応用的なものがあり、実用に供される技術がある」というように分化している。しかし知の有用性という概念は古代ギリシアにまでさかのぼり、時代とともにさまざまな様相を呈してきた。この100年は、科学の意義が「知識のため」と「社会のため」との間を揺れ動いている。
古来、科学技術を必要としていたのは、第一に権力者だった。「天下」という概念も、古代中国で「天から見下ろす」視点を得た者、つまり天体の動きを把握して暦をつくる権力者を意味していた。季節や天候の変化を予測できる暦の策定は、統治にとって重要なアイテムだったのだ。「時間」を測る暦と同じく、「空間」を測る度量衡の統一も権力者の重要な課題だった。たとえば、メートル法を普及させたのはナポレオンである。
科学と技術が分化していくプロセス
統治のための道具であった科学技術は、同時に民衆の生活を豊かにし、安定させることにも寄与した。19世紀前半には「科学はヒューマニズムを具現化する手段」「人々の苦痛を減らし、快適さを増大させることこそ、科学の意義」という考え方が広まった。
自然科学が実用的な価値から切り離され、真理を追求し、知識を増やす活動として意義があると考えられはじめたのは、19世紀後半である。これを科学の「制度化」と呼ぶ。専門家が集まって情報を共有できる学会や協会がつくられ、学術誌が安定的に刊行されるとともに、専門家を育成する教育制度や機関が整備された。
この制度化の象徴といえるのが、




















