観察力の鍛え方
一流のクリエイターは世界をどう見ているのか


著者
佐渡島庸平(さどしま ようへい)
株式会社コルク代表取締役社長。編集者。
1979年生まれ。中学時代を南アフリカ共和国で過ごし、灘高校に進学。2002年に東京大学文学部を卒業後、講談社に入社し、「モーニング」編集部で井上雄彦『バガボンド』、安野モヨコ『さくらん』のサブ担当を務める。03年に三田紀房『ドラゴン桜』を立ち上げ。小山宙哉『宇宙兄弟』もTVアニメ、映画実写化を実現する。伊坂幸太郎『モダンタイムス』、平野啓一郎『空白を満たしなさい』など小説も担当。
12年10月、講談社を退社し、クリエイターのエージェント会社・コルクを創業。『宇宙兄弟』『インベスターZ』『テンプリズム』『修羅の都』『オチビサン』『マチネの終わりに』『本心』などを担当。インターネット時代のエンターテイメントのあり方を模索し続けている。コルクスタジオで、新人マンガ家たちと縦スクロールで、全世界で読まれるマンガの制作に挑戦中。
株式会社コルク代表取締役社長。編集者。
1979年生まれ。中学時代を南アフリカ共和国で過ごし、灘高校に進学。2002年に東京大学文学部を卒業後、講談社に入社し、「モーニング」編集部で井上雄彦『バガボンド』、安野モヨコ『さくらん』のサブ担当を務める。03年に三田紀房『ドラゴン桜』を立ち上げ。小山宙哉『宇宙兄弟』もTVアニメ、映画実写化を実現する。伊坂幸太郎『モダンタイムス』、平野啓一郎『空白を満たしなさい』など小説も担当。
12年10月、講談社を退社し、クリエイターのエージェント会社・コルクを創業。『宇宙兄弟』『インベスターZ』『テンプリズム』『修羅の都』『オチビサン』『マチネの終わりに』『本心』などを担当。インターネット時代のエンターテイメントのあり方を模索し続けている。コルクスタジオで、新人マンガ家たちと縦スクロールで、全世界で読まれるマンガの制作に挑戦中。
本書の要点
- 要点1最も応用が効き、かつ経営や創作に役立つ能力は「観察力」である。「観察力」を鍛えることで、他の能力も必然的に向上させることができる。
- 要点2「認知バイアス」「身体・感情」「コンテクスト」の3つが観察を阻む要因であることを認識し、これらを「仮説」として用いることでいい観察ができるようになる。
- 要点3「いい観察」により、バイアスのかかった無意識下での判断を避け、多様性を受け入れる「あいまい」な思考をすることが可能となる。
要約
観察力について
「いい観察」と「悪い観察」

Wavebreakmedia/gettyimages
ピラミッドを作った人や日本地図を作った人、そして「万有引力の法則」を発見したニュートンのような過去の偉人とわたしたちの差は何だろうか。編集者である著者は、「観察力」の差であると考えた。では「観察力」とは一体何か?
著者によれば、「観察力」とは経営や創作に役立つ能力であり、これを鍛えれば必然的に他の能力も鍛えることができる、いわば「ドミノの一枚目」だ。「客観的になり、注意深く観る技術」と「組織的に把握する技術」の組み合わせが「観察力」と言えるかもしれない。本書が着目するのは、「客観的になり、注意深く観る技術」である。
「観察」について考えるにあたり、著者は漫画家の羽賀翔一氏の成長を「観察」した。新人の頃の羽賀氏は著者が経営するコルクの社員を観察して一日1ページの漫画を描いていた。これは著者の発案で行われたものだったが、「半径5メートル以内の出来事を毎日1ページマンガにする」という課題を続けることが羽賀氏の観察力を鍛え上げ、この成果はやがて『漫画 君たちはどう生きるか』の大ヒットという形で結実した。
著者は羽賀氏の経験から観察力の鍛え方に再現性を持たせることを試み、この本の執筆に際して二年近い時を費やして「観察」についての考察を行った。そして辿り着いた仮説で「いい観察」と「悪い観察」について次のように定めている。「いい観察は、ある主体が、物事に対して仮説をもちながら、客観的に物事を観て、仮説とその物事の状態のズレに気づき、仮説の更新を促す。一方、悪い観察は、仮説と物事の状態に差がないと感じ、わかった状態になり、仮説の更新が止まる」というものである。
いい観察によって問いと観察の無限ループを生み出し、悪い観察を避けることが重要だ。悪い観察を避けるには「認知バイアス」「身体・感情」「コンテクスト」という解像度に影響を及ぼす3つの要因に注意し、観察の精度を高めることを心がけよう。
仮説の立て方
観察を邪魔する「認知バイアス」「身体・感情」「コンテクスト」の3つを著者は「メガネ」と呼ぶ。「認知バイアス」とは常識、偏見、言葉、概念などを指す。実は人は目で見ているのではなく、脳が先に何を見るかを決めており、バイアスはこの脳の認知に作用する。では「身体・感情」はなぜ観察の邪魔になるのだろうか? 観察は五感によって行われるが、疲労などの肉体のコンディションや喜怒哀楽といった感情は観察の質に影響を及ぼす。最後は「コンテクスト」だが、これは例えばある人の格好を見て「だらしない」と思うか、あるいはTPOに相応しいリラックスした格好と感じるかは、状況によって変わる、といったものだ。
人間がものを見るとき、これらの要素の影響を受けることは免れない。この「メガネ」を完全に取り去ることはできないが、それを自覚した上でこの「意識的なメガネ」を、自らの「仮説」として観察の際に用いることを著者は勧める。例えば、ニュートンの「万有引力の法則」は、もともとは「なぜリンゴは地面に落ちるのだろう?」という極めてシンプルな問いから始まっている。歴史に残る偉大な発見も、最初はごく単純な問いにすぎない。ありふれた問いを仮説と観察の積み重ねで更新しよう。
では優れた仮説はどのように立てればよいのか? まずはできるだけ主観を排除しながら自らの目で見たものをひたすら言葉にする「ディスクリプション」を行う。二つ目は、他者がどのようにディスクリプションしているかを「真似る」。三つ目は「統計データ」を用いる。これらの行為を行う際には、適切なタイミングで客観的に、またあるときは主観的になることが重要であると著者は考える。主観と客観のスイッチを適切に切り替えることによって観察の質を上げることが可能になる。
編集者として『ドラゴン桜』や『宇宙兄弟』など多くのヒット作品を生み出してきた著者は、かつては仕事に必要なのはホームランであると考えていた。しかし経験を重ねるうちに、最も大切なのは「普通」であり続けることであると気づくに至った。そのためにまずやるべきことは、他者や、すでにある普遍的な「型」を徹底的に真似て基本を身につけることだ。「真似る」ことの繰り返しの中で観察の解像度が上がり、自ずと湧き上がる自分の欲望や関心からやがて「オリジナリティ」が生まれてくる。
【必読ポイント!】「見えないもの」を観察する
「感情」と「関係性」

Jolygon/gettyimages
これまで述べてきた「見えるもの」の観察はある程度再現性があるが、では「見えないもの」を観察するにはどうすればいいだろうか。
見えないものは歴史に記録されていなかったり、あるいは後世の人間には理解できない形で残されている。しかし著者は、社会を本当に動かしてきたのはそのような「見えないもの」なのではないか、と考える。
著者が観察の対象とする「見えない」ものは「感情」と「関係性」だ。
「感情」を重要視するようになったきっかけの一つは、著者が中学時代を過ごした南アフリカで目撃したマンデラ大統領誕生の選挙だ。このとき現地で目の当たりにした、白人と黒人の歌手がともに歌を歌う様子から、著者は人々の「国を守りたい」と願う祈りの気持ちを感じ、胸を打たれた。しかしこの曲は今ではインターネットの検索で見つけることもできず、歴史に残されてもいない。このように歴史としては記録されていなくとも、確かに存在していた人々の「感情」を観察することによって歴史や社会、人を理解したいと著者は考えるようになった。
そしてもう一つの観察対象である「関係性」をわかりやすく表しているのは、作家の平野啓一郎が唱える「分人主義」だ。人は、他者と接している時の自分は「本当の自分」ではなく「演技した自分」であると考えているかもしれない。しかし実はそうではなく、家での自分や会社、パートナーと一緒にいるときの自分はどれも本当の自分であり、それぞれの場面での異なる「キャラ」が集合して一人の人間を形成しているとするのがこの概念だ。
「最も合理的なセンサー」
この「感情」と「関係性」という二つの「見えないもの」を感知する能力は「物語」によって鍛えられると著者は言う。人は「物語」を通して、現実世界では見えにくい他者の内面に入り込むことができるようになる。従来の学校教育や社会では人々は論理的に動くように教育され、まるで工場で働く一員のように資本主義の社会にとって効率性を高めるべく生きることを望まれた。しかしそのような過去の時代とは異なり、テクノロジーの発達によって知が解放されたこの人間中心主義の現代では、「感情」や「関係性」が重要度を増すと著者は予想している。
「感情」の定義とは何か。人間は常になにかしらの感情を持っているが、今、あるいは少し前にどのような感情を持っていたかを即座に述べることはできないだろう。ギリシア哲学や仏教を見ても、人間は2000年ちかく「感情」を的確に定義できないままでいるようだ。この問いに答えることは難しいことは認めつつ、著者は「感情は、ヒトという動物にとって、最も合理的なセンサー」という考えを紹介する。そしてこの取扱困難なセンサーを理性と調和させることで、社会と適切な距離をとり、自らにとって快い状態を保つことができる、と考えている。
愛ある観察
判断を保留する

Ponomariova_Maria/gettyimages
人間は「わかりたい!」と願って、知識を身につけ、必死に学ぶ。著者はこの「学ぶ」という行為を次の2種類に分けることができると考える。
1「スキルを身につけることで、無意識に行えるようにする学び」
2「身につけているスキルを、意識的に行えるようにする学び」
1の学びは主に学校教育で行われる、基礎学力を身につけることを目的としたものだ。そして本書で著者が行っているような「観察」をめぐる思考においては、2の学びが主眼となる。まず1の「ラーン」(学び)を極め、それを意識的に手放すことで2の「アンラーン」(脱学習)に移行することが可能となる。この「アンラーン」に至るとき、人は「判断保留」している。
ギリシア哲学の用語で「エポケー」と呼ばれる「判断保留」とはどのようなものか。「観察」に重ねて捉えると、次のように考えることができる。人間の行為の多くは、無意識のうちに行われている。例えば車の運転やスポーツなどでは徹底して「型」を真似ることにより、やがて「動作を無意識下」に置くことができるようになる。人間は本能的に「無意識」で動きたいと願うが、「観察」はそのような無意識下での行為を意識下にあげることであると著者は述べる。それによって正解のない、不安で「あいまい」な状態に自らを置くことになる。この「あいまい」な状態から世界と自分を観察した上で、自分の感情に従うことこそが著者が目指す生き方であり、この状態を保つためにこそ「観察力」が必要なのだ。
「あいまい」な思考法
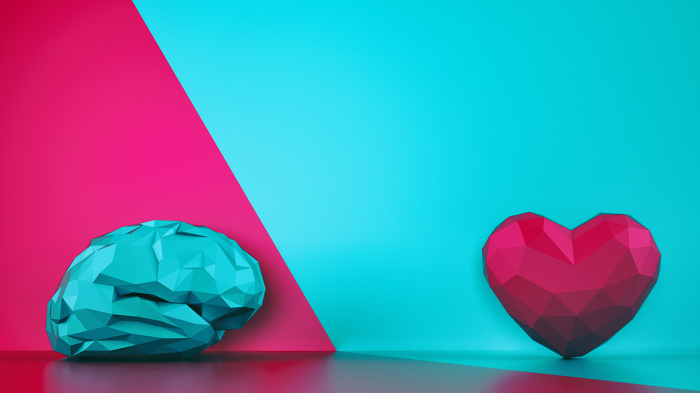
alphaspirit/gettyimages
「あいまい」な思考法は、今の時代にあっている、と著者は考える。
これまでの社会では人々はマイホームや高学歴に象徴されるような「スタンダード」を求めてきた。例えばLGBTQという存在に目を向ければ、彼らは新たに現れたわけでなく、昔から存在していた。しかし「男女」という曖昧さを排除した2つだけの性別の概念で運営される社会の中で、その存在が可視化されてこなかったにすぎない。いま社会はそのような「スタンダード」(標準化)から、あいまいさを受け入れる「ダイバーシティ」(多様性)に向けて変化の時期を迎えている。
多様性を受け入れるには、バイアスのかかった無意識の判断をしないようにする必要がある。あいまいなものを抱えつつ、あるがままに観察することが大事だ。
そして観察に最も重要なものは、対象への「愛」である、というのが著者が辿り着いた考えだ。「愛」によって、いい観察ができるようになる。そしていい観察によって、愛はさらに深まる。その愛する対象を、「どう愛しているか」を表現する。つまり「一流のクリエイターは、愛にあふれている」。
今著者の中には新しい問いが生まれた。「愛とはなんだ? どうすれば、僕の中で、対象への愛をあふれさせることができるのだろう?」

この続きを見るには...
残り0/4139文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2021.10.30
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約











