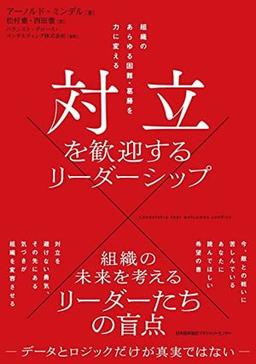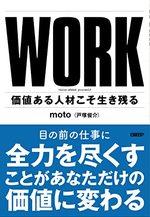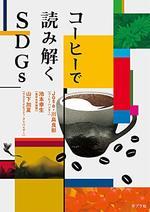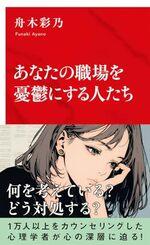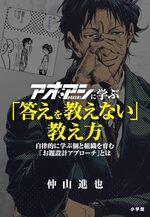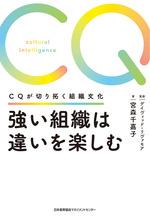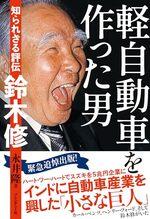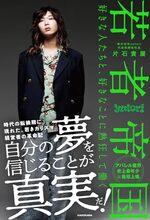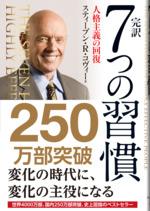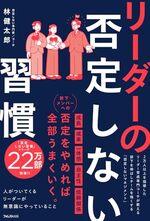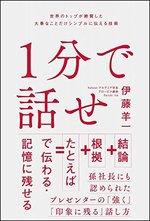フィールドの要素
自然に従うワールドワーク

本書は、プロセスワークにおける集団へのアプローチ、ワールドワークについて述べたものだ。プロセスワークとは、人が気づいていない自分自身や組織、社会の可能性に気づいて、それを実現していくのをサポートする手法である。そしてワールドワークは、心理学、物理学、スピリチュアルな伝統の知識をそれぞれ活用して、集団の変容を促すものだ。著者はワールドワークによって、個人・組織いずれの観点からも、より有意義で楽しい世界の創造を目指していく。
このワールドワークは、ディープ・デモクラシーの姿勢があってこそ効力を発揮する。その姿勢とは、人間のすべての部分や世界のあらゆる視点は本来的に重要であると信じる特別な感覚(フィーリング)といえる。ディープ・デモクラシーの感覚は不変のものであり、武道や老荘思想などのスピリチュアルな伝統に由来している。
ワールドワークの土台には民主主義があるが、民主主義的感覚はほとんどの人が持ち合わせていない。たとえば、リーダーに不平不満をいう一方で、公的行事へ参加しないといった行動をとり、リーダーに独裁的な力を与えることもある。ワールドワークを成功させるためには、まず私たち一人ひとりの成長が欠かせない。
ワールドワークの中心には自然の概念がある。病気や憎悪という困難な事象すら、ありのままに受け入れ、思いやりとアウェアネス(気づき)を持って流れに従うと、それらを役立つものにできるという。このプロセスの姿勢を、京都・東福寺の福島慶道老師は「日日是好日」と表現した。
フィールド理論
組織を巨大な氷山として捉えてみよう。指導的立場にある人は水面よりも上に立って、氷山の行き先を見据えている。一方、従業員たちは水面下で集団全体を支えつつも、組織の方向性やビジョンを知らない。そして、より具体的に組織の現実を表すうえでは、スピリチュアルなビジョンや感情、ムードなどの影響がある。これらの目に見えない影響は、物理学ではシャドーエネルギー、ユング心理学では集合的無意識と表現されるものだ。