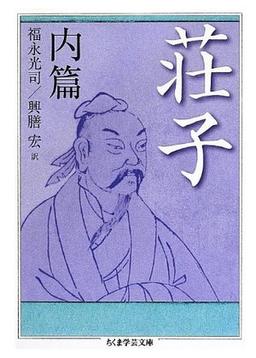「神人」として生きるということ
巨大な魚と小さなウズラ
殷の湯王に使えた賢臣の棘(きょく)は、次のような話を王に伝えた。
極北の地の果てに広がる暗い海、「天の池」に、背幅が数千里もある巨大な魚がいて、名を鯤(こん)という。この魚が変身した姿である鳥、鵬(ほう)は高い山のような大きな背中を持ち、南の果ての暗い海に向かって飛んでいく。小さなウズラがその鳥を見て、「あいつはいったいどこへ行くつもりなんだろう、おれだってりっぱに飛んでいる」とあざわらった。
一つの官職を全うするほどの知恵や才能を持っている人の自己認識は、このウズラ程度のものだ。戦国時代のある思想家は彼らのことをこのように冷ややかにみて、決して調子に乗らない。世間的な幸福にも目をくれない。天地自然の真理にまたがり、無窮の世界に遊ぶ大人物ともなれば何にも依存しない。「至人には私心がなく、神人には手がらがなく、聖人には名誉がない」のだ。
「神人」の生活と「無用の用」

遠く遥かな山に神人が住んでいる。穀物を食べず、風を吸って露を飲み、雲や霧にまたがって、飛龍をあやつる。その徳はあらゆる物を包みこんで一つにまとめ上げるので、天下統治の事業など造作もない。どんな天変地異にもびくともせず、現実世界のことに思い煩うことはない。
こういう話もある。ヤマネコやイタチは身を伏せては獲物をとり、高いところもへっちゃらだが、罠にかかって死んでしまうことも多い。一方、大きな牛は、ネズミすら捕えられないものの、生き延びてきた。それと同じように、大きいばかりで役に立たない木は、広野にあれば憩いの場にもなり、若木のうちに切り倒されることもない。だから役に立たないことを気に病む必要はないのだ。〔この「散木」は荘子の「無用の用」のシンボルである。〕
いにしえの人の知恵
「生があると同時に死があり、死があると同時に生がある。可があると同時に不可があり、不可があると同時に可がある」。物の対立をなくし斉(ひと)しくする論理、すなわち万物は一体であるという考え方が「斉物(せいぶつ)の理」である。
一つに通じる道を求めていながらものごとが同一であることを理解していない。これを「朝三(暮四)」という。ある猿使いが猿たちにトチの実を「朝は三つ、晩には四つあげよう」というと、猿たちはみな怒った。「では、朝は四つ、晩には三つあげよう」というと今度は喜んだ。ことばも中身も何ら変わっていないはずだ。
聖人は、是と非を調和させ、「両行(対立したものを二つながら生かす道)」を実現する。
いにしえの人の知恵にいう最上の境地とは、「もともと物など存在しなかったとする立場」だ。たとえ物が存在しても、境界などなかったと考え、境界が存在しても、是非の区分はないとする。是非の区分は道を破壊し、愛憎好悪を生じさせる。すべてを自ら得るままにゆだねる。これが斉物の理に従う道だ。
胡蝶の夢
ある日、荘周(荘子)はチョウになる夢を見ていた。気持ちよく飛びながら、自分が何者であるかも忘れていた。やがて目が覚めてみると、自身はまぎれもなく荘周であることがわかる。
「はて、これは荘周が夢でチョウになっていたのか。それともチョウが夢で荘周になっていたのか」――現実的な我と物の境界が取り払われ、夢も現実も混ざりあいそれぞれに変化しあう世界。これこそ「物化(万物の変化)」だ。我を忘れる境地だと言える。
自己の生を全うするために
生命を養う方法

知は限りがないから、限りある人生を費やして知を求めるのは危険だ。善いことをしても名誉に近づくな。悪いことをしても刑罰を受けてはいけない。なにごともほどほどを心がければ天寿を全うできる。