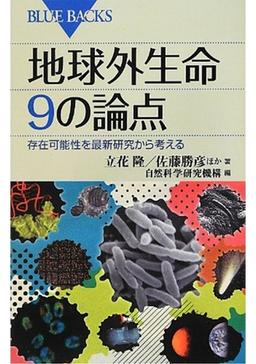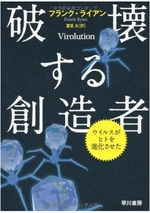地球外生命体へのアプローチの歴史
科学の進歩とともに地球外生命体は「科学」ではなくなっていった

夜空の星を見上げ、この星々のどこかに「生命体」が存在しているのではないか、我々が会いにいくのをずっと待っているのではないか、と思ったことはないだろうか。古の人々も同じように考えていたようだ。たとえば、古代ギリシャの数学者ピタゴラスは宇宙には地球と同じような世界がたくさんあり、それぞれの「住人」がいると弟子たちに語っていたという。日本人になじみ深い、日本最古の物語、竹取物語のエンディングでは月から使者が訪れてかぐや姫を迎えにくる。このように、古来より人間はおおむね地球外生命体の存在を自然なこととして考えていたようだ。
1543年にコペルニクスが「地動説」を唱えたことをきっかけに、この宇宙のなかで地球や人類は「特別な存在ではない」と多くの知識人が考えるようになっていった。中世の代表的な科学者ケプラーは、月には規則的な地形が観察でき、それは高度な文明をもった住人が建設したものだと述べ、宇宙人の存在について活発に議論されるようになっていった。
近代に入ると、もはや宇宙人の存在は常識とされ、実際にどのようにして彼らとコンタクトを取るかが議論されるほどであった。ところが、19世紀後半になると、天体物理学が発達するにしたがって、人々の宇宙への情熱は急速に冷めていく。開発された天体を分析する新しい手法によって映し出されたのは、極めて低温で真空の宇宙空間であり、大気や水の存在すら疑わしく、生命が存在するにはあまりに過酷な環境であった。こうして宇宙人の存在について悲観的に考える立場が支配的となるにつれ、科学者の中でも地球外生命体は「科学」ではなくなっていった。
なぜ我々は、「彼ら」にまだ出会えていないのか―科学者たちが考える3つの答え
しかし、20世紀半ばにはいって、地球外生命体について本気で考え始める科学者が現れた。それは、意外にも原子物理学を専門とし、ノーベル物理学賞を受賞していた物理学者フェルミであった。1950年、ロスアラモス研究所で同僚とランチをとっているときに、彼はこうつぶやいたという。「みんな、どこにいるのだろう」。フェルミは、何か未知の数値を限られた手がかりや論理から概算することを得意としていた。たとえば、「シカゴにピアノの調律師は何人いるのか」をシカゴの人口、1世帯あたりの人数、ピアノを所有している世帯の割合などから推定することができる。こうした手法は「フェルミ推定」と呼ばれ、近年ビジネスの現場でも応用されている。
フェルミは、宇宙の広大さ、宇宙の誕生から現在までの時間などを概算することで、知的な地球外生命体は必ず存在し、しかもすでに何度も地球を訪れているはずだと推定していた。それにもかかわらず、私たちはまだ一度も彼らに会っていない。「みんな、どこにいるのだろう」。フェルミが指摘した、地球外生命体が存在する可能性の高さと、私たちが彼らにまだ一度も遭遇したことがないという事実とのギャップは「フェルミのパラドックス」と呼ばれ、宇宙において我々は特別な存在なのか、あるいはありふれた存在なのかという問いを突きつけた。
科学者たちは、これに対して大きく3通りの答えを出している。