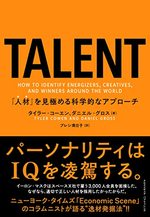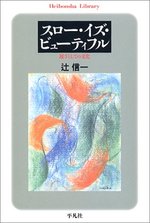脳の地図を書き換える
神経科学の冒険


著者
デイヴィッド・イーグルマン(David Eagleman)
1971年生まれ。スタンフォード大学で「脳の可塑性」講座を教える神経科学者。エミー賞にノミネートされたテレビシリーズ「The Brain」の生みの親で同番組のプレゼンターも務めたほか、非侵襲的なブレイン・マシン・インターフェースを開発するネオセンソリー社のCEOでもある。これまで7冊の著書を上梓し、なかでも『あなたの知らない脳――意識は傍観者である』(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)は世界的なベストセラーとなっている。カリフォルニア州パロアルト在住。
1971年生まれ。スタンフォード大学で「脳の可塑性」講座を教える神経科学者。エミー賞にノミネートされたテレビシリーズ「The Brain」の生みの親で同番組のプレゼンターも務めたほか、非侵襲的なブレイン・マシン・インターフェースを開発するネオセンソリー社のCEOでもある。これまで7冊の著書を上梓し、なかでも『あなたの知らない脳――意識は傍観者である』(ハヤカワ・ノンフィクション文庫)は世界的なベストセラーとなっている。カリフォルニア州パロアルト在住。
本書の要点
- 要点1脳は自らの配線を変え、果てしない変化と適応を続ける「ライブワイヤード」なシステムだ。感覚器官の活動バランスが崩れると脳領域は短時間で乗っ取られる。
- 要点2汎用の計算装置である脳は、ある感覚で別の感覚を代行できる。感覚代行の先には、感覚強化、感覚追加の世界が広がっている。
- 要点3脳は義腕のような新しい体でも、巧みに操る方法を学習できる。
- 要点4自分にとって何が大事かにもとづいて、脳の領土の地図は描かれる。
要約
変化を続ける脳
脳が半分しかない子ども
3歳のマシューが床に倒れたまま目を覚まさなくなったことがあった。さまざまな検査を受けたが悪いところが見つからない。1カ月後の食事の最中、今度は奇妙な表情を浮かべたまま、右腕を頭の上に上げた状態で、1分ほど固まった。神経科で脳の活動を測定すると、てんかんを示す特徴が見つかった。
そのうち発作が2分おきに起きるようになった。入院は年10回に及び、それが3年続いたのちジョンズ・ホプキンス病院へ移り、ラスムッセン脳炎にかかっていることが判明する。この状態での治療法は大脳半球切除術しかない。両親は数カ月悩み、決断した。
少年は排便や排尿のコントロールや、歩くこと、話すことができなくなった。しかし、理学療法と言語療法によって、3カ月後には年齢相応の発達段階に達することができた。それからも、マシューは右手を使ったり歩いたりすることに不自由を抱えている。それでも「普通の生活」を送っており、長期記憶も心配ない。レストランでも問題なく働いている。彼の脳が半分ないことに誰も気づけない。
このようなことが可能なのは、「残された脳が自らの配線を変え、失われた機能を別の領域が肩代わりしたから」だ。スマホの電子回路を半分にしたら電話はかけられない。それが「脳の可塑性」である。この脳のあり方を著者は、「ライブワイヤード(livewired)」という新語で表現している。「果てしない変化と適応を続けながら情報を求めるシステム」であることこそ、脳の本質なのだ。
夢を見る進化的な理由

Natalia Misintseva/gettyimages
ここ数十年の発見で、脳の可塑性についてその変化の驚異的な速さがわかっている。
とある研究では、脳の大々的な変化の速さを調べるため、目の見える人に研究室の環境で5日間目隠しをして点字訓練を受けてもらった。結果は驚くべきものだった。目隠しをしなかった対照群の被験者よりも、点字の細かな違いを感じ分けるのがはるかに上手になったのだ。しかも、目隠しをされた被験者だけが、物体に触れたとき、あるいは音や単語に対して、(一般に視覚野があるとされる)後頭葉も活性化するようになっていた。この現象は実験後1日で消えた。
このように脳、神経は柔軟に変化することで生存に役立つ。しかしそれが裏目に出て、感覚器官の活動バランスが崩れただけで、脳領域が短時間で乗っ取られる可能性もある。地球上にいると、平均12時間サイクルで夜という闇に包まれる。それで唯一不利になる感覚は視覚だけであり、そのハンデに対処するために夢を見ている、というのが著者の仮説だ。
夜間で夢が現れるのはレム睡眠の最中である。脳幹の「橋(きょう)」にある特定のニューロン群が活発化することで、主要な筋肉群が麻痺し、筋肉の活動を停止させると、「脳は実際に体を動かさずとも擬似的に世界を経験できる」のだ。そして脳幹から後頭部へニューロンのスパイク波が伝わり、視覚野を作動させる。
視覚野は、闇の中で自らの領土を守るために自衛手段を進化させたのである。
【必読ポイント!】 脳はどんな入力でも対応できる
感覚代行

Benjavisa/gettyimages
脳は、どこからどんな情報が入力されても、ただその活用法を見出すだけだ。利用できる信号から何ができるかを判断する汎用の計算装置である。
著者はこれを「ポテトヘッドの進化モデル」と呼ぶ。じゃがいも形の人形であるポテトヘッドは、好きなように体のパーツを差し込める。それと同じように、目や耳、指先といった感覚器官は、「プラグ・アンド・プレイの周辺機器にすぎない」。とすれば、この感覚器官だけに頼らなくてもいいはずだ。たとえば、ビデオカメラからのデータを皮膚の触覚に変換するとどうなるだろう。

この続きを見るには...
残り2284/3791文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2023.08.12
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約