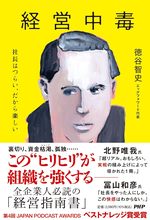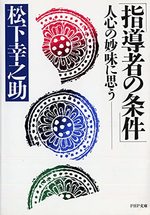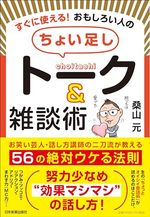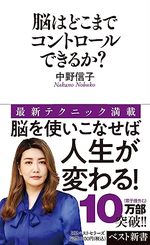業績を最大化させる 現場が動くマネジメント
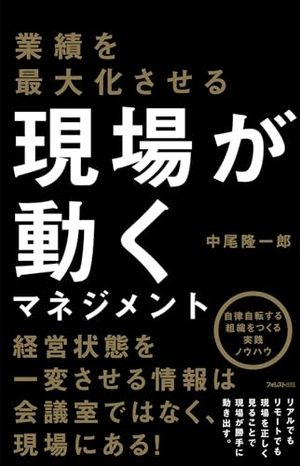
業績を最大化させる 現場が動くマネジメント
著者
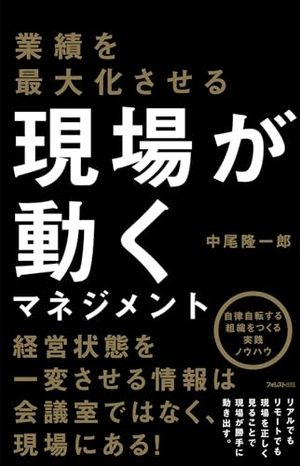
著者
中尾隆一郎(なかお りゅういちろう)
株式会社中尾マネジメント研究所(NMI)代表取締役社長
株式会社旅工房取締役。株式会社LIFULL取締役。株式会社ZUU取締役。東京電力フロンティアパートナーズ合同会社投資委員。LiNKX株式会社監査役。
1964年生まれ。大阪府摂津市出身。1989年大阪大学大学院工学研究科修士課程修了。同年、株式会社リクルート入社。2018年まで29年間同社勤務。2019年NMI設立。NMIの業務内容は、①業績向上コンサルティング、②経営者塾(中尾塾)、③経営者メンター、④講演・ワークショップ、⑤書籍執筆・出版。専門は、事業執行、事業開発、マーケティング、人材採用、組織創り、KPIマネジメント、経営者育成、リーダー育成、OJTマネジメント、G-POPマネジメント、管理会計など。
著書に『最高の結果を出すKPIマネジメント』『最高の結果を出すKPI実践ノート』『自分で考えて動く社員が育つOJTマネジメント』『最高の成果を生み出すビジネススキル・プリンシプル』(フォレスト出版)、『「数字で考える」は武器になる』『1000人のエリートを育てた爆伸びマネジメント』(かんき出版)など多数。Business Insider Japan で「自律思考を鍛える」を連載中。リクルート時代での29年間(1989年~2018年)では、主に住宅、テクノロジー、人材、ダイバーシティ、研究領域に従事。リクルートテクノロジーズ代表取締役社長、リクルート住まいカンパニー執行役員、リクルートワークス研究所副所長などを歴任。住宅領域の新規事業であるスーモカウンター推進室室長時代に、6年間で売上を30倍、店舗数12倍、従業員数を5倍にした立役者。リクルートテクノロジーズ社長時代は、リクルートが掲げた「ITで勝つ」を、優秀なIT人材の大量採用、早期活躍、低離職により実現。約11年間、リクルートグループの社内勉強会において「KPI」「数字の読み方」の講師を担当、人気講座となる。
株式会社中尾マネジメント研究所(NMI)代表取締役社長
株式会社旅工房取締役。株式会社LIFULL取締役。株式会社ZUU取締役。東京電力フロンティアパートナーズ合同会社投資委員。LiNKX株式会社監査役。
1964年生まれ。大阪府摂津市出身。1989年大阪大学大学院工学研究科修士課程修了。同年、株式会社リクルート入社。2018年まで29年間同社勤務。2019年NMI設立。NMIの業務内容は、①業績向上コンサルティング、②経営者塾(中尾塾)、③経営者メンター、④講演・ワークショップ、⑤書籍執筆・出版。専門は、事業執行、事業開発、マーケティング、人材採用、組織創り、KPIマネジメント、経営者育成、リーダー育成、OJTマネジメント、G-POPマネジメント、管理会計など。
著書に『最高の結果を出すKPIマネジメント』『最高の結果を出すKPI実践ノート』『自分で考えて動く社員が育つOJTマネジメント』『最高の成果を生み出すビジネススキル・プリンシプル』(フォレスト出版)、『「数字で考える」は武器になる』『1000人のエリートを育てた爆伸びマネジメント』(かんき出版)など多数。Business Insider Japan で「自律思考を鍛える」を連載中。リクルート時代での29年間(1989年~2018年)では、主に住宅、テクノロジー、人材、ダイバーシティ、研究領域に従事。リクルートテクノロジーズ代表取締役社長、リクルート住まいカンパニー執行役員、リクルートワークス研究所副所長などを歴任。住宅領域の新規事業であるスーモカウンター推進室室長時代に、6年間で売上を30倍、店舗数12倍、従業員数を5倍にした立役者。リクルートテクノロジーズ社長時代は、リクルートが掲げた「ITで勝つ」を、優秀なIT人材の大量採用、早期活躍、低離職により実現。約11年間、リクルートグループの社内勉強会において「KPI」「数字の読み方」の講師を担当、人気講座となる。
本書の要点
- 要点1全体最適な組織を目指す上でのキーワードが「制約条件理論」だ。
- 要点2望ましいマネジメントスタイルは、「トップダウン」と「ボトムアップ」の長所を活かした「ミドル・アップダウン」である。
- 要点3自律自転できる組織を生み出すためには、全員でゴールの認識を揃え、さらにそのゴールに関係する業務を行う必要がある。
要約
なぜ、働き方の多様性が重要なのか
働き方の多様性がもたらすメリット
新型コロナウイルス感染症が2023年5月には5類感染症となり、日本でも日常生活が戻ってきた。それに伴い、各企業ではリモートワークから出社への回帰が進みつつある。
一方、働き方の多様性を高めることは、本来人材の多様性を高めることにつながる。そして、人材の多様性は企業の業績に貢献することが明らかになってきている。
2015年にマッキンゼーが発表した報告書によると、ジェンダーの多様性について最上位4分の1の企業群の方が、最下位4分の1の企業群より業績が15ポイントも高かったという。また、国籍の多様性でも同様に、上位の企業群が下位の企業群と比較して35ポイント高かった。
なぜ、こうした多様性は業績に直結するのか。理由の1つは、アイデアや視点の多様性が生まれるからだ。また、社会的責任の観点で市場から評価されやすく、人材確保でも優位に立ちやすくなっているのだ。
なぜ日本企業は「出社」を求めるのか

Aleutie/gettyimages
多様性は企業にさまざまなメリットをもたらすが、日本企業では同一性を求める傾向が強い。新型コロナウイルス感染症が5類へ分類された後も、画一的に出社を求める企業が続出した。
日本企業が出社を求める理由の1つが「出社こそ仕事である」という文化だ。さらに、社員間のオフィスでのコミュニケ―ションを重視する傾向も根強い。
出社を求める側である経営者・幹部は、得てして会社の近くに居住しているものだ。そのため通勤の負担が低い。一方、大半の従業員は通勤の負担を感じており、リモートワークによって通勤しないことのメリットを痛感した。リモートワークの制度がありながら、実際には利用しにくい状況に、多くの人はストレスを感じている。

この続きを見るには...
残り3784/4512文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2024.03.21
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約