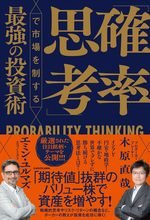百冊で耕す
〈自由に、なる〉ための読書術

著者
近藤康太郎(こんどう こうたろう)
朝日新聞編集委員
作家/評論家/百姓/猟師
1963年、東京・渋谷生まれ。慶應義塾大学文学部卒業後、1987年、朝日新聞社入社。川崎支局、学芸部、AERA編集部、ニューヨーク支局を経て、2021年から現職。新聞紙面では、コラム「多事奏論」、地方での米作りや狩猟体験を通じて資本主義や現代社会までを考察する連載「アロハで田植えしてみました」「アロハで猟師してみました」を担当する。社内外の記者、ライター、映像関係者に文章を教える私塾が評判を呼んでいる。
主な著書に、『三行で撃つ〈善く、生きる〉ための文章塾』(CCCメディアハウス)、『アロハで田植え、はじめました』『アロハで猟師、はじめました』(共に河出書房新社。前著は同社刊『おいしい資本主義』を文庫化)、『「あらすじ」だけで人生の意味が全部わかる世界の古典13』『朝日新聞記者が書けなかったアメリカの大汚点』『朝日新聞記者が書いたアメリカ人「アホ・マヌケ」論』『アメリカが知らないアメリカ 世界帝国を動かす深奥部の力』(以上、講談社)、『リアルロック 日本語ROCK小事典』(三一書房)、『成長のない社会で、わたしたちはいかに生きていくべきなのか』(水野和夫氏との共著、徳間書店)ほかがある。
朝日新聞編集委員
作家/評論家/百姓/猟師
1963年、東京・渋谷生まれ。慶應義塾大学文学部卒業後、1987年、朝日新聞社入社。川崎支局、学芸部、AERA編集部、ニューヨーク支局を経て、2021年から現職。新聞紙面では、コラム「多事奏論」、地方での米作りや狩猟体験を通じて資本主義や現代社会までを考察する連載「アロハで田植えしてみました」「アロハで猟師してみました」を担当する。社内外の記者、ライター、映像関係者に文章を教える私塾が評判を呼んでいる。
主な著書に、『三行で撃つ〈善く、生きる〉ための文章塾』(CCCメディアハウス)、『アロハで田植え、はじめました』『アロハで猟師、はじめました』(共に河出書房新社。前著は同社刊『おいしい資本主義』を文庫化)、『「あらすじ」だけで人生の意味が全部わかる世界の古典13』『朝日新聞記者が書けなかったアメリカの大汚点』『朝日新聞記者が書いたアメリカ人「アホ・マヌケ」論』『アメリカが知らないアメリカ 世界帝国を動かす深奥部の力』(以上、講談社)、『リアルロック 日本語ROCK小事典』(三一書房)、『成長のない社会で、わたしたちはいかに生きていくべきなのか』(水野和夫氏との共著、徳間書店)ほかがある。
本書の要点
- 要点1本は、百冊あればいい。それは、大量の本の中から自分にとっての正典となる百冊を自分の力で選ぶということだ。
- 要点2本棚に深みがあり見栄えの良い本を並べておけば、すぐに読めなくても次第に自分が本に似合う人間になれる。
- 要点3読む本を選ぶときには、自分がはまっている関心事を深堀りするように選ぶと同時に、定評のある必読リストに沿って選び、外からの影響で自分を変えることも必要だ。
- 要点4本を読む人は、人を愛し、自分を幸せにすることができる。だから、本を読むのは、幸せになるためなのだ。
要約
【必読ポイント!】 百冊の本棚の作り方
百冊を選ぶ
本は百冊あればいい。それは、小さな本棚ひとつに収まり、だれでも買えて持てる量だ。
これは、「本は百冊読めばいい」ではない。自分にとってのカノン(正典)となる百冊を選ぶには、一万冊ほどは手に取らなくてはならないかもしれない。本書は、自力で百冊を選べるようになるための方法論である。
最終的にはその百冊さえいらない。頭の中に、百冊の精髄が入っている。そんな状態になっていたい。
速読か、遅読か

standret/gettyimages
本の読み方として、速読が現代人にとっての必須の技術だと言われることもあれば、反対に、遅読こそが大切だと言われることもある。著者の考えは、速読か遅読かという問題は二者択一ではなく、速読する本とじっくり精読するべき本を分けるというものだ。
速読が必要なのは、静かに精読するに値する本を選ぶためだ。テレビやネット、動画は、速読を阻む、「遅すぎる」メディアだ。読者や視聴者の時間を奪い合い、それをカネに変えようと、「見せ方」を工夫する。欲しい情報の前にはCMや演出、課金の案内などが入るが、そこまでの時間や手間をかけて得るべき情報であることはほとんどない。一方、紙の本は、瞬時に全体像を見わたし、行きつ戻りつしながら、適切な場所に高速で移動することができる。速読に最も適したメディアは紙の本であり、速読こそ読書の醍醐味だ。
速読力を養う技術としては、脳内で音を再生せず文字を視覚情報として「見る」こと、漢字だけを追って情報を得ること、文章を目で追うのではなく段落全体を眺めること、目的意識をはっきりさせてキーワードだけを追うこと、すきま時間を使って同時並行で何冊かを読み、多ジャンルの本をまんべんなく読むことなどが挙げられる。
しかし、速読しかできないのはよろしくない。まじめに書かれた本は速読を峻拒する。著者は、実用書や資料は速読するが、小説は速読しないという。小説とはあらすじを追うものではなく、作品に流れる空気を味わうものだからだ。
遅読には遅読のための作法がある。文章そのもののリズムを味わい、グルーヴに乗ること、ドッグイヤーやアンダーライン、余白のメモなどで読書の痕跡を残すこと、意味の取れない本は音読してみること、写経のように書き写して抜き書きすることなどが挙げられる。
本を買うか、借りるか

urbazon/gettyimages
本は買うべきか、借りるべきかというのは、意味のない問題設定だ。どういう本を買い、どういう本を借りて済ますかという基準を自分のなかでつくり上げることが大事だ。

この続きを見るには...
残り3835/4871文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2024.12.08
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約