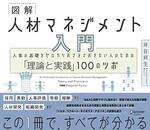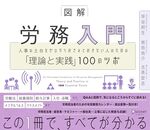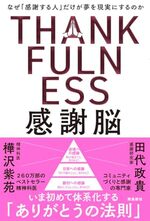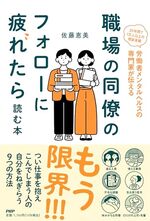マネジメントは嫌いですけど
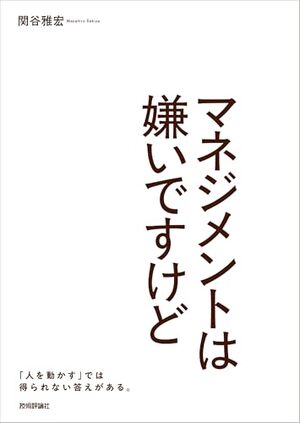
マネジメントは嫌いですけど
著者
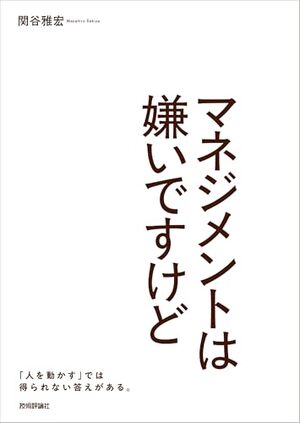
著者
関谷雅宏(せきや まさひろ)
1962年生まれ。
金融企業に新人として入社。お札を数える日々に耐えきれず退職。何かを作り上げる仕事を求めていくつかの職を転々としたのち、小さなソフトハウスでプログラマーの職につく。
2年ほどで会社が倒産した後、当時のユーザー企業に転職。その後、中堅のソフトハウスに転職したが、同僚に誘われ起業。15年間、役員として勤める。
同社は、役員・社員5人程度から、社員50人以上、協力会社を含め200人程度の規模まで拡大。その間、CFOからCTO兼副社長まで経験。常に開発現場に関わり、プログラムを組み、OS・ネットワークからデータベース、ミドルウェアの設計や構築も手がける。
セキュリティ・インシデントの対応をした縁で、某通信会社へ40歳を過ぎてから転職。社内情報処理システムの基盤部署へ配属となる。
「データベースの事故が事業のリスクになる」という上層部の判断から、データベースをはじめとして、ミドルウェアを社員でサポートできる部門を新規設立。経験のない社員に1から学習してもらい、実践を通じてエンジニアとして育てることを中心に、他部門からの信頼を得ることに成功する。ミドルウェア中心の部門を確立させたのち、サーバ、OS、データセンターなどを見る部署と合わせて管理する。その後、社内ネットワーク、などのインフラをすべて統括する責任者となる。責任者となってからも、最後まで自分のパソコンの中でプログラムを動かし続けていた変わり者として、まわりからは不思議な目を向けられていた。
現在は,子会社の管理職として過ごしている。
【X】@Guutara
1962年生まれ。
金融企業に新人として入社。お札を数える日々に耐えきれず退職。何かを作り上げる仕事を求めていくつかの職を転々としたのち、小さなソフトハウスでプログラマーの職につく。
2年ほどで会社が倒産した後、当時のユーザー企業に転職。その後、中堅のソフトハウスに転職したが、同僚に誘われ起業。15年間、役員として勤める。
同社は、役員・社員5人程度から、社員50人以上、協力会社を含め200人程度の規模まで拡大。その間、CFOからCTO兼副社長まで経験。常に開発現場に関わり、プログラムを組み、OS・ネットワークからデータベース、ミドルウェアの設計や構築も手がける。
セキュリティ・インシデントの対応をした縁で、某通信会社へ40歳を過ぎてから転職。社内情報処理システムの基盤部署へ配属となる。
「データベースの事故が事業のリスクになる」という上層部の判断から、データベースをはじめとして、ミドルウェアを社員でサポートできる部門を新規設立。経験のない社員に1から学習してもらい、実践を通じてエンジニアとして育てることを中心に、他部門からの信頼を得ることに成功する。ミドルウェア中心の部門を確立させたのち、サーバ、OS、データセンターなどを見る部署と合わせて管理する。その後、社内ネットワーク、などのインフラをすべて統括する責任者となる。責任者となってからも、最後まで自分のパソコンの中でプログラムを動かし続けていた変わり者として、まわりからは不思議な目を向けられていた。
現在は,子会社の管理職として過ごしている。
【X】@Guutara
本書の要点
- 要点1組織の成果と個人のスキルアップを両立するには、全力で業務に挑まず、20%ほど学ぶための時間と力を残しておくことだ。
- 要点2マネージャーになっても新しい技術を追いかけていい。
- 要点3マネジメントには正解がない。技術的な探求をするように、マネジメントの正解も「自分で探していい」のである。
- 要点4技術者の部下のキャリアパスを考えるのもマネージャーの仕事だ。著者は優秀な部下の評価と報酬を上げるため、「問題解決する姿を役員レベルの人たちに見せる」ことを試みた。
要約
マネージャーになってしまった!
自分自身の心の持ち方
マネージャーとして組織を率いるときに大事になるのは「自分自身の心の持ち方」だ。「こうあってほしい」という理想を当てはめるのではなく、まず目の前の現実を受け入れ、今後どうしていくかを考える必要がある。
著者は「うまくいくかどうかは半々の確率」「仕事は頼んだほうにも責任がある」「ないものを作るのだから、失敗しても今より悪くはならない」「自分がマネージャーを任されたのは実績があるからではない」と考えるようにした。こう考えることで、「自分自身」と「マネージャーという役割」を切り離せるからだ。
成果とスキルアップの両立問題

gilaxia/gettyimages
マネージャーになった著者が最初に取り組んだのは、技術者個人のスキルアップと、業務のアウトプットの両立である。著者の組織の業務は「技術サポート」であったため、アウトプットは「他部門の問題を解決すること」となる。
しかし当然ながら、技術者の能力は均一ではない。こういった場合に組織がやりがちなのは、能力の高いメンバーにフル回転で働いてもらい、成果を上げることだ。
だがこれには問題がある。まず、仕事が能力の高い人たちに集中してしまうこと。そして担当者個人の技術力によって、組織として請け負うサービスの質にバラツキが出ることだ。すると、仕事が人に固定される「属人化」が起き、チーム内に非協力的なムードが漂ってしまう。
著者はそれを避けるべく、次の3つを組織の核に置くことにした。
・アウトプットは組織の時間で換算する
・目指すのは「アウトプットの最大化」ではなく「安定的なアウトプット」
・「技術者を養成すること」を仕事の中に組み込む
次項ではこれらを実現するためにおこなったことを紹介する。
学びの余力を残しておく
通常、アウトプットには最大限の力で取り組むことが期待される。しかし、それでは個人も組織も消耗してしまい、学びや成長にリソースを割くことができない。

この続きを見るには...
残り2678/3480文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.02.21
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約