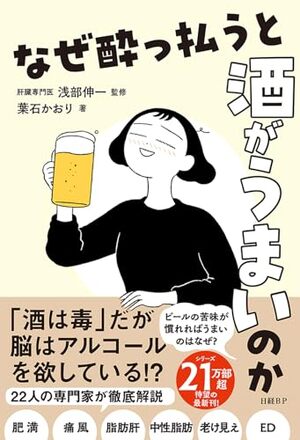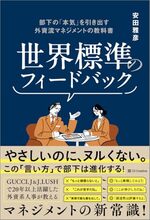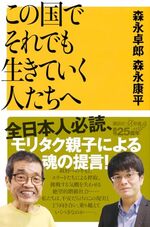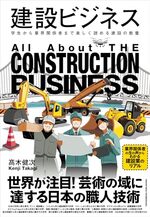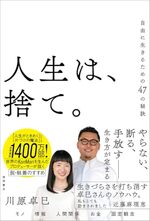なぜ酔っ払うと酒がうまいのか
著者
葉石かおり(はいし かおり)
1966年生まれ。日本大学文理学部独文学科卒業。ラジオレポーター、女性週刊誌の記者を経てエッセイスト・酒ジャーナリストに。「酒と心身の健康」「酒と料理のペアリング」を核に執筆。2024年、京都橘大学健康科学部心理学科(通信)を卒業し、認定心理士の資格を取得。「一生健康で飲む」「酒育」をテーマに、各自治体や企業において社内研修や講演活動を行う。2025年より国税審議会委員に就任。主な著書に『酒好き医師が教える最高の飲み方』『名医が教える飲酒の科学』『生涯お酒を楽しむ操酒のすすめ』など多数。
1966年生まれ。日本大学文理学部独文学科卒業。ラジオレポーター、女性週刊誌の記者を経てエッセイスト・酒ジャーナリストに。「酒と心身の健康」「酒と料理のペアリング」を核に執筆。2024年、京都橘大学健康科学部心理学科(通信)を卒業し、認定心理士の資格を取得。「一生健康で飲む」「酒育」をテーマに、各自治体や企業において社内研修や講演活動を行う。2025年より国税審議会委員に就任。主な著書に『酒好き医師が教える最高の飲み方』『名医が教える飲酒の科学』『生涯お酒を楽しむ操酒のすすめ』など多数。
本書の要点
- 要点1「酒がうまい」と感じる理由は、味覚による情報のほか、生理的・精神的・習慣的な条件が影響している。
- 要点2健康診断における「肝臓の数値」が悪いのは、酒の飲み過ぎが関係している。そのほかにも高カロリーのおつまみや“肝臓に良い”サプリメントも、肝臓の負担になっている可能性がある。
- 要点3飲み過ぎは肌の老化を早めてしまう。1週間飲酒を控えたり、「特別な日」にだけ高いお酒を飲んだりして、減酒を心がけよう。
要約
【必読ポイント!】酒が飲みたくなる理由
酒はなぜうまいのか?
酒を「おいしい」と感じるのはなぜだろうか。
飲み始めたころは苦かったはずのビールも、「本当にうまい」と感じるようになる。健康に悪いと知りつつも、うまいから飲んでしまう。
著者は、食品の味を分析しているユーロフィンQKENの肥田崇氏に、酒のうまさの正体を聞いた。肥田氏によると、人間がおいしいと感じる味覚には五味(甘味、酸味、塩味、うま味、苦味)や渋味・辛味が関わっていて、これらのバランスによって食品の味が決まるのだという。
しかし、同じ酒でもおいしいと感じるときもあれば、イマイチなときもある。その理由は、食品を味わうときの生理的・精神的・習慣的な条件が味に影響するためだという。たとえば、空腹時は糖分が欲しくなるため、マンゴーサワーのような甘いお酒を飲みたくなる。一方、体が疲れているときはレモンサワーのような酸味が欲しくなる。
精神的な条件も関係する。人はストレスがたまると、苦味を欲する傾向があるそうだ。ビールのような苦みのある酒をおいしく感じるのは、そのようなときかもしれない。
飲み慣れている酒がおいしいのは、習慣的な条件に相当する。人は行動するとき「冒険して失敗したくない」というバイアスが働く。そのため定番の酒を選びがちで、それをおいしいと感じるのである。
酒は脳を解放する

JohnnyGreig/gettyimages
飲み始めは理性があるものの、酔ってくると歯止めが利かなくなり、飲みすぎてしまう。さらには、普段はやらないような奇行をしたり、暴言を吐いてしまったりすることもある。
このようなことが起きるのは、酔っ払うと脳の機能が低下してしまうからだ。普段は脳が言動の抑制をしているが、酒が入るとコントロールが利かなくなる。
自然科学研究機構生理学研究所の柿木隆介名誉教授によると、「脳とアルコールは、非常に相性が良い」のだという。これは一体どういうことだろうか?
脳には血液脳関門という“脳の門番”があり、有害物質をブロックしている。しかしアルコールは、血液脳関門をいとも簡単に通過してしまう。胃と腸で吸収された後、あっという間に脳に到達するのである。まるで脳はアルコールを歓迎しているかのようである。

この続きを見るには...
残り3369/4277文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.04.27
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約