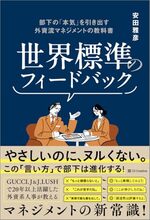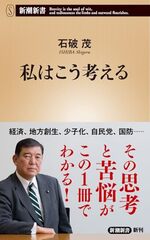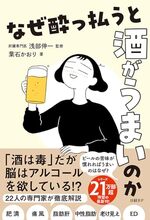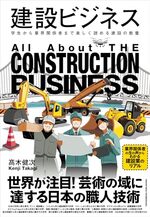知能とはなにか
ヒトとAIのあいだ
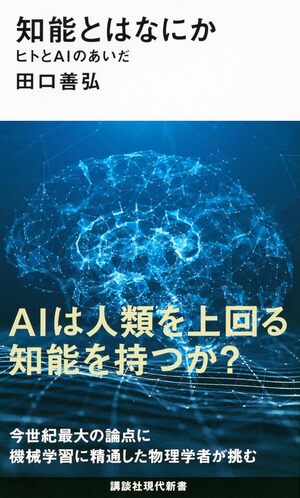
著者
田口善弘(たぐち よしひろ)
1961年、東京生まれ。中央大学理工学部教授。1995年に執筆した『砂時計の七不思議——粉粒体の動力学』 (中公新書)で第12回(1996年) 講談社科学出版賞受賞。その後、機械学習などを応用したバイオインフォマティクスの研究を行う。スタンフォード大学とエルゼビア社による「世界で最も影響力のある研究者トップ2%」に2021年度から2023年度まで4年連続で選ばれた(分野はバイオインフォマティクス)。最近はテンソル分解の研究に嵌まっており、その成果を2019年9月にシュプリンガー社から英語の専門書(単著)として出版した。主な著書に『生命はデジタルでできている』『はじめての機械学習』(ともに講談社ブルーバックス)、『学び直し高校物理』(講談社現代新書)など。
1961年、東京生まれ。中央大学理工学部教授。1995年に執筆した『砂時計の七不思議——粉粒体の動力学』 (中公新書)で第12回(1996年) 講談社科学出版賞受賞。その後、機械学習などを応用したバイオインフォマティクスの研究を行う。スタンフォード大学とエルゼビア社による「世界で最も影響力のある研究者トップ2%」に2021年度から2023年度まで4年連続で選ばれた(分野はバイオインフォマティクス)。最近はテンソル分解の研究に嵌まっており、その成果を2019年9月にシュプリンガー社から英語の専門書(単著)として出版した。主な著書に『生命はデジタルでできている』『はじめての機械学習』(ともに講談社ブルーバックス)、『学び直し高校物理』(講談社現代新書)など。
本書の要点
- 要点1人間の知能は脳の新皮質で生み出される機能とされるが、その具体的な仕組みは未解明であり、知能の定義自体も定まっていない。
- 要点2生成AIは、大規模言語モデル(LLM)などの深層学習によって、人間に近い知的ふるまいを実現しているが、本当に「考えている」わけではない。
- 要点3人間の脳と生成AIは、それぞれ異なる原理で動作し、異なる限界を持った「現実シミュレーター」と考えることができる。
要約
過去の知能研究
そもそも「知能とはなにか?」

Mohammed Haneefa Nizamudeen/gettyimages
現在のところ、脳がどのように知能を生み出しているかははっきりとわかっていない。それどころか「脳の機能としての知能とはなにか」という定義さえ定まっていない。知能は脳の新皮質で生み出されていることについては、研究者のあいだで合意がとれている。しかし、新皮質が何をするのか、なぜ知能が実現しているかについては意見が分かれている。知能が脳の機能であることは古くから知られていたものの、脳の構造と機能の関係を特定することは困難であった。他の臓器とは異なり、解剖して脳を見たところで、どこが何をしているのかわからなかったのだ。
この状況を打開したのは、ある不幸な事故であったとされる。フィネアス・ゲージという米国の建築技師は、作業中に鉄棒が頭部を貫通する事故に見舞われ、事故の前後で大きな人格変容があった。前頭葉を損傷したことで性格が激変したことから、この部位が情動を制御するために重要な役割をになっているのではないかと考えられた。その後も実験により、どの部位がどんな機能を担っているかが決められるようになっていった。
しかし、このアプローチには根本的な問題がある。実際に観測しているのは「知能そのもの」ではなく、「知能が作用した結果」にすぎないからだ。ゲージの例では、実際に情動の不安定さが観測されたのではなく、情動が不安定になった場合に観測されるであろう行動が観測されただけだ。にもかかわらず、この観測から「前頭葉が情動に関わっている」と結論づけられた。「知能」を知能そのものではなく、「知能が働いた場合の行動の変化」でしか定義できないという問題は、生成AIで知能まがいの機能が実現した現在において、大きな混乱の原因になっている。
チューリングテストの限界
「脳の機能」として知能を研究する方針では、知能とはなにかをうまく定義できなかった。意外な方向からこの状況を打開したのは、コンピュータだ。
初期のコンピュータはごく簡単なプログラミングしかできなかったが、それでもある程度の知的作業をこなすことができた。これを用いて人工知能を作ろうとする科学者が現れるのも自然な流れであった。1946年に世界初の汎用コンピュータENIACが開発され、そのわずか10年後のダートマス会議で、人間のように考える機械が「人工知能」と名付けられた。
人工知能の研究には、工学的な開発だけでなく、知能の出現を解明するという理学的な目標もあった。しかし、知能の定義が曖昧なままでは、人工知能が知能を実現しているかの判断ができない。人工知能を作るなかで知能のよい定義が生まれるかもしれないという期待もあったが、知能が定義できなければ知能の実現は人工知能のふるまいをもとに判定することになる。

この続きを見るには...
残り3574/4717文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2025.04.29
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.Copyright © 2025 田口善弘 All Rights Reserved. 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は田口善弘、株式会社フライヤーに帰属し、事前に田口善弘、株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料の活用、およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.Copyright © 2025 田口善弘 All Rights Reserved. 本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権は田口善弘、株式会社フライヤーに帰属し、事前に田口善弘、株式会社フライヤーへの書面による承諾を得ることなく本資料の活用、およびその複製物に修正・加工することは堅く禁じられています。また、本資料およびその複製物を送信、複製および配布・譲渡することは堅く禁じられています。
一緒に読まれている要約