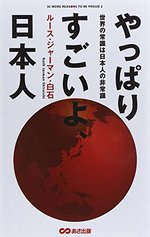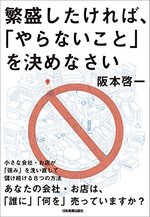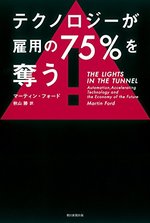毎日の掃除で、会社はみるみる強くなる
必ず人が育つ「習慣化」のルール
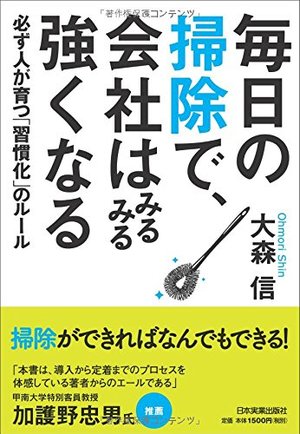
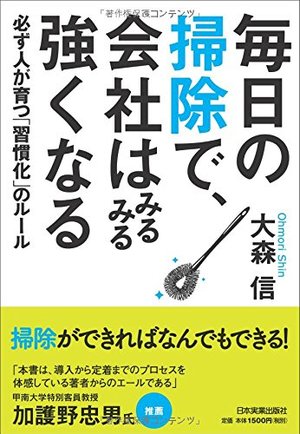
著者
大森 信(おおもり しん)
日本大学経済学部教授。経営戦略論担当。企業における掃除活動に注目するとともに、組織の活性化、新事業創造、プロジェクトマネジメントと掃除との関係性に注目した研究を行なっている。またコンサルタントや商工会議所と組み、 中小・中堅企業における掃除ならびに5Sの効果的な導入について共同研究を重ねている。
2001年に神戸大学大学院 経営学博士課程修了。博士(経営学)。城西国際大学経営情報学部ならびに福祉総合学部専任講師、東京国際大学商学部助教授を経て現職。大阪商工会議所「掃除でおもてなし研究会」座長。
著書に『トイレ掃除の経営学』(白桃書房)、『温泉ビジネスモデル』(同文舘出版、編著)、『新 経営戦略論』(学文社、共著)など。
日本大学経済学部教授。経営戦略論担当。企業における掃除活動に注目するとともに、組織の活性化、新事業創造、プロジェクトマネジメントと掃除との関係性に注目した研究を行なっている。またコンサルタントや商工会議所と組み、 中小・中堅企業における掃除ならびに5Sの効果的な導入について共同研究を重ねている。
2001年に神戸大学大学院 経営学博士課程修了。博士(経営学)。城西国際大学経営情報学部ならびに福祉総合学部専任講師、東京国際大学商学部助教授を経て現職。大阪商工会議所「掃除でおもてなし研究会」座長。
著書に『トイレ掃除の経営学』(白桃書房)、『温泉ビジネスモデル』(同文舘出版、編著)、『新 経営戦略論』(学文社、共著)など。
本書の要点
- 要点1掃除を習慣化する過程では、会社のさまざまな問題や可能性が顕在化していく。掃除を通じて社内の課題や可能性を発見できれば、それは会社を変革する糸口となる。
- 要点2通常業務(本業)とは異なる非通常業務こそ、会社が変化に適応するときに必要になる。非通常業務の中でもとりわけ掃除は地道な活動だが、長期的に取り組むことで会社の基礎力を養うことができる。
- 要点3掃除は社員全員で行うのが理想だ。ただ、若手社員、リーダー、管理職、経営者など、立場によってそれぞれの力を伸ばすための取り組み方がある。
要約
【必読ポイント!】「掃除の力」で社員の心に火をつけよう
掃除の効用とは?

Mathier/iStock/Thinkstock
掃除、特にトイレ掃除を大切にしながら会社を大きく成長させたのが、イエローハットの創業者である鍵山秀三郎氏だ。掃除を始めて50年を超えた現在でも、日々の掃除を続けている。では、掃除には一体どのような効用があるのだろうか。
多くの人が直感的にイメージするのは、仕事環境が整備され、業務効率が向上するといった「掃除そのもの」がもたらす「直接的効用」だろう。これらは比較的短期間で得られるが、会社経営においてより重要なのは「間接的効用」だ。直接的効用は業者が掃除しても得られるものだが、間接的効用は自分たちで掃除をするからこそ得られるもの。つまり、掃除そのものではなく、掃除をする人間によってもたらされる効用なのだ。
例えば、自分たちで掃除をすると什器や備品の耐用年数が向上する。なぜなら、愛着が湧き大切に使うようになることで、少しの異常にも気づけ、早めに修理や修繕をすることにつながるからだ。さらに、大切な什器や備品のある会社そのものに対して愛着が高まったり、同僚と一緒に掃除をすることで社内の連帯感が高まったりしていく。そして、会社や同僚に愛着を持つようになった社員たちの頑張りによって、売上も向上するケースがある。
「習慣化の経営」は掃除が決め手
掃除を継続し、習慣化する過程ではさまざまな問題や可能性が顕在化するだろう。それらを通じて社内の課題や可能性を発見できるようになれば、組織変革の糸口になる。つまり、会社の問題解決力の高さが試される方法のひとつが掃除なのだ。
徹底した掃除を社内で習慣化していくためには、社員の自発性や積極性を引き出していくことが不可欠だ。掃除でも仕事でも社員の自発性や積極性などが低い水準にあるのは、社員に原因があるのではなく、会社や社長にそれを引き出す力がないことに大きな原因がある。
掃除を通じて社員の自発性や積極性を引き出せるようになれば、自ずと仕事においても社員がさまざまなことに挑戦するようになる。また、本来の仕事ではない掃除を習慣化することができれば、仕事により近い、あるいは仕事に直結した案件については習慣化が容易になる。こうした経営を、「習慣化の経営」と著者は称している。
掃除を定着させるためのノウハウ

Oko_SwanOmurphy/iStock/Thinkstock
特定の行動を習慣化するためには、「きっかけ」→「ルーチン」→「報酬」というループを確立させ、さらにこのループを回すためには、「欲求」を湧き起こすことが必要だ。掃除を開始するための具体的なきっかけとしては、社長を筆頭とした経営陣が率先して行動すること。社長が必ず参加できる曜日や時間を設定し、「社長が参加するのだから」ということで社員の納得を促し、会社全体で掃除を始めるきっかけとするとよい。多くの会社が朝に掃除をする場合が多いが、朝に集まることが難しい会社では、必ずしも朝でなくても構わない。一人ではなく、社長を含めたみんなで掃除をすることが大切なのだ。
掃除の「報酬」は、基本的には「ほめること」。たとえば、その日の掃除で目立ってきれいになった場所をほめてもいいし、懸命に掃除をするメンバーの姿をほめてもいい。社長やリーダーにほめられることそのものが大きな報酬となる。
まずは掃除というルーチンのマネジメントで腕試しをしてみよう、というのが本書の狙いでもある。
掃除で会社は元気になる
元気な会社の3条件

Fuse/Thinkstock
著者は、元気な会社であるための条件は少なくとも3つあるという。第1に「業績が良い会社」、第2に「通常業務ができる会社」、

この続きを見るには...
残り2401/3862文字
3,400冊以上の要約が楽しめる
要約公開日 2015.05.07
Copyright © 2025 Flier Inc. All rights reserved.
一緒に読まれている要約